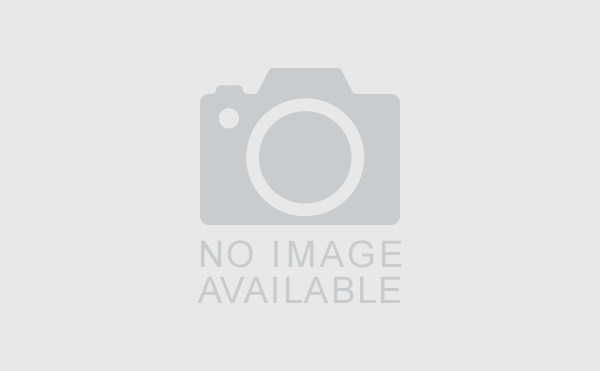【国会レポート】海外から帰国すると、清潔で、時間に正確、親切で安全、そして食事がおいしいことなど、日本の素晴らしさを実感します。【2025年1号】
海外から帰国すると、清潔で、時間に正確、親切で安全、そして食事がおいしいことなど、日本の素晴らしさを実感します。
先日、在京のある国の大使と懇談した際に、日本への赴任経緯を伺いました。その大使は母国で外務省局長を務めていましたが、ある日、大臣に呼ばれ、日本への赴任を告げられたとき、大変驚いたそうです。しかし、実際に日本に来てみると、日本人は礼儀正しく、秩序があり、誠実であり、日本での生活を通じて、自身の振る舞いにも変化があったと語っていました。例えば、人と対面する際には、足を揃え、膝の上にこぶしを置いて話すようになったそうです。確かに、私と懇談している間も、その姿勢を崩さずにおられました。
また、日本語が流暢な別の大使からは、「日本は、人材の育成において誇りを持ち、その方法を世界に示すべきだ」、特に、「日本の小学校は市民を育てる学校である」と話していました。その大使ご自身も、お子さんを日本の普通の小学校に通わせるか、インターナショナルスクールに入れるかについて、ご夫婦で話し合ったそうです。
小学校の先生が足りない
私の知り合いから、「定年を迎えてから68歳になるが、小学校で担任を受け持っている」と聞きました。また、駅でレポートを配布していたところ、定年退職後に補助教諭を務めて
いる元先生に声を掛けられ、「知り合いの校長から、『新学期が始まる前日の3月31日に明日からフルタイムで働けないか』と連絡があった」と教えていただきました。
中学校や高校の場合は教科ごとの採用試験であるため、経済学部や法学部からの受験も可能であることから、倍率が3倍を超えています。しかし、小学校は教育学部卒でないと教員免許を取得することが難しいなど、受験生に限りがある一方で、子どもの頃に憧れた先生を目指して教育学部に入学しても、学年を重ねるうちに、自分の適性や学校現場の実情を知り、最終的に3割(埼玉県45%)が教員以外の道に進んでしまいます。実際、小学校の教員採用試験の全国平均倍率は2.2倍です。
小学校にも教科別指導を
地元の事務所近くのマンションで行われた夏祭りで、大手不動産会社に入社して2年目の方と話す機会があり、どうしてその会社に入社したのか尋ねたところ、「中学や高校の先生になって部活を指導したかったが、教育実習で3か月間、朝7時半から夜7時半まで、昼食の時間もほとんど取れないほど働かなければならず、民間に就職した」と言われました。
「子どもたちと1年かけて一つのクラスをつくり上げることは、子どもたちの成長を実感できるうえ、卒業後も教え子から声を掛けてもらえるなど、先生でしか味わえない感動がある」
と伺ったことがあります。しかし、文科省の調査では、特別な教育的支援を必要とする児童生徒が増える傾向にあったり、いじめや不登校など保護者対応が複雑になったりと、学校現場はさまざまな課題を抱えています。
こうした状況を踏まえ、先生の負担を軽減する必要があります。専門家は、「小学校から中学校へ進学する際に、授業内容に大きな開きがある」と指摘しています。そこで私は、5・6年生の段階から、教科によってはクラス担任とは別に、専門の先生が担当することで負担を軽減できると考え、政策として提案します。
若者に選ばれるための働き方改革
公立の小・中・高校と私立・国立の学校では、勤務条件に大きな違いがあります。公立学校では残業手当が支給されません。これは1971年に「教師の職務の特殊性を踏まえ、時間外手当は支給しない」と定められた制度が、現在も継続しているためです。
1974年には、「教員の給与を一般の公務員よりも優遇すること」を定めた人材確保法が成立して、1980年には一般公務員より約7.4%高い給与となりましたが、現在では一般の公務員とほぼ同水準なってしまい、時間外勤務は事実上のサービス残業になっています。
地元で開かれた商工会議所とハローワークが催した求人・求職のマッチングイベントを視察した際、求職者から圧倒的な人気を集めていた企業を後日訪問しました。そこでは、「優良中小企業を目指す」という経営目標を掲げ、多様な働き方に対応するために男性社員の育児休業制度を導入し、有給休暇の取得率を高め、長時間残業を減らすために作業効率化を進めるなど、若手社員が求める制度を積極的に整備して社内改革を行っていました。
また、私の知人が経営する地元の製造業では、ご子息が30代になったのを機に大手企業から呼び戻し、社内改革を任せたそうです。給与を公務員並みに設定し、退職金制度を整備するとともに、有給休暇の取得率を向上させ、残業時間を適切に調整した結果、優秀な人材を採用できるようになったと聞いています。
2026年1月から公立学校の給与は段階的に引き上げられ、2030年度までに現行より7%ほど高くなることが決まっています。
学校の先生は人を育てる尊い仕事ですが、現在の業務量は膨大です。教師としての仕事とそうでない仕事とを見直して、負荷を軽減するなど若い世代にとって魅力的な職場にするとともに、今後は教職員の定数を増やすことも必要で、良い人材を獲得するためには、採用試験の受験者を増やすことも課題となります。大学卒社会人で小学校の先生を目指す方に、1から2年間の教職課程を設け、同講座を国の職業訓練の一つに指定することを提案します。公的な職業訓練では受講料は掛かりません。
共通体験が紡ぐ社会の絆
米国や欧州では社会の分断が深刻化していると報道されています。分断が進むと社会の統一性が脅かされ、国内に対立が生じ、社会全体が弱体化してしまいます。例えば、その結果として乳幼児死亡率が上昇する恐れがあるでしょう。日本の乳幼児死亡率は世界で4番目に低く、大国では圧倒的に低い国(千人当たり日本2.31、米国6.18、ロシア5.73)なのです。
国民が共通の体験や認識を共有することが極めて重要です。私が育った時代には中学受験をする子どもはほとんど見当たらず、中学校までは親の職業などを見れば、まさに社会の縮図ともいえる環境でした。しかし、現在では中学から私立へ進学する子どもが少なくありません。だからこそ、少なくとも小学校の6年間、地域のさまざまな家庭の子どもたちが同じクラスで学ぶことは、将来の社会基盤を築く大きなきっかけになると考えます。
公教育、とりわけ小学校における教育を手厚くすることは、「国民を育てる」うえで最重要なのです。そのためにも、これから教職をめざす若い世代が期待する働き方や職場環境を整え、生徒の人格形成に深い影響を与える教育者としての務めを果たせるよう、公教育の充実を図っていきます。