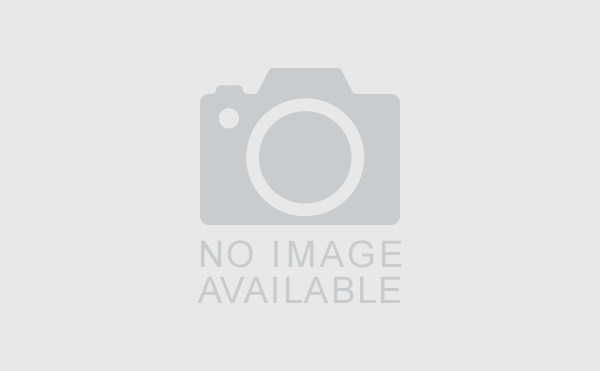第216回国会 衆議院 予算委員会 第3号 令和6年12月10日
令和六年十二月十日(火曜日)
午前八時五十七分開議
出席委員
委員長 安住 淳君
理事 井上 信治君 理事 高木 啓君
理事 牧島かれん君 理事 山下 貴司君
理事 岡本あき子君 理事 奥野総一郎君
理事 山井 和則君 理事 三木 圭恵君
理事 浅野 哲君
伊藤 達也君 稲田 朋美君
井野 俊郎君 鬼木 誠君
国光あやの君 河野 太郎君
國場幸之助君 後藤 茂之君
小林 茂樹君 齋藤 健君
新藤 義孝君 田所 嘉徳君
田中 和徳君 谷 公一君
田野瀬太道君 土屋 品子君
寺田 稔君 中谷 真一君
西田 昭二君 西銘恒三郎君
平沢 勝栄君 深澤 陽一君
福田かおる君 古屋 圭司君
山田 賢司君 今井 雅人君
大島 敦君 大塚小百合君
大西 健介君 岡田 悟君
神谷 裕君 川内 博史君
黒岩 宇洋君 近藤 和也君
酒井なつみ君 重徳 和彦君
階 猛君 杉村 慎治君
高松 智之君 長妻 昭君
西川 厚志君 波多野 翼君
本庄 知史君 眞野 哲君
水沼 秀幸君 山 登志浩君
米山 隆一君 早稲田ゆき君
東 徹君 空本 誠喜君
徳安 淳子君 西田 薫君
林 佑美君 石井 智恵君
長友 慎治君 橋本 幹彦君
大森江里子君 河西 宏一君
西園 勝秀君 沼崎 満子君
山口 良治君 櫛渕 万里君
田村 貴昭君 緒方林太郎君
…………………………………
内閣総理大臣 石破 茂君
総務大臣 村上誠一郎君
法務大臣 鈴木 馨祐君
外務大臣 岩屋 毅君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 加藤 勝信君
文部科学大臣 あべ 俊子君
厚生労働大臣 福岡 資麿君
農林水産大臣 江藤 拓君
経済産業大臣
国務大臣
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 武藤 容治君
国土交通大臣 中野 洋昌君
環境大臣
国務大臣
(原子力防災担当) 浅尾慶一郎君
防衛大臣 中谷 元君
国務大臣
(内閣官房長官) 林 芳正君
国務大臣
(デジタル大臣)
(規制改革担当) 平 将明君
国務大臣
(復興大臣) 伊藤 忠彦君
国務大臣
(国家公安委員会委員長)
(防災担当)
(海洋政策担当) 坂井 学君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)
(共生・共助担当) 三原じゅん子君
国務大臣
(経済財政政策担当) 赤澤 亮正君
国務大臣
(クールジャパン戦略担当)
(知的財産戦略担当)
(科学技術政策担当)
(宇宙政策担当)
(経済安全保障担当) 城内 実君
国務大臣
(沖縄及び北方対策担当)
(消費者及び食品安全担当)
(地方創生担当)
(アイヌ施策担当) 伊東 良孝君
内閣府副大臣 瀬戸 隆一君
財務副大臣 斎藤 洋明君
国土交通副大臣
兼内閣府副大臣
兼復興副大臣 高橋 克法君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 岩尾 信行君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 古谷 一之君
政府参考人
(内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官) 北尾 昌也君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 松家 新治君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 高橋 謙司君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官) 柿田 恭良君
政府参考人
(内閣府宇宙開発戦略推進事務局長) 風木 淳君
政府参考人
(こども家庭庁成育局長) 藤原 朋子君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 阿部 知明君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 大沢 博君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 竹村 晃一君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 大河内昭博君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 河邉 賢裕君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 堀内 義規君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 黒田 秀郎君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 間 隆一郎君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 前島 明成君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 井上誠一郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 浦田 秀行君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長) 伊吹 英明君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局長) 野原 諭君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 山本 和徳君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 五十嵐徹人君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 大和 太郎君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 青木 健至君
政府参考人
(防衛装備庁長官) 石川 武君
予算委員会専門員 中村 実君
―――――――――――――
委員の異動
十二月十日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 井野 俊郎君
国光あやの君 西田 昭二君
小林 茂樹君 田野瀬太道君
深澤 陽一君 新藤 義孝君
大西 健介君 岡田 悟君
神谷 裕君 高松 智之君
酒井なつみ君 西川 厚志君
本庄 知史君 長妻 昭君
米山 隆一君 重徳 和彦君
空本 誠喜君 東 徹君
前原 誠司君 徳安 淳子君
長友 慎治君 石井 智恵君
赤羽 一嘉君 山口 良治君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 中谷 真一君
新藤 義孝君 深澤 陽一君
田野瀬太道君 小林 茂樹君
西田 昭二君 國場幸之助君
岡田 悟君 大西 健介君
重徳 和彦君 米山 隆一君
高松 智之君 山 登志浩君
長妻 昭君 本庄 知史君
西川 厚志君 波多野 翼君
東 徹君 空本 誠喜君
徳安 淳子君 林 佑美君
石井 智恵君 長友 慎治君
山口 良治君 西園 勝秀君
同日
辞任 補欠選任
國場幸之助君 国光あやの君
中谷 真一君 福田かおる君
波多野 翼君 眞野 哲君
山 登志浩君 水沼 秀幸君
林 佑美君 前原 誠司君
西園 勝秀君 沼崎 満子君
同日
辞任 補欠選任
福田かおる君 田所 嘉徳君
眞野 哲君 杉村 慎治君
水沼 秀幸君 大塚小百合君
沼崎 満子君 赤羽 一嘉君
同日
辞任 補欠選任
田所 嘉徳君 鬼木 誠君
大塚小百合君 神谷 裕君
杉村 慎治君 酒井なつみ君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
令和六年度一般会計補正予算(第1号)
令和六年度特別会計補正予算(特第1号)
令和六年度政府関係機関補正予算(機第1号)
――――◇―――――
○安住委員長 これより会議を開きます。
令和六年度一般会計補正予算(第1号)、令和六年度特別会計補正予算(特第1号)、令和六年度政府関係機関補正予算(機第1号)、以上三案を一括して議題とし、基本的質疑に入ります。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官北尾昌也君、内閣府地方創生推進室次長松家新治君、内閣府政策統括官高橋謙司君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官柿田恭良君、内閣府宇宙開発戦略推進事務局長風木淳君、こども家庭庁成育局長藤原朋子君、総務省自治行政局長阿部知明君、総務省自治財政局長大沢博君、総務省国際戦略局長竹村晃一君、出入国在留管理庁次長杉山徳明君、外務省大臣官房審議官大河内昭博君、外務省総合外交政策局長河邉賢裕君、文部科学省研究開発局長堀内義規君、厚生労働省社会・援護局長日原知己君、厚生労働省老健局長黒田秀郎君、厚生労働省年金局長間隆一郎君、農林水産省農村振興局長前島明成君、経済産業省大臣官房審議官井上誠一郎君、経済産業省大臣官房審議官浦田秀行君、経済産業省製造産業局長伊吹英明君、経済産業省商務情報政策局長野原諭君、中小企業庁事業環境部長山本和徳君、国土交通省鉄道局長五十嵐徹人君、防衛省防衛政策局長大和太郎君、防衛省人事教育局長青木健至君、防衛装備庁長官石川武君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安住委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
○安住委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井上信治君。
○井上(信)委員 皆様、おはようございます。
予算委員会の与党の筆頭理事を務めます井上信治でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
この予算委員会、三十年ぶりの野党の予算委員長、そしてまた少数与党ということで、委員会運営も大変厳しい状況にあると認識をしておりますけれども、是非、委員長には委員長の御指導をしっかりいただきながら、また、山井野党筆頭を始めとして、理事の先生、委員の先生方の御協力をいただいて、私もしっかり頑張ってまいりたいと思います。
そして、まずは先週、予算委員会が開会をされました。そして、安住委員長の方で、与野党に限らず、例えばやじへの対応であったり、あるいは質問時間の超過などを厳しく御指導いただきまして、そういう意味では、本当に不偏不党、中立公正に委員長として差配をしていただいたということ。安住委員長は、何といっても立憲民主党の国対委員長を務め、あるいは財務大臣も務めたということで、大変経験豊富で、そして、本当に円熟した尊敬すべき政治家だと思っておりますので、引き続き、当然のこととは思いますけれども、しっかり差配をしていただきたい、期待をしております。
またあわせて、山井筆頭にも、ここのところ連日、断続的に筆頭間協議を誠実に対応していただいております。そういう意味では、今のところ順調にやらせていただいておりますけれども、是非お願いをしたいと思います。
そして、石破総理におかれましても、まさに少数与党という中で、国会答弁など、本当に丁寧に、誠実に対応していただいていると私は認識をしております。しっかりと、与野党それぞれ、主義主張をぶつけて政策をぶつけ合う、そして、お互いに歩み寄れるところは歩み寄って政策を前に進めていくということ。これは今、少数与党だからそのようなことが言われておりますけれども、考えればこれは当然のことだと思うんです。別に与党が多数であっても、こういった姿勢というものは非常に重要だと思っています。総理も今うなずいていただきました。
とりわけ、石破総理は、総理に就任する前から、やはり国民の声を聞くことが大事だということ、そして、その考えに基づいて政策をつくり、行動をされてきたわけです。そういう意味では、与党でも野党でも、国民の代表者としての声をしっかり聞いて丁寧に対応していただく、これをやっていただいていると思います。
こういったことを踏まえて、この予算委員会、国会にかける、そういった状況についての総理の意気込み、考え方をいま一度お示しをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○石破内閣総理大臣 今から十三年ぐらい前のことになりますでしょうか、私は山井さんの席に座っておった。そのときの予算委員長は、鹿野道彦先生であったり、中井洽先生でありました。それで、今、井上委員がおっしゃったように、野党もすごく大事にしていただいたというのがあります。
そのときに、私は、鳩山総理や、あるいは菅総理や野田総理に最初に申し上げたのは、この時間は総理の時間でもなければ私の時間でもない、この質疑の時間は。総理の時間でもなければ私の時間でもなくて、これは主権者たる国民の時間なのだと。この国民の時間をどうやってきちんと有効に使うかということを考えましょうねということで、いい議論をさせていただいたと思っております。
やはりそういう認識をもう一回きちんと持ちたいと思っておりまして、言いっ放し、聞きっ放しではない、本当に、賛成はしてもらえないかもしれないけれども、それでも、政府の言うことは分かったよ、でも賛成できないよというような、そういう議論であるべきかなと私は思っておるところでございます。
○井上(信)委員 ありがとうございました。是非そういう姿勢で今後ともお願いをしたいと思います。
それでは、補正予算案の質疑に移ります。
まず、石破総理は、十月十五日、衆議院選挙の公示日において、街頭演説で、一般会計の歳出総額で約十三・二兆円だった昨年度の補正予算を上回る規模を編成したいと述べられました。そして、その後、実際に、一般会計ベースで十三・九兆円の規模、今回の補正予算が編成をされた。まさに昨年度を少し上回る規模であった。そういうことから、これは規模ありきではないか、こういった批判が一部の野党の皆さん、あるいはメディアから寄せられております。
しかし、私が思いますのは、そうはいっても、やはり予算において規模というものは非常に重要だというふうに思っています。その予算規模の大きさというものが、当然のことながら、経済効果として大きな影響を与えるということになります。
例えば、直近の補正予算で見ても、令和四年度の補正予算は一般会計ベースで二十九・一兆円、この予算に対して実質四・六%程度のGDPの押し上げ効果があった。令和五年度では十三・一兆円の予算に対して三・五%程度のGDP押し上げ効果、これが見込まれていて、今回は十三・九兆円に対して三・七%ということで、やはりここは対応をしているということだと思います。
ですから、この予算案の編成に当たりまして、やはり十分な規模をしっかりと確保すること、あるいは、規模感をちゃんと示すべきだ、こういった意見も必ずあるということです。ですから、今回の補正予算案に関しては、私は、適正な、必要十分な規模をしっかり確保しているということで、そこは評価をしたいと思います。
ただ、他方で、当然のことながら、予算案の中身として、やはりそれぞれ個別個別、緊要な予算をしっかりと計上していくということが大切だと思っております。そういう意味では、現在、なかなか物価高騰によって国民生活が厳しいということ、そして、経済全体も、今、明るい兆しも見えておりますけれども、今まさに、コストカット型経済から、これから高付加価値型の成長経済に移行させていく、まさに今が正念場でありますから、やはり十分な、適正な規模が必要だということであります。
こういったことに関しましてどのようにお考えか、総理のお考えをお示しください。
○石破内閣総理大臣 最初に規模ありきということではございません。
補正予算を組むからには、補正予算にふさわしい緊要性というものが必要であって、その一つは何かというと、まさしくデフレ型の経済、コストカット型の経済から、付加価値をつけていく形の経済に変えていくということにおいて、この補正予算の持つ意味は大きいということが一つ。
もう一つは、地方創生二・〇ということでありますが、地方創生というものをもう一度、リスタートというんですかね、もう一回再起動させたいと思っております。それは来年度の当初からでは駄目で、この補正予算からその勢いをつけていくということが必要だというふうに判断をいたしました。これが二番目。
三番目は、やはり能登半島震災というものを念頭に置かねばならない。もちろん、予備費で対応をずっと切れ間なくしてまいりました。しかしながら、本格的な能登の復旧復興のためには、やはり補正予算という形で、予備費では対応できないものをやっていかねばならないと考えております。
一つはデフレの経済からの脱却。もう一つは地方創生の再起動。そして、能登半島の復興復旧を本格的なものにする、予備費では足りない。そういうようなことを積み上げたものでございまして、規模ありきということでは全くございません。
○井上(信)委員 緊要性に関しましても、総理から答弁をいただきました。
補正予算でありますから、これは当然のことながら、財政法上もやはり緊要性があるもの、これを計上していくということになります。ですから、そういう意味で、この補正予算案の中にも、総理がおっしゃったこと、それから、例えば足下、今、国民生活は非常に逼迫をしておりますから、国民に対して、例えば低所得者に対する給付金、あるいは電気、ガス、ガソリンなどへの補助金、こういったものは今すぐ手当てをしなければいけないということで、ある意味、非常に分かりやすい緊要性があるかと思います。あるいは総理がおっしゃったような能登半島の復旧復興、これはまさに一刻も早くということですから、当然のことながら緊要性はある。こういったような分かりやすい個別の予算もあります。
しかし、他方で、その他の部分に関して、本当にこれは補正予算で必要なのか、むしろ来年度予算、当初予算でも十分間に合うではないかとか、あるいは先ほどから山井筆頭が言っているような、基金も幾つかあります。こういったものに関して、これは本当に補正予算に盛り込むことがふさわしいかどうかということ。
こういった一部の批判がありますから、これに対して、そうではないということ、それをしっかり政府の方で、加藤大臣の方からお示しをいただきたいと思います。
○加藤国務大臣 今総理からお話がありましたように、あるいは委員から御指摘があるように、経済もいい方向に流れる兆しが見える、それを賃上げと投資が牽引する成長型経済に移行していく、まさに分岐点にある。そうした思いの中で、前向きに、国民一人一人が実際の賃金、所得の増加という形で豊かさを感じられるようにするため、総合対策を講じ、そしてそれに必要な補正予算を計上させていただいております。
具体的には、家庭の電気使用量の最も大きい時期である一月に間に合うように、冬期の電気、ガス代の支援を行う。あるいは、今、物価高の影響を受けておられる低所得世帯の皆さん方にも速やかに給付金が支給できるよう、補正予算後できるだけ早期に開始をしていきたい。また、重点地方交付金についても、これから厳冬期を迎えるわけでありますから、それを念頭に灯油支援メニューなどを新たに追加し、地方自治体の早期の予算化を支援していく。さらには、能登の復旧復興、こうしたまさに緊要性のあるものも含まれております。
それから、それ以外、いろいろな基金のお話もあります。これについても、例えば基金については、一つの考え方をこれまでもお示しをさせていただいている中で、本当に必要なもの、この補正において計上しなきゃいけない、それをしっかり精査した上で必要な予算額を計上させていただいたところであります。
○井上(信)委員 ありがとうございました。
時間の関係上、個別のそれぞれの予算項目について一つ一つ緊要性を確認するということは私の質疑ではできませんけれども、恐らくこれからの質疑の中で他の質問者がいろいろお聞きになると思いますので、そこは丁寧に説得力ある説明をいただきたいと思っています。
今朝の理事会でも、やはり野党の皆さんの方からは、修正案の用意もあるといったような御発言もあります。そういったところがまさに修正案の中身となるというようなことを想定ができますから、そこはしっかり、理解できるように是非御説明の方をお願いしたいと思っています。
それから、能登半島の復旧復興について質疑を移りたいと思います。
十一月の十九日に、まさにこの予算委員会の理事メンバーで、能登半島の地震、豪雨の被災地である石川県の視察をしてまいりました。被災現場を視察するとともに、仮設住宅で避難住民の皆様と意見交換をして、そして切実な要望の声を伺ってまいりました。
やはり、今回の能登半島の地震、豪雨、この大きな特徴といたしましては、本当に、お正月という大変なときに地震が起きてしまったということ、そして、それからまだ九か月余りしかたっていない中で、その被災地に集中豪雨、これが起きてしまった、いわば二重の災害であります。更につけ加えれば、やはり奥能登ですから、そういう意味では、大変な人口減少や、あるいは少子高齢化、そして過疎化の状況にある、なかなか道路などのインフラも整っていない。そういう中での復旧復興、厳しい条件がたくさんあるというふうに考えております。
ですから、そういう意味で、今までの自然災害と比較をしても手厚い、そして迅速な復旧復興を是非お願いしたいと思います。
そして我々、石川県の馳浩知事とも意見交換をいたしまして、十一項目にわたる要望が寄せられました。そして私からも、馳知事には、この十一項目の中で、全てといえば全てだとは思いますけれども、これから補正予算の審議に当たって、最優先課題、是非とも補正予算でやってもらいたい課題は何ですかという質問をいたしました。
そのときにお答えがあったのは、宅地や農地の堆積土砂撤去、これを是非盛り込んでもらいたいと。それはある意味当然だと思います。土砂を撤去しなければ、いわば何もできないということであります。逆に言えば、土砂撤去さえまだ十分に実現できていないということですから、これは必ず、早急にやっていただきたいというふうに思っています。
そして、能登半島の復旧復興ですけれども、一部、やはり野党の皆さんやあるいはメディアの方々から言われているのは、なぜ今まで予備費で対応して、補正予算の編成が遅れてしまったのかといったようなことが言われております。
ただ、私が思いますに、七回の予備費ということでやってまいりました。ですから、緊急に、とにかく早くやらなければいけないからこそ予備費で対応したということは、これは一定の理解を示します。ただ他方で、やはり財政民主主義の原則もありますから、早急に補正予算を編成をして、そしてそこでしっかり手当てをしていくべきだったのではないかといった思いは私もあります。
ただ、衆議院の解散・総選挙があったとか、いろいろな事情もあります。その上で、今回この補正予算の編成ということになったわけですから、逆に言えば、このタイミングで必ずしっかりやっていかなければいけないということだと思います。
るる申し上げましたけれども、この補正予算案における能登半島の復旧復興について、総理のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○石破内閣総理大臣 補正予算をなぜ組むかということですが、御指摘のように、予備費でその場その場で可能な限りの対応は行ってまいりました。しかしながら、本格的な復興復旧に入っていくためには、やはり補正予算というもので対応しなければならぬということでございます。
そうしますと、補正予算というのは、これは党首討論でも申し上げたと思うんですが、実際に補正予算を組む、そして御審議をいただく、成立をする、それまでに最低二か月ぐらいはかかるものでございます。そこにおいて、まさしく今御審議をいただいているわけですが、その中身は本当に補正予算にふさわしいものであり、能登の復興に資するものであるかということの審議をするためにこの国会をやっていただいているわけでございます。そこにおいて、本当にこれは真に必要なものだということになりますれば、その執行を早くやっていかねばならない。
それは、予備費というのは予備費で使い便利はいいのですけれども、どうしても予備費としての限界というものはございます。本格的な復旧復興のために補正予算が必要だと私どもは判断をしておるところでございます。
○井上(信)委員 私もまさに総理のおっしゃるとおりだと思います。ですから、予備費で対応ということは、とにかく緊急に手当てをしなければいけなかった。ただ、その上で、今回、補正予算、本格的なものを組んだわけですから、しっかり能登半島の復旧復興に取り組んでいただきたいと思っています。
それで、参考までに一例を申し上げたいんですけれども、実は、私の地元、東京都の青梅市というところですけれども、能登半島、輪島市にある日本航空学園石川、日本航空大学校石川、これが避難をされておられます。
やはり能登キャンパスが使えなくなったということで、そもそも全寮の学校ですから、それが避難地を探しておりまして、東京中を探した結果、私の青梅市に、ある大学が撤退をした跡地があったということで、そこに移転をできないかといったお話がありまして、そして、関係者の協力をいただいて、移転することができたわけです。
学生、そして教職員を含めて八百人以上の方が今避難をされているということで、なかなか、慣れない地で学校生活を送っているわけですから、大変な状況にありますけれども、我々地元の青梅市民といたしましては、歓迎をするとともに、しっかり応援をしていこうということでやっております。
ただ、なかなか大変だったのは、今、大学の跡地をお借りしている。これは無償で三年間ということでお借りをしておりますが、実は十年近く前に撤退したものですから、そのいろいろな修繕など、これについても非常にお金がかかりました。それから、当然のことながら、能登キャンパス、こちらの方の修繕も非常にお金がかかる、時間もかかる。国の方で二分の一の補助、これをやっていただいていますので、それは大変感謝をいたします。
ただ、考えれば分かるとおり、やはり学校ですから、学生の皆さんですから、二年か三年かすると卒業をしてしまう。ですから、そういう意味でも、とにかく復旧復興を早くしなければ、貴重な学生時代を避難生活の中で送ってしまうということになりますから、こういったことは一例ですけれども、やはり復旧復興というのはとにかく迅速なことが大切だということで、是非取組を加速化していただくようにお願いを申し上げたいと思います。
それから、次に、さっき総理からも少し御紹介がありましたけれども、地方創生についてお伺いしたいというふうに思っています。
総理の地方創生にかける思いというもの、非常に大きいものと理解をしております。総理が初代地方創生大臣に着任された二〇一四年以降、様々な取組をしていただいて、例えば、三百を超える市区町村で人口が増加をした。あるいは、移住支援事業を活用した移住者数は昨年度七千七百人に上った。また、企業版を含むふるさと納税についても、返礼品の在り方などについて検討は必要だと思いますけれども、今や制度が定着し、活況を呈しております。あるいは、TSMCの熊本進出、ラピダスの北海道進出など、企業の移転によって地域の経済力が向上している。そんないわば成功例、これも多く見られているということで、私も高く評価をしております。
ただ、他方で、総理は、地方創生二・〇ということで、地方創生をいわばバージョンアップしていくんだということをおっしゃっております。先週の質疑でもありました。ただ、私も、私自身が勉強不足なせいか、いま一歩、今までの地方創生、これとの違い、いわば今までの地方創生に何が足りなくて、何が課題であって、それを今回の地方創生二・〇ではどのように変えて、より地方創生を推進していくことができるのか。
こういったことにつきまして、いま一度お答えを、御説明をお願いしたいと思います。
○石破内閣総理大臣 私ども、田中角栄先生の列島改造、大平正芳先生の田園都市構想、竹下登先生のふるさと創生、地方の発展策というのはやってきましたし、列島改造論は昭和四十七年の本ですが、一極集中の是正ということは、そこからもう書かれているわけですね。そういう問題意識をみんな持ってやってきました。
ただ、それは経済が伸びて人口が増えていた時代の発想だったんですよね。だけれども、今は、経済は何とか頑張りますが、そんなに急激な伸びが見通す範囲で見込めるわけではない。人口は、このままいけば、あと八十年たてば日本人は半分になるという、経済は伸びません、人口は減りますという、全くかつてとは違う状況の中で地方創生というプロジェクトをやろうとしておるわけで、十年前から始めました。
多くの歴代大臣が一生懸命に取り組んできて、いろいろな成果は出てまいりました。だけれども、東京への一極集中は止まらない、地方の人口減少は止まらないということは歴然たる事実であって、これをどうやって止めるかということを考えたときに、もう一度原点に返ってみると、若い方、女性の方に選ばれる地方というのは一体何なんだろうかということ。そして、第一次産業であれ、サービス業であれ、地方の持っているポテンシャルの高い部分をどうやって最大限に引き出していくのかということ。首都直下型地震とか南海トラフとかいろいろ言われますが、東京の過度の集中というものを、そういうリスクをどうやって減らしていくかということも考えていかねばなりません。東京対地方という構図ではなくて、日本全体をどのようにしていくのかという観点から、今度の地方創生二・〇というのはやりたい。
予算を倍額すれば何でもできるという話じゃないだろう、よく承知をいたしております。そういうふうな考え方に基づいて、日本全国四十七都道府県、千七百十八市町村、青梅なら青梅、そしてまた奥多摩なら奥多摩、檜原なら檜原、やはり檜原なら檜原なりの、どうしたらよくなるんだという知恵があるはずなんです。それは東京都庁で考えても分からないし、そういうことを全部で考えていただくということが大事なのであって、何を大事だと考えているかというふうにお尋ねがありましたので、これを大事だと考えている。これが質疑というものでございます。
○井上(信)委員 ちゃんと私の質問に答えていただいて、質疑を行っていただいて、感謝を申し上げたいと思います。重ねて、私の地元の青梅市、奥多摩町、檜原村まで御紹介をいただきまして、ありがとうございます。
今、総理のお話にもちょっとありましたけれども、地方創生を語るときに、東京一極集中の是正、こういったことが必ず出てまいります。私が東京選出だから言うわけではありませんけれども、これはなかなかニュアンスが難しいと思っておりまして、何か東京一極集中の是正といいますと、これは東京対その他、都会対地方、こういったような対立構造で語ってしまうと、私は、それは道を誤ってしまうというふうに思っています。
東京も、やはり中央と地方という構図であれば、当然地方の一つであります。あるいは、御紹介をいただいたように、私のところは東京の一番西の方です、山間部であります。町や村のような過疎地もあります。自然は豊かで、あるいは文化もたくさんあります、すばらしいところですけれども、やはり少子高齢化、人口減少、そして経済の低迷、そういったことに苦しんでいる典型的な地方の一つであると思っています。
ですから、そういう意味で、地方創生二・〇を繰り広げるに当たって、東京に対するそういった施策も是非お願いをしたいと思いますし、東京一極集中の是正というのは、私は、やはり今、日本全体の国力が、残念ながら、徐々に落ちてきてしまっている。GDPでもドイツに抜かれ、インドに迫られている。こういう状況でありますので、日本のいわばパイの奪い合いを東京とその他地方でやるのではなくて、パイ全体を日本の国力として大きくしていくこと、これがより重要だというふうに思います。
東京というのは、そういう意味では、やはり日本の首都でもありますから、当然のことながら、ニューヨークやロンドンやパリや北京、こういったところと争って、世界の中で日本をしっかりよりよくしていくということが大切だと思いますし、東京がよくなれば、地方と東京の連携を密にすることによって、むしろ全体として日本の力を押し上げることができるというふうに思っております。
ですから、地方創生をやるに当たって、それぞれの地方地方がしっかり頑張って、そして地域をよくしていくということが基本であって、何も東京に物や金、人が集まっていく、このことを地方に移していくんだ、そういった発想ではなくて、地域、地方創生を是非進めていただきたい、そんな思いであります。
改めて、最後に、そういったことについて、もう一度総理からお返事をお願いします。
○石破内閣総理大臣 委員御指摘のような、東京の富を地方に移すということを考えているわけではございません。中央省庁の地方移転だって、何も富を地方に移そうと思って文化庁を京都に移転したわけではございません。文化行政ならば京都がふさわしかろうということでやったのでございます。
農業であれ、漁業であれ、林業であれ、観光業であれ、ポテンシャルを持っているのにそれを伸ばせなかった、その部分を最大限に伸ばすことによって日本を新しい形に変えていきたいというふうに思っておるところでございまして、東京対地方の二極対立のような構造は今度の地方創生二・〇で必ず変えていかねばならないと思っておりますので、今後ともどうぞ御指摘賜りますようお願い申し上げます。
○井上(信)委員 ありがとうございました。
時間ですので、これで終わりとしたいと思います。ありがとうございました。
○安住委員長 この際、新藤義孝君から関連質疑の申出があります。井上君の持ち時間の範囲内でこれを許します。新藤義孝君。
○新藤委員 おはようございます。新藤義孝でございます。
今日は、質問の機会をいただけて、大変うれしく思います。
今、世界は激動している。総理は、就任以来、本当に激動の日々をお過ごしだ、このように思いますけれども、しかし、世界は更に揺れているわけです。中国の経済の不透明感、そして、来年にはまたトランプ政権が誕生する。さらに、直近では、韓国の大統領の弾劾の問題、さらにシリアのアサド政権の突然の崩壊。
こういう世界が激動している中で、私、海外に行っていろいろな人の話を聞くと、どこかしっかりとした安定した国、そして信頼の置ける国が世界を引っ張っていってほしい、経済を押し上げていってほしい、こういう声を聞きます。私は、日本は、自分の国をまずよくすることとともに、今混乱の中であるからこそ、世界の中で信頼できる、そして頼られる日本、これにならなければいけないんじゃないか、このように思うんです。
ですから、その意味において、私どもは責任第一党として、日本の経済を新しいステージに持ち上げていく、それは少子高齢化、人口減少であっても成長していく、そういう経済をつくるとともに、やはりこの国をいかに安心、安全とともに礎をきちんと固めながら次に準備していくか、こういうことが大事だと思っております。
そして、私たちの国は、景気回復の流れは極めて明らかです。三十三年ぶりに賃上げ率が五%を突破しました。そして、株価も三十四年ぶり、さらには、名目GDPは初めて六百兆を超え、企業の設備投資も初めて百兆円を超えた。そういうとてもよい兆しが出てきているわけです。
でも、一方で、中小企業は厳しいです。その動きがまだ波及していません。そして、何よりも、賃金が物価を超える状態になっていない。物価の上昇率を超える賃金上昇率、これを何としても達成しなきゃいけない。
こういう中で、本格的な景気回復のチャンスを生かせるかどうか、これは今とても大事だ。そして、何よりも重要なのは、このよい回復の兆しを本格軌道に乗せるためにはこの春先の経済がとても大事で、今回の春闘が五%を超えました。でも、去年は、その前は三%ちょっとだったんですね。三・六%です。その前は二%台。その前はもっと低かった。ですから、この五%になった大きな流れを確実に今度の春につくらなければいけない。この春の経済を押し上げるための、その支援する予算は、たった一回、この補正予算しかない。新年度の予算で幾ら頑張っても、それが執行できるのは七月、八月ですから。ですから、今、この補正予算がいかに大事であって、日本の構造改革を進めながら賃上げの流れを確実にするか、これが大事だということでございます。
そして、私たちは、そういう意味で、今回の経済対策は極めてシンプルにつくったと思っています。
まず第一に、女性、若者、高齢者を含めて、全ての世代の現在、将来の賃金、所得を増やす、これを、全体の所得を増やそうということを第一の柱。そして、成長型経済への移行に道筋をつけるための、物価高を克服しますよ、これが第二の柱です。そして三つ目に、その成長への移行の礎を築くためには安心、安全の確保が大事だ、こういう三つの要素になりました。
まずは賃上げ、これを徹底して頑張らなきゃいけないわけでありますが、これは何といったって、民間の経済、そして世の中がそういうムードにならなければいけません。私も直前までは経済再生担当大臣をやらせていただきましたけれども、いかに政府が強いメッセージを、民間、そして労働界の皆様方、産業界の皆様方に出し続けるかということなのであります。
まず、この来春に向けてのキックオフは、年明けに、春闘に向けた、経労委報告というんですけれども、経団連の経営労働政策特別委員会報告、こういったものが出されます。ここにいかに強いメッセージを出すかということが重要だと思います。まずは総理から、そうした大きなメッセージ、強いメッセージをいただきたいと思いますが、いかがでございましょう。
○石破内閣総理大臣 やはり賃金が上がっていかないと、そして、それが物価上昇を上回る賃金上昇で、それが安定的に続くという話にならないと個人消費が上がっていかない。日本のGDPの過半を占めますのは個人消費でございますので、個人消費が上がっていかなければならぬのだということで、とにかく賃金を上げろということが一番大事なんだということだと思っています。
私ども、社会主義経済をやっているわけではございませんので、国が賃金を上げろと言ったら上がるというような、そんなものではございません。賃金を上げる原資こそがまさしく生産性の上昇というものなのだろう。生産性の上昇って何ですかそれといえば、このお金を出してもこの商品を買いたい、このお金を出してもこのサービスを受けたい、そういうものに対する投資が行われなければどうにもならないねということで、投資がきちんと行き渡る、そして下請の皆さん方にきちんとお金が支払われる、労働者の方々に賃金が支払われる。
配当が上がるのもいいことです。内部留保を私は決して全否定はしないのだけれども、それが内部留保、配当に回るだけではなくて、設備投資、そしてまた賃上げ、下請に対するきちんとしたお支払い、そういうものをきちんと戻していくことによって本来あるべき経済の姿というものに移行していくということが大事だと考えております。
○新藤委員 経労委報告に向けては、何としても賃上げ、そしてその原動力である価格転嫁、これを全力で働きかけていく、この強いメッセージを出していただきたい。また、それをもう既にお考えだと思いますけれども、是非、ここをしっかりと、まず総理から申し上げるのが一番強いメッセージになりますので、お願いしたいと思います。
そして、実質賃金と家計の負担について。
実質賃金、プラスになるまであと一歩、十月の速報値で〇・〇%まで来ています。しかし、実質賃金がプラスになっていないんですから、物価上昇を上回っていないんですから、消費の力強さ、これは残念ながらまだ出てきていない。
特に、こちら側のグラフを見ていただくと、所得の上がらない世帯ほど、収入のほとんどが消費に使っている。そして、消費として、生活必需の食料品価格が高止まりしている。ですから、名目賃金が増えても国民の生活実感は厳しさが抜けていない、こういう状態になるわけであります。
物価高を克服する対策、私たちは政府として打たなきゃならないわけでありますけれども、そのための生活支援に加えて、地域の実情に応じたきめ細かい物価対策、これが必要だと思います。
それから、今関心が高まっています百三万の壁、積極的に誠意を持って今議論が始まっています。実質賃金がプラスでない状態で手取りを増やすというのは、これは可処分所得を増やすという意味で非常に有効だと思います。そして、それは私たちももとより進めなきゃいけないことでずっとやってきたわけなんです。
でも、可処分所得が増えても賃金水準全体が増えなければ、これは結局、総所得における可処分所得の割合を増やしただけでは、これは、その総所得を官民で、要するに消費と税とでどう分けるかというところで議論が止まってしまうわけであります。
ですから、我々が取り組むべきは、賃金の水準全体を引き上げて、そして物価を超える賃上げを定着させる。それは、先ほど、今総理もおっしゃいました、その賃金を払うためには企業が業績を上げていなければ。業績を上げるためには、生産性向上のための投資をしなければならない。この循環をいかにつくっていくかということになるわけであります。
ですから、設備投資のためのデジタルの投資だとか、新しいことを思い切ってやっていく、それは全て賃上げに結びついていくんだということを、私たちははっきりと皆さんに訴えていかなきゃいけないと思うんです。
総理、そこで、今回の経済対策のメインテーマは、全ての世代の現在、将来の賃金、所得を増やす、これをテーマとしています。これを実現させるために、今回の総合経済対策と補正予算において具体的にどのような施策を展開していくのか、少し御披露いただきたいと思います。
○石破内閣総理大臣 これは今度の補正予算で強調しているキーワードでございますが、全ての世代のというのが一つ。現在だけではなくて将来の賃金、所得も増やしましょう、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済を実現するためにはというので、さっきから委員が言っておられる、成長力を強化し、賃上げの原資となる企業の稼ぐ力を継続的に高めるのだというお話でありまして、今だけ上がればいいんじゃない、次の時代もきちんと安定的に上がっていくよということが見通せないと、怖くて使えないのですよね。
賃金が多少上がったとしても、また物価が上がるんじゃないのとか、あるいは社会保障費が上がっていくんじゃないのということになると、これは怖くて使えない、手元に持っておくしかないということになってしまうわけで、そういうのを払拭するだけの経済の成長する力というものをみんなが実感をしていかねばならないのだと思っております。
ですので、これは本当に同じことを何度も繰り返しますが、今委員のおっしゃった人手不足、仕事はあるんだけれども働いてくれる人がいないので会社を閉めざるを得ないというのは、最近多いですよね。仕事はあるんだけれども働く人がいない、どうしようかと。だから、AIに対する、あるいはロボットに対する支援をちゃんと行いましょうということであって、どういうところに手当てをすればいいのかというのを、かなりきめ細かく見ておるつもりでございます。どこで誰が何に困っているのかということ。
そして、もう一つ私たちが考えていかねばならないのは、労働分配率をどう考えるんだということはきちんと考えねばならぬことだと思います。
景気がよくなるときは一時的に労働分配率は下がるものだという説があって、私はそれで論争したこともあるんですけれども、労働分配率というものが中小企業は意外と高い、大企業はなかなかそうでもない。中小企業はかなりきついような、そういうような賃金というものを一生懸命やっているわけで、そういう中小企業に対してどれだけの支援をするかということも、今回の補正予算でかなり配意した点でございます。
○新藤委員 今、総理はとても重要なことをおっしゃったと思うんです。労働分配率は大企業と中小企業で全く違うわけです。中小企業ですと七割から八割いってしまいます。ですから、とにかく業績が上がらない限りは賃金に回らないわけですね。大企業は五〇%ぐらいです。ですから、大企業の場合は、新しい投資をして、更に業績を増やしながら賃上げをする、こういう流れをつくっていかなきゃいけないと思います。
それから、私たちは今回、賃金と所得を増やすというふうにこだわって言葉をここに書いてあります。所得というのは何だというと、賃金は給料ですね、所得というのは、年金だとかその他の所得、そういったものを私たちはイメージをしているわけです。
ですから、今回のことで給与所得者の賃金を、給与を増やしていくことと併せて、全体の経済が上回っていけば年金も上がるわけですよ。それから、女性や高齢者の皆さんが働きやすい環境をつくることによって、もっとそれぞれの所得を増やしていく、こういう工夫をしなければいけない。そのことが今回の対策の中には織り込まれています。
三号保険の問題も、私は思い切って改革すべきだと思うし、在職老齢も、これから高齢者がますます活躍する、希望する方々はどんな世代であっても、どこにおいても仕事ができる、そういう社会をつくること、これが世の中全体の経済をつくっていくことだと思います。
次に、やはり大事なことは価格転嫁、これをどう実現させるかなんですが、今のところ、現状で賃上げを行った中小企業のうちで六割は防衛的賃上げだ、これは商工会議所の調査で明らかになりました。業績の改善が見られないが、人手の確保のために防衛的に賃上げをしている、これがまだ六割なんです。ですから、業績改善をもっとやらなければいけない。
私は、経済再生、赤澤さんと一緒のやつと併せて新しい資本主義の担当大臣もやらせていただきましたけれども、賃上げと価格転嫁を徹底させる、それには、中小企業の団体の皆さんにお集まりいただいて、下請の実態を、大手からどういう連絡が来ているのか実態を教えてください、そういうヒアリングをやりました。そして、経済財政諮問会議に報告するとともに、これを官邸に、総理と一緒に、大企業の、大手トップの方に集まっていただいて、どうやって本当に裾野まで、全国先端まで価格転嫁を達成させるか、こういうことをやってきたんです。公取と一緒に価格転嫁のためのガイドラインも作りましたし、交渉のためのシートも公取のクレジット入りで作りました。是非これは使ってもらいたいと思いますけれども。
そういう中で、今年の春先では、世の中を挙げて賃上げだ、転嫁と言っているけれども、実際の中小企業には全く下りてきていない、事もあろうに、この期に及んでもまだもっと下げられないのかという声だって出ていたんです。
これは思い切って私たちはやってきました。結果として、夏前ぐらいから随分交渉がやりやすくなってきた、それから、ある業界では、見積りを出すときに価格転嫁も入れてどうぞお出しくださいという通知まで来るようになってきた、そういうことなんです。もう一歩だ、このように思うんです。
そして、価格転嫁は、ですから下請法の運用改善をしたんですけれども、この法律の改正だって必要だと思いますが、具体的に一個ずつ着々とやっていかなきゃいけないと思うんですが、これを担当する武藤経済産業大臣、どういう具体的な取組をしているのか。それから、約束手形のこともあるね。手形経済というのは一体世界でどこでやっているんだ、そういうことなんですけれども、そういったことを含めて、価格転嫁の取組、具体的なことを教えていただきたいと思います。
○武藤国務大臣 新藤委員には、鋳物議連を始めとして、現場の、本当に中小企業の実態等々をいろいろ今までも御指導いただいてきまして、本当にありがとうございます。
今もいろいろお話しいただきましたけれども、価格転嫁につきましては、ちょっと改めてデータを申し上げますと、経済産業省が九月に実施した価格交渉に関する調査によりますと、発注側からの声がけで価格交渉できた割合、これが半年前と比べて二ポイント増加をして二八%ということであります。交渉しやすい雰囲気というものは、先生方の今までの御指導のおかげで醸成されつつあるものだというふうに承知をしております。他方、価格転嫁率は四九・七%、半年前より三ポイントは増加しましたけれども、いまだ半分にすぎません。
また、今先生の御指摘いただいた話でございますけれども、この先でございますけれども、各段階の取引構造では深い取引段階ほど転嫁割合が低くなる傾向がございますので、何とか多段階の取引構造を下請法の見直しで今後調整をしていきたいというふうに思っております。
今回の経済対策につきましては、コスト上昇時の価格交渉、転嫁を後押しすべく、公正取引委員会と連携した下請法の改正の検討、また、全国各地で小規模事業者を含めて取引実態を把握すべく、四十七都道府県の下請かけこみ寺の調査員と下請Gメンが連携することによる情報収集体制の強化などを盛り込んでいます。ただ、まだこれから、本当にそのことについては連携を深めて更に深掘りをさせていかなくてはいけません。
最後に約束手形の件でありますけれども、産業界や金融界と協力をしながら、二〇二六年までに紙の手形の利用を廃止し、現金やでんさいによる支払いへ転換する取組を促進をさせていただきます。
また、本年十一月からは、手形や電子記録債権等について、決済期間が六十日を超えないように行政指導の新たな基準を施行したところであります。
引き続き、価格転嫁を定着させるためにも、取引適正化のための取組を徹底してまいりたいと思いますので、御指導をまたよろしくお願いいたします。
○新藤委員 是非、具体的にきめ細かくお願いをしたい、このように思います。
価格転嫁は、やはり大手と中小と、そして業界がみんなでやらないと、価格転嫁しようといいながら、いや、私は大丈夫です、これが始まっちゃうと駄目なんです。企業は結局、防衛的賃上げから抜け出せない。だから、みんなで価格も上げるし、業績も上がる。でも、人件費が上がって消費が増えればまた発注が増える。この循環をつくるまで、ここが非常に重要なので、是非これは力を入れてお願いしたい、このように思います。
今回、実は、価格転嫁を、思い切って新しい取組をしようと。今回の経済対策、補正予算の中で目玉があります。でも、残念ながら、まだ政府の作った経済対策の文書の中ではなかなか分からないので、この機会に是非、今日はテレビ中継も入っていますから、全国の自治体の皆さんや、そして全国の中小企業の皆さんにもこれは私はお知らせしたい、聞いてもらいたいと思うんですけれども、企業間の取引だけじゃないんです、価格転嫁というのは。地方公共団体の調達、これにもどうやって価格転嫁を充実させるかということが大事です。
自治体は、前年度に予算をつくって、その予算を執行していきますので、その段階で算出した単価が、物件費、労務費が上がっているのに、結局、そのもっと前に、半年以上前につくった単価でこの予算を執行するものだから、場合によっては、建設工事などでは入札不調というのが出てしまうわけであります。ですから、こういうものを思い切って価格転嫁を自治体の公共調達の中にも盛り込もうじゃないかということを今回私たちは提案をしているわけなんです。
この赤いところ、地方公共団体発注の公共調達における労務費を含めた価格転嫁の円滑化にも対応できますよというメッセージをここに入れています。これはどういう意味かといえば、自治体が発注する契約行為の中で、建設、警備、物流、印刷、物品調達、様々なところに価格転嫁分を加味したものを考えていただいて結構です、その転嫁分は国が丸ごと御支援します、そして、それは重点支援地方交付金で賄いますと。もちろん、それは、盛り上げた分は、その分は人件費に、給料に反映させていただくことに、これが前提になりますけれども、こういう、自治体予算に賃上げの原資を盛り込んで、そして地域ごとに、それは過疎地を含めて全国で、中小企業が役所から受ける仕事に転嫁分が乗ってということになるわけです。
今回の重点支援地方交付金は、いわゆる推奨事業メニューという中に含めようとしているんですけれども、前回の五千億に対して今回は一千億積み上げて六千億円の規模になっています。いろいろな、様々な事業推奨メニューや、それから生活者支援のためのものもやって一兆円になっているんです。こういうものを使って、私は、思い切って価格転嫁を全国に波及させて、そして、公共調達が価格転嫁が進めば、当然その町の民民の取引も上がっていくことに私はなると思うんです。
これは、私は、上手に使っていただけば目玉になる、どうやってやるかは予算を成立させていただいた後の、今度はそれをどう使うかの要綱の中で明らかにしていくんですけれども、総理、ここは石破内閣としての目玉になりますから、是非このことを皆様にお知らせいただきたいと思います。
○石破内閣総理大臣 ありがとうございました。
今度の経済対策の中で、これは委員御指摘のようにポイントとなるものでございます。
ですから、地方公共団体が公共調達を行う、このときに、物価が上がりましたね、価格分、じゃ、どうやって上乗せしますかねというときに、労務費をも含めた価格転嫁の円滑化をやっていかなきゃどうにもならぬ。それを国のお金で出しますから、ちゃんと、資材が上がったらこの分払ってあげてね、労務費が上がったら払ってあげてねということで回していきたいということであります。
これはかなり異例の政策だとは思っていますが、これをやらないと、隗より始めよというのかしら、地方公共団体がやっていかないと、賃金も、あるいは資材もきちんと転嫁されていかないということだと思います。
ありがとうございました。これは、ありがたいこういうのをいただきましたが、私、総理大臣をやってみて、本当に徹底的にPRしなきゃいかぬと思っております。どんなにいい商品を出しても、PRがないと売れないので、いかにして売るかということは、お役所の余り得意とするところではございませんので、誇大宣伝をするつもりは全くございませんが、こんな制度もあります、あんな制度もあります、もし分からなかったら、この役所のこの番号のこういう担当者に聞いてちょうだいというところまでやらないと、と言うとまた役所が青い顔をするんですけれども、やはりやっていかねばならぬのだなと。やはり行政というのは最大のサービス産業なので。そういうものだと思っております。
○新藤委員 非常に重要です。これは、やはり内閣全体で連携していかなきゃなりません。総理の下でまずは総括して、経済財政担当大臣がこれを音頭を取る。そして、実際には地方創生担当大臣がおやりになるわけですし、それを後押しするのは総務省です。地方自治体にきちんとその中身を分かっていただいて、そして、どういうやり方をすればこれが使えるようになるのか、これを応援するのは、政府全体の連携、大本には総務大臣がやっていただかなきゃならないわけでありまして、政策通の村上大臣ならば、すばらしいリーダーシップを発揮していただけると思うんですけれども、地方公共団体における最低制限価格制度、それから低入札価格調査制度、こういったものも含めて、具体的なところをやっていかないとこれは進みませんので、ちょっと時間が大分なくなってきましたので、端的で結構なんでございますが、是非、この取組、総務省としてどんなことをできるのか、教えていただきたいと思います。
○村上国務大臣 新藤先生におかれては、新しい資本主義担当大臣のときからこの価格転嫁につきまして御尽力いただき、本当にありがとうございます。
自治体の契約については、契約履行を適切に確保するために、地方自治法上、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度が設けられております。自治体の契約において、適切な価格転嫁を図る観点からも、これらの制度が適切に活用されることが重要であると考えており、現在、その活用について調査を実施、結果を取りまとめ、分析を行っているところであります。
総務省におきましても、これらの最低制限価格制度などの適切な活用を促してきたところであります。この調査結果を踏まえて必要な助言を行ってまいりたいと思います。
先生の言われる重点支援地方交付税、これをうまく使えるように頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
○新藤委員 ちょっと、もう一回元に戻ります。
今、この経済対策の中で、一番最初の賃上げ、これは第一の柱です。それから、価格転嫁、そして物価高の克服、これは第二の柱です。もう一つ大事なことは、成長型経済に移行するための礎をつくるという第三の柱も忘れてはならないわけです。
そこで、一つ、実は国の根幹に関わる問題がありますので、少しこれを私質問したいと思っているんですけれども、それは、一つには、都市部における闇バイト。これは徹底してやりましょう。こういった不安を払拭することは国の責任ですから、これは様々な工夫をしながら徹底的にやっていかなきゃならないと思います。安心、安全が確保できなければ経済活動は膨らみませんよ。ですから、そういう意味で重要なんです。
これとあわせて、今、国の根幹と申しました。それは出入国在留管理。この国に国籍を持って住む人と、それから海外から来て在留をされる人、この制度、ここがきちんと厳格に、かつ円満に動いていること、これが安心、安全の礎になるわけであります。
昨年、これを、関係する入管法改正をしました。そして、今年の六月十日から施行されています。
一番の問題は、送還忌避者という問題です。難民申請をして、今まで、十五年間で九千七百人申請されて一人しか認められていないんです。この難民申請の制度、でも、認められていないけれども、何度も繰り返し申請できる。だから、二回、三回、四回、五回、六回と申請を繰り返しながら、ずっと、法的には不安定なまま、一時的に仮放免という形で在留できる、こういう問題があります。
これは今年の六月十日から施行しましたけれども、私ども、これは深く関わっていろいろな協議をしました。そして、今、三回目以降の申請は、難民と認定すべき相当の理由がない限りは、明確に示されない限りは送還になる、こういうことになったんです。そして、自発的な退去を促すための制度改善もしましたので、難民申請を諦めて出国する人も随分増えたということも聞いております。
しかし、私、川口というのが地元なんですが、私の地元の川口市とその周りの埼玉の県南部で非常に今大きくなっているのは、クルド系とされるトルコ国籍の方々、この人たちが特定の地域に集まって住むようになっているんです。そこで、日常生活のマナーを違反するなんという程度にならないんです、コンビニや公園に集まって集団迷惑行為、それから、無免許暴走運転、人身事故、関連する事件、事故、こういったものが頻発して、その地域ではもう本当に怒りが頂点に達している、こういう状態で、しかも不安なんですね。
ですから、一部のこういった外国人の問題というのは、その地域内の取組では解決できません。警察行政には限界があります。国として、入管の在留制度、きちんとそれを精度を上げていかなければならないということですし、ルールを守れない方々には、これはきちんと日本から退去してもらう、法治国家としてここは大前提のところなんです。ルールを守って国を運営していくということなんです。
そういう意味で、送還忌避者がこの法制度に反する形でいつまでも日本国内にいられるというのは、欧米ではこの問題がとても社会的な問題になって、これは大きなことになっているわけであります。
ですから、今回の補正予算では、実は、礎を築く意味で、ここの問題の予算というのもきちんと入っています。今どんなことをこの補正予算でやろうとしているのか、法務大臣、是非教えてください。
○鈴木国務大臣 新藤先生には、日頃から入管行政へ大変御支援、御指導いただいておりまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。
今先生おっしゃいましたように、やはり、法令に従い手続を進めた結果として強制退去が確定した外国人、これは速やかに国から出ていっていただく、これは原則であります。まさに今、改正入管法も踏まえまして、そうしたことを、しっかり迅速に送還を実施していく、そういったことを政府としても進めているところでございます。
そういった意味で、今回の補正予算におきましては、不法滞在外国人等の送還を促進するために、国費送還の速やかな実施に向けた体制整備、ここに向けた必要な経費を計上しているところでございます。
○新藤委員 外国人の渡航者も、コロナ禍を越えて、今ようやっと戻ってきているわけであります。三千万人を超えている。この外国人の渡航者、観光、ビジネス、留学等々で日本に来てくれています。大多数は善良な方なんです。しかし、一方で、ビザの免除制度だとか難民認定の申請制度、これを悪用する形で、日本に対して不法な状態で出稼ぎをする、そういったことをもくろむ外国人の問題が発生しているわけですよ。
我々は、これを、今の三千万人を六千万人に増やすんだ、観光立国として世界から選ばれる日本をつくろう、こういうことを国是としているわけですけれども、この問題は、入ってきてからどうこれをきちんと対処するかということを今工夫をしてもらいました。でも、あわせて、元々、正当な目的のないまま日本に入ってくる、これはやはり入口でチェックしなきゃいけないというふうに思うんです。既にアメリカやイギリス、カナダ、オーストラリア、いろいろな国々でやっているのは、電子渡航認証制度、ESTAというんですけれども、これによって、目的地、それから滞在場所、何をするのかが分からない方は電子申請をした段階でそこに不備があれば入国できない、こういう状態を今つくれるんですね。このESTAを日本に是非入れようじゃないかと思います。
しかし、これは全世界相手に、しかもシステムの大規模変更がありますから、すぐ、あと一か月でというわけにいかないことなんですけれども、これも補正予算の中で、この日本版のESTA、これは前倒しで進めようということが入っております。
是非、ここをどういうふうに今後やっていくのか、法務大臣、説明してください。
○鈴木国務大臣 今委員おっしゃいましたのは日本版のESTAでありますけれども、まさにこれは、今後増加が見込まれる訪日外国人、この審査の円滑化という目的のほかに、不法滞在を企図する外国人等の入国を未然に防ぐ効果があるということであります。
今回、補正予算におきましても、この電子渡航認証制度の導入に向けた調査費、これを計上しておりまして、できる限り早い、できるだけ早い運用開始に向けて今検討を進めているところでございます。
○新藤委員 今、私は、目の前で起きていますから、川口やその周辺地域のことと言いましたが、これは全国で起こり得ることです。ですから、この不法在留の外国人をめぐって起きていること、これをきちんと対処して、これ以上広がらないように、しかも本来の正常な形に速やかに戻すということをしなければ日本全体に広がっていく問題だということで、これは指摘をします。
その上で、絶対にやらなければならないのは、難民認定の申請制度の改善は行ったんですが、もう一つ、仮放免の制度の運用改善をしなければならないんです。
今回、仮放免の制度も法改正によって変えたんですけれども、例えばこういうことが起きているんです。先週末の報道です。川口市内で女子中学生への性的暴行により有罪判決を受け執行猶予中のトルコ国籍の無職男が、執行猶予中にまた十二歳の少女に再び性的暴行をしたとして再逮捕、起訴される、こういう事件が起きています。この方は、トルコ生まれ、日本育ちの在留クルド人で、難民認定中で仮放免中、こういう状態なんです。
犯罪を犯して執行猶予がつく、有罪を受けても、でも、また出てきて、そしてまた犯罪を起こしている、しかし、その人は法的には不法状態で、仮放免で在留している、こういう状態なんです。これでは警察はどうにもならないんです。ですから、警察と自治体に加えて入管庁がしっかりこの問題を対処しなければならないと思います。この問題は、是非、これから更に法務省、入管庁とは連携させてもらいたいと思います。
私、たまたまですけれども、もう七、八年前からこの問題をやって、入管法の改正、二回やってきました。でも、まだまだ改善しなきゃいけない。これは、国家の礎として、選ばれる日本になるためには、ルールを守って、そしてその上で文化や習慣の違いを超えた共生の社会をつくる、この日本をつくっていきたいと思いますので、是非、そこは法務省、しっかりまた連携させてもらいたい、このように思います。
では、もう一回、第一の柱に戻ります。
景気回復の一丁目一番地は賃上げと価格転嫁です。なんですが、これに加えて、成長型経済に移行するためには、新しい需要をつくり出す、生産性の向上を図らなければならない。
ここにありますように、潜在成長力を上げる、これは三つの要素です。労働と資本、労働投入、資本投入と、全要素生産性、TFPというんですけれども、新しいデジタルだとかそれからドローン、これをやっていく。スタートアップも。そういった意味で、日本の根幹である潜在成長率を高めるための政策、これをちりばめて、私たちは体系的に国として戦略を作っていただいているわけなんですけれども、その中で、このフロンティア、宇宙や海、今の、目の前の経済を大きくするとともに、将来の日本の経済を大きくするという意味において、宇宙と海というのは大きな可能性がある。
私は、自民党の宇宙・海洋開発に関する特別委員会の委員長を務めておりました、長い間やってきました。その中で、宇宙戦略基金、横串を刺した上で、一兆円のお金を使って、そしてそれを世界に負けないスピードで宇宙開発しよう、商業化しよう、こういうことを進めてきました。
今日はちょっと時間がないので、もう一つ大事なことで、海洋資源について。
これももうこの十五、六年、二十年近くやっているんでしょうか、南鳥島のレアアース泥です。海底の六千メートル下にある泥を吸い上げて、そして、そこからLEDだとかそれからハイブリッドカーの磁石を作るレアアースを取り込もうと、世界初の海洋産レアアースプロジェクト。今、パイプが三千メートルまでできていて、これまで取った予算でいよいよ残りの三千メートルのパイプが完成して、六千メートル下から泥を吸い上げて、レアアースを世界で初めて商業化するための大きなステップを踏もうと思っているんですけれども、今回、レアアース泥に関しては、補正予算で、やはり、経済成長を進めるためにこういうことをどんどんと進めていって商業化しないことには、いつまでたっても経済が上がらない。
これは、緊急性といったって、目の前の一か月じゃないんです。そういう国としての大きな緊急性の中で今回予算を取っていただきました。この南鳥島の資源開発、大事なことは、泥を揚げるところまで来たら、この泥をどこで製錬するのかということ。私は南鳥島を使うのが一番いいと思うんですけれども、そういったことも含めて、どんな予算になっているか、これはちょっと本当に短くていいので、じゃ、城内大臣、お願いします。
○城内国務大臣 新藤委員におかれましては、自民党の宇宙・海洋開発特別委員長として長年この分野の議論に取り組んでおられましたことに敬意と感謝を申し上げたいと思います。
南鳥島沖の水深六千メートル海域の海底にはレアアースがたくさん含まれており、まさに宝の山のように泥が、いわゆるレアアース泥がたくさん眠っておりまして、これを海底から掘って引き揚げて取り出すことを揚泥といいますが、これはまさに人類未踏の挑戦であります。確かに様々な技術的課題がありますが、現在、戦略的イノベーション創造プログラム、通称SIPにおきまして、これを克服するための研究開発、技術実証を精力的に進めているところであります。
今般の令和六年度補正予算案では、南鳥島周辺海域での実証実験に向けまして、無人潜水機関連設備やレアアース泥製錬に必要な機器の整備などに約二十七億円を計上しているところであります。
この南鳥島沖レアアース開発は、様々な行政分野を横断する取組となるため、内閣府及び関係府省をまたぐ課題として内閣府がリーダーシップを取って推進しております。そして、鉱物資源のほぼ全量を今海外に依存している状況でありますので、我が国にとって、この産業化、商業化が実現すれば、これは極めて重要な我が国の経済成長に資するものであるというふうに理解しております。
○新藤委員 ありがとうございます。
あと二分なので、質問じゃなくて、これはきちっと言います。
南鳥島の周辺のEEZの中で私たちは今一生懸命やっているわけです。そうしたら、鳥島の外縁部の公海で国際鉱区を設定して、中国、ロシア、韓国、どんどん今、周りでマンガンだとかコバルトの開発をしようとしている。私たちもやっていますけれども、EEZだけじゃなくて、公海上のこうした資源開発。日本は世界第六位のEEZを持っていて、海洋資源大国になれる。これが、私たちの、少子高齢化、人口減少時代にあっても経済を成長させていく原動力になる。その意味で、この問題、こうした国際的な動きにも私たちもしっかりと対応して、日本としても、EEZ内に加えて公海の開発、これもきちんとやっていこう、これを訴えたいと思います。
そして最後に、今日本は伸びている、チャンスがあると言いましたけれども、三十年間の倍率、賃金もGDPも株価も、ほぼ一倍ですよ。三十年間で、アメリカは株価十三倍ですよ。ドイツも韓国も。私たちは、三十年ぶりによくなったで止まっちゃいけないんです。もっと大きな私たちは成長ができる。そのための構造改革、これは、今、石破内閣、徹底的にここでやるしかないということを、是非しっかり連携してやっていきましょう。お願い申し上げまして、私の質問にします。
ありがとうございました。
○安住委員長 この際、中谷真一君から関連質疑の申出があります。井上君の持ち時間の範囲内でこれを許します。中谷真一君。
○中谷(真)委員 自民党の中谷真一でございます。
まず冒頭、この度、私どもの事務所において不記載の問題がございました。これは速やかに修正をいたしましてというところであります。これは単純ミスでございまして、国民の皆様に疑念を持たれることがあってはなりませんので、これはしっかりと、今後、再発防止、二度とこのようなことがないように努めてまいりたいということを申し上げたいというふうに思います。本当におわびを申し上げたいと思います。
それでは、この度、質問の機会をいただきましたことに心から感謝申し上げます。委員長始め、また理事の皆様、そして委員の皆様に心から感謝を申し上げるところでございます。
それでは、早速質問に移らせていただきます。
まずは、総理がおっしゃっておられますアジア版NATOについて質問をしたいというふうに思います。
このアジア版NATOでありますが、まず、今、世界中がどのようになっているかという状況認識について確認をしたいというふうに思います。
今、ロシア、ウクライナの戦争は継続中であります。千日を超えてというところであります。さらに、北朝鮮がこれに参加をしてきております。さらには、イスラエル、パレスチナ、これは中東で戦争が起きていますが、これにヒズボラ、これはレバノンですね、さらにイラン、こういったところが参画をしてきているということであります。燃え広がってきているということであります。第三次世界大戦が始まっていると言う有識者もおられるというところであります。
私は、我々の東アジアも例外ではないというふうに考えています。これは皆様とほぼほぼ共通認識だと思いますが、東アジアにおいて、我が国の安全保障において最も脅威になっているのは、やはり中国であります。
中国は急速に軍事力を伸ばしています。さらに、力による現状変更を試みています。東シナ海、さらには南シナ海で行っています。さらに、毎日のように領海侵犯、領空侵犯を繰り返しているわけでありまして、力による現状変更を許してはいけないということで、海上保安庁、そして陸海空自衛隊の皆さんに頑張っていただいているという状況にございます。
ここでまたさらに大きな出来事がございました。それは、まさに日本が同盟を結ぶ米国でありますが、トランプ大統領の再登板であります。
トランプ大統領についてはいろいろな評価がありますけれども、私は、東アジア、日本の安全保障を考えた場合に、歓迎するという立場であります。
これはなぜかと申し上げますと、前回トランプ大統領が就任されたときはオバマ大統領から引き継いだわけでありますが、このときは、ニクソン政権、ニクソン大統領のときからオバマ大統領まで続けていた対中融和政策を変えて、そして中国が行っている力による現状変更を許さないということで、まさにそれに対抗するというふうな政治姿勢に変えた、米国の政策を変えたのはまさにトランプ大統領でありました。それを引き継いだのがバイデン政権であったというところであります。
トランプ大統領が今回の選挙戦を通じておっしゃっているのは、ロシア、ウクライナの戦争を終わらせると言っています。それは、これまでウクライナに対して支援してきた、この支援について制限をしていくということを言っています。さらには、ウクライナのNATO加入については、これを認めないということによってロシアと交渉していくことになろうかというふうに思います。そして、ヨーロッパでの戦争を終わらせて、ヨーロッパに割いていたアメリカの力を東アジアに集中するとも言っているわけであります。
そうしますと何が起きるかというと、米中の摩擦が激化していくことになります。
そこで、地図を持ってまいりました。この下の白い地図を見ていただきたいんですが、アメリカを青に塗っています、中国を赤に塗っています、そして日本を緑、そして台湾を黄色に塗っていますけれども。
この地図を見ますと、米中が摩擦を起こしたときにどこがホットゾーンになっていくかということでありますが、これは、八十年前、日本とアメリカが太平洋戦争を戦ったときと大体同じ地域がホットゾーンになってきます。これは地政学的にそうであります。そう考えますと、やはり、インドからASEAN、そしてオーストラリアを含むオセアニア、そして太平洋、これは大洋州を含みますけれども、ここがホットゾーンになってくるということになります。
中国は太平洋に出なければアメリカとは勝負にならないわけでありまして、そう考えますと、日本列島と台湾がまさに中国が太平洋に出ようとするのを防ぐか、邪魔するかのように存在しているということでありまして、台湾に侵攻するのではないかと言われているのはそういった理由でありまして、これを取ることによって太平洋への道が開けるということであります。このホットゾーンがここの地域だということを申し上げました。
そこで、米ソ冷戦期を振り返ってみたいんです。
米ソ冷戦期はどうであったかということでありますが、この上の地図を見ていただきたいというふうに思います。当時、米ソ冷戦期にNATOが作った地図でありますけれども、これは、青い方は、アメリカを含むまさにNATO諸国を青色で塗っています。赤色の方は、ソ連とそしてワルシャワ条約機構を赤色で塗っています。
これが西と東に分かれて対立構造をつくっていったというところでありますけれども。この評価については様々ございますが、この二つの固まりが対峙することによって最終的には戦争を回避したということでありまして、そういった評価もできるというところであります。
これは、舞台を変えて、今度は東アジア、このアジアでこういった形になっていくのではないかという予測がされているところであります。
そうなっていきますと、まさに総理がおっしゃっているような、NATOのようなものを形成していく。これは軍事同盟というよりは、やはりネットワークを形成していく必要があるというふうに考えているところであります。そう考えますと、それをやろうとすると、アジアはそこまで成熟していないとか、中国を刺激するんじゃないかというようなこともありますが、やはり、やっていかなければいけないというふうに思っています。
これは、少なくとも中国はもう始めています。この五月から、調べたんですが、今年の五月からだけでも九回、いわゆる軍事共同訓練をASEANの諸国と行っています。特に自分の自国に近いところですね、ラオス、カンボジア、タイ、ベトナム、こういった国々とバイで共同訓練を行っております。
こういったことを考えますと、私たちの日本も、東アジアにおいて価値観の近い国々とはそういったことをしていかなければいけないのではないかというふうに思うわけであります。今、まさにヨーロッパの国々とはACSA等々結んでおりますけれども、そうではなくて、やはりアジアの国々と結ぶ必要があるというふうに思っています。さらには、共同訓練、こういったものもやっていかなければいけないというふうに思っています。
そして、これは軍事だけではなくて、まさに経済的にも結びついていかなきゃいけないというふうに思っておりまして、それは、ODAを使って、そしてAZEC、アジアのゼロエミッションとかですね、こういったものに協力していくとか、宇宙を共同で開発していくとか、こういったことを行っていく必要があるというふうに思っています。
とにかく、ネットワークをつくって、東アジアの安定をつくっていくのはやはり日本だというふうに思っているところでありまして、総理のアジア版NATOに関しての考え方をお聞きしたいと思います。
○石破内閣総理大臣 今の委員の前提のお話を聞かないと答えの意味が分かりませんので、それは本当に説明をしていただいてありがたいことだったと思います。答えだけ聞いても何のことだか分かりませんので、前提をきちんと御説明いただいて、本当に厚く御礼を申し上げます。
要は、私はバランス・オブ・パワーだと思っているのです。力が均衡しているとき、どっちが勝つか負けるか分からないねというときは、人類の経験則上、戦は起こりにくいということで、これはもう多分かなり真理を含んでいるんだろうと思っています。
アメリカとソ連が二超大国として核兵器を持ってにらみ合っていたときは、軍事の力が完全にパリティーでしたから、やっても勝つか負けるか分からぬ、お互いに核ミサイルを撃ち合うとお互いが滅びちゃうのでやめておきましょうね、これが冷戦時代の本質だったということでございますが。
そのソ連がぱったり倒れました、アメリカ一極支配になりました、世界は平和になりましたか、ちっともなりませんでした。二極構造の下で封印されていた領土、宗教、民族、経済間格差、こういう戦のネタがわっと表に出てきたというのが冷戦後の社会で、そこへテロが組み合わさってきて、よく分からない世界になりましたねという時代に我々は生きていたんだけれども。
じゃ、まさか国連常任理事国が隣の国を侵略すると誰が思いましたか。誰も思っていなかったが、それが現実のものとして起こっている、三年間、終わらない。
じゃ、仮にウクライナがNATOに入っていたとしたら、ロシアはウクライナを侵略しただろうか。それはしなかったでしょう。仮に、ブダペスト・メモランダムというのがあって、ウクライナが核をロシアに移譲しなかったら、ロシアはウクライナを攻めただろうか。みんなイフの世界なんだけれども、いろいろな国の首脳と話してみると、それはそうだろうねという話になるわけで。
そうなってくると、今ヨーロッパ、ウクライナで起こっていることは明日のアジアかもしれないと考えたときに、NATOに入っていたらああはならなかったよねと。じゃ、この地域において我々はどうなの、国ではないが、台湾はどうなのという話は、それは考えておかないと無責任なんだろうと私は思っているのです。何かがあったときに、ああしておけばよかった、こうしておけばよかったというのは、それは国をお預かりする者として正しい態度だと私は思っていません。
委員御指摘のように、まだアジアはそんなに成熟していない、その議論は二十五年前に聞きました。成熟していないこのアジアでそんなことができるか。二十五年たちました。今でもそんな議論でいいんでしょうかということ。
そして、アメリカの力は相対的に落ちている。アメリカはあのときからハブ・アンド・スポークからネットワーク型へというふうに言っていたわけで、相対的に落ちていくアメリカの力を、どこがどう補って力の均衡を維持するかということは、これは軍事を考える上において極めて当たり前の話であって、考えない方がよほどおかしいということだと思います。
そのときにおいて、じゃ、日本においてそれが可能なのか、憲法解釈上そんなことができるのか、そういうことを積み上げていかねばならないのであって、最初から駄目とかそういうことに決めつけるのを思考停止というのだと私は思っています。
我が党は、ですから今、政調の下で、どうなんだろうか、そういうことはと。憲法上どうなんだろうか、能力上どうなんだろうか、バランス・オブ・パワーの理論においてどうなんだろう、そういうことを一つ一つ精緻に積み上げて、国会における議論に供するということで、その中心に議員がおられると私は認識をしておるところでございます。
○中谷(真)委員 ありがとうございます。
これは、私も時間がないというふうに思っておりまして、速やかに議論をして、そして具体的な行動に移していく必要があるというふうに思っております。総理始め皆様、是非よろしくお願いを申し上げたいというところであります。
次の質問に移ります。
防衛産業の再編について質問したいというふうに思います。
技術力をしっかり保持していることは、まさに抑止力であるというふうに思っております。それが怖さでありまして、抑止力が働いていくということになります。その技術力を支える防衛産業において、私は少々問題があるというふうに思っています。
防衛力整備を更に強化するということで、防衛費を一・六倍に引き上げました。このことによって防衛産業は受注額が非常に伸びています。伸びているんですね。それで、三菱重工がトップメーカーでありますが、年間一兆円を超える契約を行っているというところもあります。一兆円を超える公共事業を行っている会社というのはありませんから、これはすごい額だと思っています。にもかかわらず、なかなか力が入らないような構造になっているんじゃないかというふうに思っています。
これは、全体の売上げの中に占める防衛事業における収益を見ますと、大体、三菱重工でさえ一〇%程度なんです。そうしますと、なかなか力が入らない。それが本業ではないですから、残り九割の事業がありますから。そうなりますと、力が入らない、株主を説得するのも難しい、さらには、本業へ影響するようなことをなかなかできないとか、こういった問題が起きているというふうに思っています。
ですから、ここは、防衛産業、今四重工ありますけれども、こういったところを再編を行って、そして一つ若しくは二つにして、そして六割から七割防需で食べているというような企業をつくっていかない限り、これはやる気とかそういったものがやはり引き出すことができないというふうに考えているところであります。
これに対しまして総理の御意見をお伺いしたいと思います。
○石破内閣総理大臣 足らざるところは防衛大臣からお答えを申し上げます。
私は、委員の御指摘のとおりなんだろうと思っています。
だから、三菱にしても、川重にしても、みんなそうなんですけれども、防衛の分野は非常に少ない、そんなにもうかりゃせぬ、だったらば、そんなに力を入れぬでもいいだろうということが問題の第一。
それからもう一つは、我々が、私と防衛大臣はほとんど同世代なんですが、子供の頃聞いていた兵器メーカーというのはもうほとんど名前がなくなっちゃった。ですよね、あのメーカーはどこに行っちゃったのというのがあって。
アメリカにおいてもヨーロッパにおいても、そういうのが統合に統合に統合を重ねているのは、それはなぜなんだろうかということになると、兵器専業メーカーとなっていくことによって、その能力を高めていくということで、飛躍的に軍事技術が高まっている中にあって、各社がばらばらばらばらにやっておったらば、それはこの時代は生きていけないという戦略的な考え方なのだろうと思っております。
我が国においては、お客様が、自衛隊か警察か消防か海上保安庁というふうにお客様は決まっているわけで、そこにおいて幾つかのメーカーが、すみ分けという言い方がいいかどうか分からないけれども、そういう我が国の防衛産業の状況と、本当に統合に統合に統合を繰り返して、本当に世界の中で最先端の技術を磨いていく。それは、いつか彼我の差が出て、だんだんだんだん他国に頼るような装備体系になって、本当に我が国は大丈夫ですかということが問われているんだと思います。
そういうようなメーカーが大きくなっていくことによって、やれ死の商人だの何だのかんだのという話になりますが、他国を見たときに、本当にこのままの状況で我が国の独立と平和、兵器産業は大丈夫なんですかということを考えたときに、私どもはもう一度、党として、あるいは国会として、感情論ももちろん大事ですが、本当にこれで我が国は生き残れますかということを真剣に考えたいと思っておるところでございます。
○中谷国務大臣 現在、我が国の防衛産業の現状は、欧米で見られたような大規模な再編とか統廃合は見られません。現在、プライム企業はおおむね一〇%未満で防衛産業を手がけているのが現状であります。
そこで、国家安全保障戦略などで示されて、防衛産業基盤強化法が成立しました。この中で、防衛産業の強化、技術優位性、また、装備移転などを手がける基本方針を昨年十月に策定をしまして、各種施策に取り組んでおります。
今後とも、サプライチェーンのリスクの対応、それから、先端民生技術の取り込み、そして、今後の防衛産業の在り方について中長期的に方向性を見せるということで防衛産業戦略の策定をしておりまして、今後、御指摘の点も含めまして、経済産業省を含めて、関係省庁と、また、産業界、学術界とも意見交換を進めながら検討を進めてまいりたいと思っております。
○中谷(真)委員 大臣言われたように、法律を改正して、最大一五%まで利益を取れるように改正したんですね。ですから、例えば一兆円事業をやれば一千五百億の利益を得る可能性もあります。
ただ、今の状況だと、その防衛で得たいわゆる利益をグループ会社の別のことの開発に使ってもいいわけであります。それでは困るわけで、やはり防衛産業、防衛技術の発展のためにそれを使っていただくという形も必要だということも指摘をさせていただきたいというふうに思います。
国内で競争するのではなくて、やはり国外と競争しなきゃいけない。これは技術力の競争ですから。そうしますと、やはり、BAE、今将来戦闘機をやっているBAEとか、レオナルド、こういったところに勝たなければいけませんし、技術的に。さらに、ロッキードやレイセオン、こういったところに支配されないというような体制をやはりつくっていかなきゃいけない。これは、防衛省、政府も一体となってやっていくというような体制を是非つくっていただきたいということをお願い申し上げたいというふうに思います。
それでは、次の質問に移ります。自衛隊のパワハラの問題についてであります。
自衛隊で、今、パワハラを撲滅するということで、様々な活動が行われているというのは承知をしているところであります。
ただ、パワハラについてでありますけれども、これはどのような基準でパワハラだと認定しているんですかということを私は防衛省に問うたことがありますけれども、そのときに言ったのは、まさにほかの省庁と同じ基準でやっています、こう言うんですね、自衛隊に対して。
ただ、自衛隊というのは、まさに重火器を持っていて、さらに、戦場を始めとする危険な地域に行くことを想定した実力組織であります。この組織と普通の省庁のパワハラを同じふうに論じていいのかという、この大問題があります。例えば、では、この先行ったら危険があるという場所に対して自分の部下隊員にそこに行くように命令することは、これはパワハラですかとかですね。これは全然やはり違うんですよね。
しっかりとした自衛隊独自のルール、自衛隊独自の基準をしっかり設けて、それによっていわゆる判定をするということをしなければ、これは、みんなパワハラだというふうに言われてしまうので、それは、みんな指導しなくなっちゃう。そうしますと、まさに実力組織の自衛隊に規律がなくなってしまうという大問題に、大問題です。この大問題、これは最も自衛隊が抱えている大きな問題になってくるというふうに思います。規律なきそういった組織というのは極めて危険でありますし、これをしっかりとコントロールしなきゃいけない。
このためにも、私は、海外では軍法とか軍規とかという名前を使います。さらには、裁判所でそれをしっかりと判定するという、そういうシステムがあるんです。日本だけなんです、ないのは。これをやはりしっかりとつくっていかなきゃいけないということを非常に思っているわけであります。
これに対しての総理のお考えをお聞きしたいと思います。
○石破内閣総理大臣 これは、中谷委員も、今答弁いたしました中谷防衛大臣も、幹部自衛官として本当に厳しい訓練の中で職務に精励されて、今、国会議員をお務めであります。
私は、名前は自衛隊でも何でもいいんですが、最高の規律と最高の栄誉というのがこの組織にはなければならない。
なぜならば、自衛隊員になるときに、ほとんどが自衛官ではあるわけですが、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって職務の完遂に務め、もって国民の負託に応える、こういう誓いをしているのが自衛隊であって、自分にも、お父さんも、お母さんも、奥さんも、子供たちも、恋人もいる、だけれども、一旦命令が下ったら危険を顧みないで職務を全うするんだと誓っている集団であります。それは、国の独立であり、国民の生命であり、世界の平和なんですが、それを守るために命を賭す人たちをその社会で最も尊敬しないで、何でその国が成り立つんですかという当たり前のお話だと私は思っています。
最高の栄誉を与えなければいけない。だけれども、そういう組織であるがゆえに、最高の規律がなければ、扱うものは重火器であって、飛行機であって、船であって、最もパワーの強いものを扱う集団に規律がなかったら、その国は一体どうなるんですかということであって、最高の規律と最高の栄誉、両方がそろって初めて成り立つ組織だということです。
これは、その国の独立を守るために、委員御指摘のように、どの国もやっています、そういうような規律がない。もちろん我々にも規律はありますが、おっしゃるように、戦場の論理と市民社会の論理と違いますので、そこにおいて、裁判をする者も、検事も、弁護士も、全く戦場の論理は存じませんということになったときに、そういう裁判が行われたときに、では、自衛官の人権は誰が一体守ってくれるんだということも我々は考えていかねばならないことなのであって、ほかの国で当然のように行われていることが我が国で議論すらされないということで、本当にこの国はどうなりますかと。
賛成の方も反対の方もいらっしゃるでしょう。でも、国を守るってどういうことですかというお話が、この議会において、賛成でも反対でもいいです、私も、三十何年間議論してきて、自分が知らなかったことがたくさんあることに気づかされました。そこにおいてそういう議論が行われて、我が国の独立と平和。
そして、ハラスメントもそうじゃないですか。そういうような、起こり得る組織であるとすれば、どうやって、例えば、一つの部隊も、ずっと何年も同じ上官と同じ構成でいたらそういうことは起こるかもしれない。船なんかは艦長以下を全部一回入れ替えるとかいろいろな工夫をしておるのであって、ハラスメントをいかにして減らしていくかということも併せて考えてまいりたいと思いますので、防衛大臣の下でそういうことを着実に実行してまいりたいと考えております。
○中谷(真)委員 これは本当に重要な問題なので、是非、総理、検討を、検討というか、しっかりと会議体を立てて、今後、どうやってそういったルールを作ったり、どうやってそれをいわゆる審判していくか、こういったところを是非やっていただきたいと思います。これは本当に、自衛隊の規律がなくなっちゃう。できないんですよ、みんな怖くて。できなくなっちゃいますから、それは是非やっていただきたいというふうに思います。
それでは、次の質問に移ります。自衛官の退職後の処遇についてであります。
私も自衛隊を十四年前に退職をいたしました。このとき、私は幹部自衛官で辞めたんですが、自分でリクナビNEXTに登録して、自分で就職活動しました。
辞めた後のしっかりフォローというのは、余り当時はなされていませんでした。今は大分よくなっているというふうには聞いておりますけれども、それでも私はまだまだというふうに思っています。
任期制隊員、大体二年に一遍、私は陸上自衛官でしたので陸上のことを申し上げますけれども、二年に一遍、いわゆる、更新しますか、それともここでお辞めになりますかということを問うていきます。ですから、二年とか四年とかで退職されて、セカンドキャリアを踏むわけでありますが、このセカンドキャリアが本当にその経験を生かせているようなものなのかとかという問題もあります。
さらに、学校に行きたいという方々に対して応えられているかという問題があります、若い人たちには。定年まで働いたとしても五十五歳です、若年退職者制度を持っていますから。セカンドキャリアをしっかりつくっていかなければいけないわけであります。ただ、それも、まさに自衛隊での経験とか知識を生かしたものかと言われると、私はそうではないというふうに申し上げたいというふうに思います。
ですから、そういった再就職先をしっかりと整備する、また、学校に行きたいという方々に学校に行って学んでいただくとか、そういったことをしっかりやっていかなきゃ、募集しても来ません、人が。そこまで見ますから。ですから、そこをしっかり整備することが、まさに募集における困難性を解決することにもつながっていくというふうに思っているところであります。
私、現役時代に、米海兵隊員と訓練する機会がありました。そのときについてくれた隊員さんに私は聞いたんです、非常に危ないですよねと、米軍は。当時、ソマリアに行っていたりとかしていましたから。それでも何でここに来たのと私は聞いたんです。そうしたら、その彼は、自分の家は非常に、裕福ではなくて、そして兄弟も多かった。ですから、私はここに来て、ここで働いて、そのことによって学校に行くに当たっての奨学金が取りやすいという制度があったりとか、また、入りやすいという制度もあるそうであります。そういったことがあるので、ここにチャンスをつかみに来たという言い方をしていました。そういった考えも私は必要だと思っています。
ただ、再就職に関しては、今のところ、日本では、防衛省だけがこれに対応しようとしています。それでは駄目なんです。政府、また日本として、先ほど総理も、尊敬の対象だとおっしゃっていただいたので非常にうれしいんですけれども、そういったものだということで、やはり、日本国としてどうこれに対応していくかということを考えていただく、省庁またがって。このことをする必要があるというふうに考えますが、総理のお考えをお聞きしたいと思います。
○石破内閣総理大臣 そのとおりです。
議員各位も、陸海空どこでもいいのですけれども、自衛隊の基地、駐屯地のお祭りとかあるじゃないですか、そこへ行かれて、格好よく戦車とかいろいろなものが展示してあることもあるんだけれども、募集の隊員がどんなに一生懸命努力をして、自衛隊に入ってくださいとお願いをしているか、私は、そこへ行って、必ず話を聞くようにしているんです。
今、自衛隊の充足率は九〇です。九〇ということは一割いないだけじゃないかと言われますけれども、一割いないと部隊は動きません。船も飛行機も動きません。そういうものです。そして、若い自衛官を募集しますと、五割来ません。半分来ないです。どうやってこの国を守りますかということで、どんなに自動化を進めても、それは限界はあります。これが一番の問題だと思っています。
そして、委員御指摘のように、若年定年制を取っておりますので、精強性の観点から、五十五歳若しくは五十六歳で退官です。自衛官の退官はお誕生日でございますので、一年三百六十五日、お休みの日を除いて、必ず毎日どこかで退官行事をやっているんです。五十五歳、五十六歳といったら、お子さんは中学生だったり高校生だったり。自衛官で長い間ありがとうね、あしたからどこに勤めるの、まだ決まっていないんだと。それはやはり、何だったんだろうということになる。
自衛隊におって、国家のために、人々のために一生懸命やって、退官したら次の仕事をどうするの。それは一生懸命探してきます、援護もします。でも、そこで見つかった仕事というのは、どんな仕事も大事だけれども、自衛隊として積み上げてきたキャリア、船なら船、飛行機なら飛行機、車なら車、レーダーならレーダー、それを最大限に生かせる、そういうような仕事をいかにしてマッチングしていくかということは、防衛省・自衛隊だけではできません。国交省もそう、厚労省もそう、文科省もそう、経産省もそう、農水省もそう、関係する全ての省庁が自衛官の再就職にみんなで一生懸命取り組むよということにならなければおかしくないですか。だって、国が独立して平和であるということは国民全ての幸せですよ。日本国の独立と平和あっての一人一人の国民であって、何もそれはミリタリーチックなことを言っているわけではありません。
本当にこの国は、みんなが人権が守られ、自由に豊かに暮らせる、その基盤が自衛隊でございますので、今回、私ども、そういうような組織をつくって、本当に大丈夫だよね、再就職できるよねという環境をつくりたいと思いますので、是非また委員各位のお知恵を賜りたい。これは本当に大事なことだと私は思います。
○中谷(真)委員 総理、ありがとうございます。
総理、是非この点、多省庁にまたがって様々な就職に対しての支援ができるように、体制を是非整えていただきたいというふうに思います。
それでは、次の質問に移ります。
次は、経済政策についてであります。私は、ここが非常に問題だと思っているところでありまして、コストカット経済からいかに抜け出していくかという部分について質問をしたいと思います。
今までデフレ下では、まさにコストを下げる、このハンカチを三百円で売っていたところを二百五十円にして競争力を持っていくということでありました。これはデフレ下でしたので、そういったことがずっと行われてきたわけであります。
このとき、やはり人件費というのは、どっちかというとコストになっちゃうんですよね。ですから、そのコストをどう切り下げていくかということをずっとこの三十年間続けてきた。このことによって、新しいものが生まれないとか新しいサービスが生まれない、そのものを安くすることに注力してしまいますから。これから抜け出そうということを政府は今言っておられます。
ただ、実際はどうかといいますと、経済産業省を始め政府のいわゆる経済政策に関する文書とかを読んでいますと、省人化とか、あとは効率化、こういったことに対しての設備投資とか、こういったものに対しては支援しますよというふうに書いてあるわけです。何となく、全体を読んでいくと、まだやはり人件費がコストであるかのように読めちゃう。これはまさに、コストカット経済から抜け出そうと言っているにもかかわらず、それを続けているようにも読めます、これまでの政策を。
そうではなくて、もうインフレーションになっていますから、これは価格を下げることは難しいので、ですから、新しいものや新しいサービスを生み出して、そしてそれを付加価値をつけて売っていくというふうにしていかなければいけないわけであります。それをするのは、やはり私はあくまでも人だというふうに思っています。
ですから、人件費、いわゆるお給料をたくさんお支払いすることは、まさに新しい人材を求め、さらに、今いる方々にやる気を出してもらう、その方々が新しいものや新しいサービスを生み出す。こう考えますと、まさに労働分配率を高めている企業は、これは成長企業になるわけであります。
ところが、これはそうなっていない可能性があります。私、地元に帰ったりなんかしますと、みんな経営者は、人件費が高くなっていて、これをどう抑えるかという議論をやっています。また、利益の中の二〇%以下に人件費を抑えなきゃいけないというようなことを、会計士の方、指導している方がそういうことを言っていたりとかというふうになっています。
そうではなくて、しっかりお給料をお支払いすることはまさに成長につながるんだということを、これは私、政府を挙げて言っていっていただかなければ、頭がチェンジしていかないです、私のふるさと山梨とか、そういったところまで。
ですから、ここは、私は、まさに政府として、経済産業省は、賃金を上げることは投資である、これをしっかり言っていっていただかなければいけませんし、まさに補助とか減税とかこういうところで、まさに労働分配率の高い企業に対してこれをやはり支援するべきでありますから、そういったことをしっかり発信していっていただきたいというふうに考えているところであります。
これについて、経済産業大臣にお伺いしたいと思います。
○武藤国務大臣 中谷先生の質問に答えさせていただきます。
問題意識は全く、私自身も共有しております。
今、我々経済産業省でやっているいろいろな施策の中で、省人等々いろいろ、活力を出すということで、人材不足の中で今回の補正にもいろいろ入れさせていただいています。
ただ、本当に、先生がおっしゃられるように、コスト型経済から賃上げと投資が牽引する成長型経済へ、これへの転換を確実なものとしなきゃいけないということだろうと思いますし、物価高に負けない持続的な賃上げと併せて経済全体の生産性を高める、このまさに必要性があるわけで、まさに人への投資というところが鍵となると思っております。
在職者に対して、今までもいろいろと出ていますけれども、キャリア相談からリスキリングですとか転職までを一体的に支援するキャリアアップ支援事業などを実施してきております。また、賃上げや教育訓練費の増加に取り組む企業にインセンティブを与えたり、またさらに、人材を先生おっしゃられるようにコストではなく資本と捉えて、その価値を最大限に引き出すことの重要性を経営者に広く認識してもらうため、人的資本経営とのコンセプトを打ち出し、先進事例の共有を通じながら、企業が実践できるよう後押ししているところであります。
こうした取組を通じて、社会の通念を変えていくということが大事だと思います。企業による人への投資をしっかり進めていきたいと思います。
○中谷(真)委員 是非、これは経産省を挙げてそこを言っていっていただかなければ、賃金は上がっていきませんし、働く側の意欲も湧いてこないということでありますから、是非お願いをしたいというふうに思います。
それでは、次の質問に移ります。リニアの静岡工区についてであります。
知事が鈴木知事に替わられて、鈴木知事はリニアに対しては御理解をいただいているというふうに考えているところでございます。リニアが大きく動き出すということで、すごく期待をしております。私ども山梨も、これは山梨県の夢であります。
ただ、現状、静岡工区の着手がまだ見通せていないというところでありまして、一刻も早く手をつけなきゃいけないと思っています。JR東海によりますと、静岡工区はほぼ全線トンネルということで、どうしても端からしか行けませんから時間がかかってしまう、八年かかるとも言われているんですが。ということは、手をつけてから八年の間は仕上がらないということになってしまいますから、できるだけ早く手をつけていただきたいというふうに思っています。
ただ、行政の継続性か、静岡県庁の手続の速度は余り速まっていないということも聞いているところでありまして、ここはやはり国土交通省が先頭に立って、スケジュールを示して、そしてこれに対してしっかりとサポートしていくということを是非お願いをしたいというふうに思います。
これに対して、国土交通大臣の御見解をいただきたいと思います。
○中野国務大臣 中谷委員からリニア中央新幹線の御質問でございます。しっかり御指導、御指摘を踏まえて取り組んでまいりたいというふうに思います。
御指摘の未着工の静岡工区につきましては、静岡県とJR東海との対話を促し早期着工するということがリニア中央新幹線の早期開業に向けて非常に重要であるというふうに考えております。
国土交通省の有識者会議におきましては、水資源や環境保全に関する報告書を取りまとめました。また、これらの報告書に基づく対策の状況を継続的にモニタリングするための会議、これを今年の二月に新たに立ち上げまして、これまで五回開催をさせていただきました。
この静岡工区のモニタリング会議を通じまして、JR東海の対策状況を継続的に確認をするとともに、やはり静岡県とJR東海の協議に国土交通省も入って一層の対話を促すなど、リニア中央新幹線の早期整備に向けた環境を整えまして、一日も早い開業に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○中谷(真)委員 ここは、国土交通省には本当に前面に立っていただいてというふうに思っているところであります。来年度には手をつけるとか、こういったやはりスケジュール感も必要だと思っていまして、そこを是非早期に立てていただきたいということをお願い申し上げたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。水田活用直接支払いについて質問をしたいというふうに思います。
以前、私の地元にも、当時、鈴木憲和副大臣に御視察をいただきました。私の地元というのは中山間地が多うございまして、そこでお米を作っていたわけでありますが、当時、政府の減反政策によって、ここでは米を作らずソバを作るようにと言われまして、そこでソバを作っているという現場を見てもらったんです。そこに五年に一度水をためるようにと言われても、今まで水を抜くためにいろいろやってきました。しかも、段々ですから、上から水を流したら下にいっぱい水が行っちゃいますので、そんなことはできないというのが現状であります。
これは非常に問題でありまして、この直接支払いをいただいているおかげで、実はそこをしっかり整備できています。秋には非常に美しい風景が見えたりとか、あとは、これは非常に、まさにふるさとの原風景をつくり出しているのは、そこでそういう方々が作物を作っているからでありまして、これは何とか私は農水省に守っていただきたいというふうに考えているところであります。
畑地化促進事業に移ればいいじゃないかと言うんですが、これも五年間しか実は見ていただけないということで、じゃ、六年目以降はどうなるんだというところがあります。そういった問題もありまして、じゃ、あと五年間でどうやってやめるかという話になっちゃいますから、そうしますと、誰もやれる人がいなくなってしまいます。
私どものふるさとの農業を守るという観点で是非農水省には施策をしていただきたいというふうに思いますが、農水大臣の御見解をいただきたいと思います。
○江藤国務大臣 先生のところに負けないぐらい中山間地ばかりの江藤でございます。
六年目以降なくなることについて、不安の声をたくさん私も直接聞いております。
この間の委員会でもお答えいたしましたが、水活については大変難しいかじ取りをいたしました。私、当時はまだ自民党の調査会長でしたけれども。とにかく、本省に会計検査院が入る、そして地方農政局にも入る、そして水田協議会、全国で百九十か所以上に検査が入ってしまう。このまま放置していたら、この水活の事業自体が不適切という判断を下される。そうなると、事業自体が中断してしまう。そして、これまで交付金を受領された方々が過去に遡って返還命令を受ける。そんなことになったら現場は大混乱ですから、何とかこれをしのがなきゃいけないということで、大変苦しい、苦しいところですよ。
ですから、五年間で一回だけ、五年で一回ですよ。私の地元でも、すぐ水張りをしなきゃいけないと勘違いしている人がいます、代かきまでしなければいけないと勘違いしている人がいますが、五年で一回だけやってくださいというところで、難しいですね。なかなか私もじくじたる気持ちはありましたが、そういう見直しをしました。
そして、たまたま今回、私はまた農水大臣になりました。ですから、役所に行って、次の日だったと思いますが、この水活についてはしっかりやろうと。今後、これが継続的に、継続できる政策にならなきゃいけないし、中山間地域を守っていかなきゃいけない。そして、納税者たる国民から見ても、食料安全保障を確立する上でこれだけの予算をかけても仕方がないだろうと御理解いただける、そして、今までこの水活で地域を守ってきた方々が納得のいただけるような制度設計をしたいと思って、今作業中でございます。
まだ、農林水産省の中で今検討を進めておりまして、まだ自民党にも公明党にも野党の方々にもその方向性は示しておりませんが、できる限り早く方向性をお示しをして、熟議の国会でありますから、野党、与党の垣根を越えて先生方の御意見を賜って、いいものに仕上げていきたいと考えております。
○中谷(真)委員 是非御検討をお願いしたいと思います。
最後に、中山間地直接支払いについてお伺いをしたいと思います。
これは私どもの地元でも大変ありがたいという声があります。まさに条件不利地における農業を守っていただいています。私はここに加算していってもいいかなというふうに思いますけれども。
その中で、ただ、非常に過疎化が進んでいまして、人がいなくなってきています。これで集落協定のリーダーの方々とお話ししますと、活動継続が困難になってきているという声も聞いているところであります。また、草刈りが大変だとか、あと、書類が多くて非常に大変という声も聞いているところでありまして、来年度から新しい五年間が始まるということであります。これに対してどう対応するかというところを農水大臣にお聞きしたいと思います。
○江藤国務大臣 中山間地直接支払いについては、これから先どういう形であるべきかは、これから引き続き検討が必要だと思っております。
来年度からは、集落協定から、ネットワーク化、統合を支援していきたいということで、ネットワーク加算、これをつける。それから、草刈りは大変なので、今、自動で草刈り、斜面でもできるのがありますから、リモコンでできるやつ。スマート農業化についても支援したいということにしております。
しかし、現場では、今まで集落機能強化加算、これでずっとやってきた、これから突然ネットワークに移れと言われても困るという意見があることも聞いておりますが。その御意見を聞いて、この制度に残りたい、このままやりたいという方々については、当面の間、これでやっていただいても結構だという判断をいたしました。
しかし、私、内容をよく精査しましたが、ネットワーク加算、それからスマート農業加算をつけると、手厚くなるんですよ、今までよりも。ですから、説明がやはり足りなかったんじゃないかなという気がします。ですから、しっかり説明をして、移っていただけるように努力もしたいと思います。
一つだけ例を御紹介させていただきたいんですが……
○安住委員長 ちょっといいですか。質疑が大幅に過ぎていますけれども。自民党の時間を削りますよ。(中谷(真)委員「もう大丈夫です」と呼ぶ)
○江藤国務大臣 ということで、中山間地域直接支払い制度は、根拠法に基づいて継続してまいります。
○中谷(真)委員 終わります。ありがとうございました。
○安住委員長 この際、国光あやのさんから関連質疑の申出があります。井上君の持ち時間の範囲内でこれを許します。国光あやのさん。
○国光委員 自民党の国光あやのでございます。
本日は、若輩にもかかわらず、質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
私からは、国民の生活に身近な課題、私は、元々医療やそして社会保障の世界でずっと生きてまいりました、そういう中から見える今直面する課題についてお伺いをさせていただきたいと存じます。
まず、本日も朝から出ております賃上げでございます。
賃上げにつきましては、やはり現役世代の手取りの向上という意味でも非常に大きな課題、まさに石破政権の中でも最大の課題であろうかと思います。
ちょうど春闘でも、年々春闘の賃上げ率は上がっており、今年の春は約三十年ぶりに高水準となる五%を超える賃上げが実現いたしました。是非これを持続し、そして、石破政権の下でも、物価高を上回る賃上げを是非実現していただきたいと思っております。
その中で、特に強調したいのは、この賃上げが、より確実に国としてできるところ、そしてより緊急性が高いところを是非是非手当てをいただけるということが非常に重要なのではないかと思っております。
そういう中で、その分野は何なのかということであります。
賃上げは非常に重要です。ただ、我が国は社会主義経済の国ではありませんから、やはり民間にしっかりお願いしていただく必要がある。その中で、保育や医療や介護等の現場、こちらは全雇用者の約一四%、総理の御地元でも、そして、ここ東京でも、私の地元茨城でも、大体一三から一六%ぐらい、かなりのボリュームを占めております。そして、これは国家が公的価格に基づいて賃金水準を決められるものでございます。さらに、非常に大事な分野であるにもかかわらず、賃金は低く、そして人手不足も非常に困窮している、それがまさに保育や医療や介護等の現場の課題でございます。
実際の賃金水準を御覧いただきますと、全産業平均では約三十七万円です。それが、保育士の方では約三十二万円、そして介護職員では三十万円、医療職種では三十四万円ですが、特に看護補助者と言われるような方々は、三十万を切って二十七万円と非常に低い水準でございます。
これに対して、ずっと、例えばこの春の報酬改定などでも、しっかり賃上げに向けての原資として、診療報酬、介護報酬、障害報酬、実は、過去二十年来で最大の改定率のアップは成し遂げることができました。ただ、まだまだ十分に行き渡っていない。私も、実は、月に何回か病院で当直などをしておりますが、やはりまだまだ、国光さん、報酬改定プラスといっても、なかなか私たちの元に行き渡らないよというお声もいただいております。
その中で、今回の補正予算で、この資料のとおり、総理の御英断で、保育は月額約三・八万円のアップ。ありがとうございます。これは大きなニュースになりました。
一方で、そのほかに、介護現場や医療現場も、余り報道には出ておりませんが、補正予算を私はめくって調べたら、しっかりと措置もされております。介護では、常勤介護職員一人当たり約五・四万円に相当する、最大ですね、一時金を支給、そして医療には約数万円程度、これは生産性の向上という事業の中でも措置をされているというものがございます。
今、保育や介護や医療、まず国がやはり率先してできる賃上げは確実にしていく、その姿勢が、更に民間への大きな波及効果も賃上げにおいて示していかれると思います。
是非総理、改めて石破総理のリーダーシップ、意気込みをお聞かせいただければと思います。
○石破内閣総理大臣 御指摘のように、前年比一〇・七%、大幅な処遇改善を保育士の方々に対しましては行いました、月額約三・八万円。でも、全産業平均よりは低いわけですよね、全産業平均は三十七万円で。それでなくても人が足りなくて、さてさて一〇%上げました、すばらしいでしょう、でも、全産業平均より低い。
やはり保育の現場というのは、本当に物すごい労働、ちっちゃい子供たちですから責任は重いし。本当にそれに対してこれでいいのかという問題があるんだが、とにかく上げました。本当にそれが一人一人の保育士さんのところへ行っているんですかということが問題で、私どもといたしまして、確実に事業主から保育士さんに行き渡るように、実績報告、ちゃんと行きましたねという報告はいただきます。そういうふうにやっていかないと、行かなかったら、これは何のために上げたか訳も分かりません。
保育士さんの数が減るということ、多分、私どもの鳥取県民の数よりも潜在保育士さんの数というのは多いんだろうと思う。行かないなら行かない、保育の現場に出ないなら出ないなりの理由があって、私も聞いてみて愕然とする理由もいっぱいあったんだけれども、やはりこの苦労にふさわしい、そういう報酬が払われていること、これをきちんと実行すること、これをまずやってまいりたいと思っておりますので、是非またいろいろ御教示を賜りたいと存じます。
○国光委員 ありがとうございます。是非お願いいたします。
私も様々政策を見てまいりましたが、総理、非常に本当に重要な御指摘でありまして、補正予算でこれほどつけたんだよ、本予算でこれぐらいつけたんだよ、たくさんPRがありますが、やはりおっしゃるとおり、しっかりそこが現場に行き渡っているかという点が非常に重要でもあります。
今回、例えば報酬改定においても、ベースアップ評価料という、今年度は本当はベースアップ二・五%相当、そして来年度は二%相当の賃上げに使える原資を実は報酬にきちんと入れ込んでいるんですが、まだまだこれがしっかり行き渡っていないんじゃないかなという指摘があるんですね。でも、財源は取ってあるんです。だから、そこをしっかり見ていただくというのが、今日は診療所や病院などでも待合室でいらっしゃる方はたくさんいると思いますけれども、現場への大きなエールになると思いますので、是非そこはきめ細やかにフォローアップをいただければと思っております。
そしてもう一つ、現役世代の賃上げや手取りの向上で大事な側面は、賃金を上げることはもちろんです、ただ、今、現役世代が何に困っていらっしゃるでしょうか。私も現役世代、そして担当大臣でもいらっしゃる福岡大臣も現役世代、五十一歳でいらっしゃると思います、まさにど真ん中ですね。我々の世代が最も本当に負担が大きいと思うのは、やはり社会保険料でございます。昨日もおとついも現場の現役世代の皆様とお話をすると、やはり賃上げもありがたいけれども、保険料だよねというお話はたくさんいただきます。そういう中で、是非これは改革をしていく必要がある。
こちら、フリップを御覧ください。実際に社会保険料の上昇はどうなっているかというと、このフリップを御覧いただきますと、二〇〇〇年には社会保険料の負担率は二二%だったのが、今は約三〇%近くなっております。これは、あと十年や二十年で四〇%とか、そういう大きな数字にまたなってしまいます。これは、現役世代の方にとって、手取りが減ってしまうという意味で非常に大きな負担です。
ここについて、やはり我々政治家が何をすべきか。冒頭、石破総理からも御発言の中で、この場は主権者の場であるというお言葉がありました。我々は、地元を代表する、まさに主権者を代表する議員でございます。やはり私がいつも思いますのは、先送りできない課題に対してしっかりと取り組んでいくということだと思います。
この社会保険料の課題も、実は、もっと抑制をしたいという中でどうしても避けては通れないのは、じゃ、どこの給付を効率化するんですかという話があります。
私は、やはり現役世代の保険料の負担、これが本当に最大課題の一つでありますので、しっかり給付の効率化という点も、我が党も総裁選のときに、保険料の負担軽減を掲げられた候補はたくさんいらっしゃいました。そして、先般あった衆院選でも、野党の皆さんもたくさん保険料の負担軽減をおっしゃっていましたよね。おっしゃっていたんです。ここを、私は、ずっと医療や社会保障の世界で生きてきた人間としては、やはり政争の具に過度にしていただきたくない、やるべき改革はしていかねばならないというふうに思っております。
そういう意味で、この保険料の負担の軽減、実は、今、全世代型社会保障の改革工程の中でも、様々保険料の負担軽減の策の中で、この年末までに決着をすることになっているというものが一つございます。それは、保険料の抑制効果には一つ効果がある高額療養費。
これは、医療を受診されると自己負担がかなりかかってしまうときに、上限のピン留め、医療のセーフティーネットとも言われておりますが、自己負担の軽減、例えば医療費が百万円かかったら、自己負担三割で三十万円になります。ここの上限を、三十万円はお支払いするのはなかなか厳しいので、ここをピン留めして、上限はここまでですよという上限をつくっているというものであります。
これを、例えば、負担能力がある方にはもうちょっとお足をいただいて御負担をいただき、もちろん低所得者の方には配慮をし、そして、やはり今一番苦しい課題の一つである現役世代の保険料の負担軽減にしっかり取り組むんだという意思を、私は、この予算委員会を始め政治の場で、主権者の代表たる我々がその背中、姿勢を見せるということは非常に重要なことだと。
私自身は、医療現場の出身ではあります。給付の効率化がつらいこともよく分かります。ただ、現役世代の悲鳴がたくさん聞こえます。是非寄り添っていただきたいと思っておりますが、是非、福岡大臣、現役世代の代表としてもお答えをいただければと思います。
○福岡国務大臣 高額療養費制度は、御指摘いただきましたように、医療のセーフティーネット機能という意味から大変重要な機能であるというふうに考えておりますが、一方で、今、高齢化の進展であったり、また高額薬剤の普及等によりまして、その総額が年々増加しておりまして、結果として現役世代を中心とした保険料を上昇させているというような状況にある、それが、先生が御指摘のように、現役世代の負担感につながっているというような御指摘があるというふうに思います。
物価や賃金の上昇が着実に進むなど、経済環境も大きく変化する中、現役世代を含めた被保険者の保険料負担の軽減を図る観点から、高額療養費制度の見直しの方向性につきましては、セーフティーネットとしての役割を維持しながらも、能力に応じた負担という全世代型社会保障の理念に基づいて、今、審議会において御議論をいただいています。
お尋ねの現役世代の保険料の軽減については、資料でもお示ししていただいていますように、審議会に事務方から提案した機械的な試算の数字をそのまま申し上げれば、年齢や所得によって差はあるものの、現役世代では平均すると年間三千五百円から五千六百円程度の保険料軽減効果が見込まれますが、これは一定の前提条件に基づく試算でございまして、制度をどのように見直すかによって変動し得るものです。その際に、御懸念を示されましたように、所得の低い方の自己負担等については引上げ率に配慮するなど、制度見直しにおいては丁寧に進めてまいりたいと考えております。
○国光委員 ありがとうございます。
まず何よりも、現役世代の保険料の負担軽減を念頭に置きながら、おっしゃっていただいたように、低所得、所得の低い方への配慮も忘れずに、ただ、やはりこの改革自体は私は進めていただきたいと思っております。是非きめ細やかに、年末ですからもう余り日もありません、しっかりとまとめていただいて、大臣のリーダーシップを期待をしておるところでございます。
〔委員長退席、牧島委員長代理着席〕
続きまして、現役世代のまた負担軽減の中で、子供政策についてお尋ねをしたいと思います。
私は、常々、政策は、非常に財源がかかる、非常に調整が困難なことは時間がかかるかもしれませんが、すぐできること、調整を少しすればできることというのは是非是非取り組んでいただきたい、そういう姿勢で常に考えております。
その中で、フリップを御覧いただければと思います、子供政策、特に、石破総理がよくおっしゃる、地方でお母さんが少なくなる少母化というお話があります。私も、高校生の子供がいて、母の一人ですので、よく分かります。私の地元茨城でも非常に出生数が減って、非常に厳しい状況でございます。
そういう中で、では、どうやれば産み育てやすくなるのかということ。こちらはいろいろな論争もありますけれども、やはり国民の方がどう考えているかということは、各種世論調査やアンケートは非常に多くございます、それで明らかにやはり一番大きいのは、子供数を持てない理由は、経済的な理由、もう圧倒的、八〇パーです。その中で、じゃ、どんなことが負担なんですかということに関して言うと、一番は、肌感覚等もおありだと思います、やはり教育費ですね。教育費の負担が非常に大きい、大学等の奨学金、これはこの後にまた御質問いたします。
その次に、妊娠、出産に伴う医療費の補助。妊娠、出産、あっ、そこなのと思われる方は、多く、男性の方もいらっしゃるかと思いますが、これは結構負担なんですね。
実は、今、妊娠、出産をされるときに、平均的に、大体お一人、普通分娩、普通に出産するときに六十万とか、高いところ、東京では百万とか、えっ、そんなにかかるのという感じですけれども、本当にかかるんですね。それはやはり子供さんが少なくなっているから、病院も経営です、私も一応医師なので経営も分かりますが、やはりお客さんが減っているわけですから、ある程度負担を妊婦さんにお願いをしないとなかなか採算が取れないということはあります。ただ、しっかりこれを負担軽減をしていくということは非常に重要な視点であり、それは病院の経営にも配慮しながらですね。
実は、ホップ、ステップ、ジャンプで様々な改革が進んでおります。まず、三原大臣、こども担当大臣でいらっしゃいます。不妊治療の保険適用は、三原大臣が大臣におなりになる前に、大きなリーダーシップの下に成し遂げられたことであります。私もそこに実は非常にインスパイアといいますか刺激を受けまして、不妊治療の次には出産の保険適用をやり遂げたいと思い、出産の保険適用に取り組んで、そして、約二年後に出産は保険適用する方向ということが出ております。自己負担についても配慮をして、なるべく自己負担がかからない形、そして病院の経営にも配慮するということで対応させていただく予定になっております。
ただ、残された課題は、不妊治療、出産、その後、皆さんが通過する妊娠、出産のイベントは何でしょうというと、妊婦健診です。この妊婦健診がなかなかまだ課題でありまして、大体お一人当たり、妊婦健診は一人十二万円ほどいたします。
以前は、こちらは平成二十五年まで国庫補助事業で十二万円分を各自治体に、市区町村に国が国庫補助事業として対応しておりました。それが、平成二十六年度以降は地財措置、一般財源化をされて、三位一体改革の下、地方分権の中でされておりますが、これは地方分権あるあるなんですけれども、一般財源化された途端、地方の裁量ではあるんですけれども、やはり医療や介護やこういう子育ての政策は、あるあるなんですけれども、格差が出てしまいます。
このとおり、妊婦健診は、実際どうなっているかといいますと、元々十二万円出していたんですね。これがそのまま、その財源が地方に移譲されたわけなんですけれども、一番出していただいているのが、能登の被災でも苦しい中ではありますが、石川県、すばらしいです、十四万円。以前の国庫補助の額以上に出してくださっているんですね。
じゃ、逆に一番下はどこでしょうというと、大変恐縮なんですけれども、三原大臣の御地元の神奈川県が一番下で、約七万六千円ですね。これでも、神奈川県の名誉のために申し上げると、私が昔から結構言うものですから、少しずつ上げていただいたりはしているんですけれども、まだ結構大きな格差があるんですね。でも、明らかに都会の方が高いんですね、妊婦健診の費用は。だから、相当神奈川県のお母さん方は持ち出しをしているんです。
かなり私はやはり言われます。妊婦健診も何とかしてよというお声であります。これについて、是非、ずっとこども家庭庁さんは、総務省さんと連携をして、各自治体に一般財源化してもちゃんと出してあげてよという働きかけをしてくださっていると思いますが、まだやはりちょっと牛歩の歩みでございます。是非ここは、元々財源はあったわけですから、やはりこれをきちっと措置していっていただければ、各市町村からですね、それは、理論上は妊婦健診も無償化になる予定でありますので、是非ここはしっかりと三原大臣のリーダーシップを振るっていただきたいということを切にお願いをしたいと思います。
また、どうしても難しい場合、ずっとこの話はあるんですね、ある場合は、私は、やはり国庫補助事業に戻していく、格差が広がってしまうことについては国庫補助に戻していくということも含めて、これは先週の金曜日も予算委員会で、別の事業の話で上月参議院議員からも御質問があったところでありましたけれども、やはり地方分権をしっかり見直していくという視点も、国が最低守るべきナショナルミニマムは何なのかという視点も含めて必要かと思いますが、是非三原大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。
〔牧島委員長代理退席、委員長着席〕
○三原国務大臣 妊婦健診も含め、妊産婦の方々の経済的負担を軽減し、安心して妊娠、出産や子育てができる環境整備を進めていくことは重要であると考えております。
現在、妊婦健診に必要な費用につきましては、今おっしゃられたように、既に地方交付税措置を講じておりますけれども、一方で、各自治体による公費負担の実施状況については、現状、ばらつきが見られると承知しております。
このため、妊婦の方々に自己負担が発生しないように、各都道府県及び市町村に対し、公費負担の一層の充実を依頼する事務連絡を発出しているほか、国光委員から以前御提案いただいた、総務省と連携して、個別の都道府県の妊婦健診担当部局長に対して直接連絡を行い、改善を働きかける等の取組を進めさせていただきました。その結果、都道府県からは、自己負担が生じないよう、管内市町村等と調整を進めるといった前向きな回答もいただいているところであります。
現状、自治体の公費負担の状況は改善している状況でもありますので、まずは公費負担の更なる推進に向けた取組を引き続き進めていくことが重要であると思っております。
総務省とも連携して、改善状況のフォローアップを行い、自治体の公費負担の状況等の見える化などの対応策をしっかり検討してまいりたいと思います。
○国光委員 ありがとうございます。
最後におっしゃった見える化も含めて、こちらは表にさせていただいているんですけれども、余りこれは自治体に対してはそんなにオープンにはお示ししていなかったと思いますし、各市民の方に、えっ、何か隣の県では実はたくさんもらえて、うちはもらえていないのなんという、見える化が余り進んでいなかったところでありますが、是非そこを見える化していただいて、改善を期待はしたいと思います。
ただ、やはり完全には改善をしないときは、この妊婦健診だけじゃない、たくさんほかにもこういう事業はあるんですね。大臣や委員の御地元でも、やはり各自治体間の格差で非常に困っているんだという話はたくさんあろうかと思います。石破総理が掲げる地方創生の中で、是非二階建ての発想で、一階建てのいわゆる国家として保障すべき部分、例えば医療や介護や福祉という最低限のところはきちんと国家として担保していく。そして、二階建ての部分の地方、それぞれ創意工夫がなされるところについてはしっかりと対応していく。それをまるっと地方創生交付金などでも後押しをしていくような、そういう施策を是非推進していけるように、地方分権の検証も含めて、是非改めてお願いを申し上げたいと思っております。
続きまして、子供政策の関係をもう一つ、あべ文科大臣に。
子育て世代のやはりナンバーワンの負担は、大学等の奨学金でございます、子育て世代の方、私も今子供は高校生と申し上げましたけれども、やはり大学のことを考えると気が重いですよね。非常にやはりお金がかかってしまう。
そういう中で、昨年からずっと奨学金の拡充を進めていただき、そして、様々奨学金の拡充を進めていただく中で、もちろん、まだ道半ばであろうかと思います。今回、今年の四月から始まったことでは、例えば、第三子、三人目までのお子さんがいる御家庭では、給付型の奨学金の拡充をされたり、また、貸与型の奨学金、授業料やそして入学金の減免の拡大などをしております。
なかなか財源が厳しい折、できることというのは若干限られてしまった部分はあるかとは思いますが、対応されていることはされているんですけれども、一点、私は、非常に、これは教育政策や社会保障と共通してなんですけれども、結構頑張って政策をつくった割には、みんな知らない、複雑で分かりにくい、そういう課題が多くあろうかと思います。
この奨学金の拡充も、かなりいろいろな給付のメニューを今回つくってはいるんですけれども、私も地元で、筑波大学などがあって、学生さんと話すときに、それほどやはりみんな知らない。実際、これは文科省に調査の結果をもらいましたら、奨学金というのは、対象者の方の約三割が認知していません、使っていません。それはなぜかというと、やはりよく知らないとか、申込みのタイミングを逃したとか、将来返済できるか不安などの意見があります。
こちらにつきまして、やはりせっかくつくった支援でありますので、更に周知をしていただけるということを効果的に進めていただきたい。これは、様々やっているけれども、まだ課題があろうかと思います。是非その点で、あべ大臣の御見解を教えていただければと思います。
○あべ国務大臣 委員にお答えいたします。
二月二十八日の予算委員会でも御質問いただきましたと思いますが、特に、給付型奨学金の対象者が三割知らない、使っていないということに関しては、やはり高等教育の機会均等の観点と、また子供たちが進学に対する中長期の意思決定をしていく点では本当に重要でございまして、積極的な情報発信がまさに重要なところでございますので、特に中学三年生の生徒に対しまして、やはり高校に進学する前に自分の将来を、教育にしっかりアクセスできるかということの機会均等を考えた上で、私どもは、情報量を絞って見やすい形の周知用の資料を、今年度、二十二万部配付をさせていただいて充実をしているほかに、ユーチューブなども使わせていただきまして、積極的に案内をさせていただいているところでございます。
経済的に困難な学生、また生徒、保護者が制度を知らずに進学を諦めるなどということがないように、積極的な情報発信、また関係者の分かりやすい説明にしっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。
○国光委員 ありがとうございます。
奨学金で救われたという方はたくさんいらっしゃって、さらに、それを知ってもらい、使っていただくということは非常にまた重要な視点だと思いますので、是非是非できることから確実にお願いをしたいと思っております。
続きまして、独り暮らしの方への支援、これは加藤金融大臣にお尋ねをさせていただきたいと思います。
独り暮らしの方、独り暮らしの世帯は、二〇四〇年に世帯数の約半分、さらに、その中で、親族がいない、いても頼れないという方が非常に増えています。私の地元でも、たくさんそのような方からの御心配の声、御不安の声をいただきます。
この課題に対して、加藤大臣、そして今日は坂井大臣もいらっしゃいますけれども、共に、党で今まで一緒にプロジェクトチームをつくって、独り暮らしであっても、そして身寄りがいない、親族がいても頼れない、そういう方であっても、どなたでも安心して住み暮らせるような、そんな社会をつくりたいという思いで取り組んでまいりました。
おかげさまで様々な取組が進み、例えば、何かあったときに相談できる自治体の窓口も今年からモデル事業が始まり、約二十の自治体が、今、手を挙げてくださって、事業が進んでいます。さらに、今回の補正予算でも自治体に対して拡大をして、モデル事業を普及し、そして、相談の窓口や支援の連携などのそういう窓口機能を強化するべく取り組んでいただいています。
その中で、一つ課題があるのが、今、身寄りがない方の中で認知機能が低下する方が、加藤大臣の御担当である金融機関に、月に一回二回、国民年金を下ろしたりするときに行かれるときに、明らかに独居の方でちょっと様相がおかしいなという方が金融機関にいらっしゃったりいたします。そういうときに、この方はちょっとおかしいなと思いながらも、窓口の職員の方は、やはりちょっと個人情報の関係が心配になったりということで、なかなか連絡が行政機関や福祉機関にできないという課題があります。私の地元でもその声をいただいたりいたしております。
これについて、厚労省の方で先般取りまとめられた高齢者の大綱の中で、金融機関でもしっかりその辺り、認知機能が低下されたような方、特に身寄りがないお独り暮らしのような方がいらっしゃるときには自治体と連携をして取り組んでいくようということの検討の文章が入ったところであり、金融庁とともに対策、検討が進んでいると伺っております。
是非その辺りの推進を加藤大臣にも、以前からこの身寄りなし問題、独居者の課題に取り組んでいらっしゃるお立場で、リーダーシップを振るっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○安住委員長 加藤金融大臣、申合せの時間がこれで過ぎますので、最後の答弁にしていただきたいと思います。
○加藤国務大臣 議員とともにいろいろ勉強させていただきました。大事なことは、地域社会の中でしっかり支えていくということだと思います。
そういった意味で、金融機関は認知機能が低下した方と接する機会も多く、そうした方も必要な支援を受けられるよう、福祉機関との連携が期待されるところであります。
御指摘のあった、先般閣議決定いたしました高齢社会対策大綱においても、金融機関に対して、必要に応じて、社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業の支援会議などの枠組みへの参加を促すこと、また、認知機能の低下が見られる方の対応に関する金融機関と福祉機関の連携などに当たり、個人情報の取扱いに係る柔軟な対応ができるよう、金融分野ガイドライン等の運用見直しの必要性について検討することが盛り込まれております。
金融庁としても、関係省庁と連携して、金融機関を含めた地域社会で、認知機能が低下した方々を支えていくための取組をしっかりと進めていきたいと考えています。
○国光委員 ありがとうございます。しっかり取り組んでいただければと思います。
ありがとうございました。
○安住委員長 これにて井上君、新藤君、中谷君、国光さんの質疑は終了いたしました。
次に、重徳和彦君。
○重徳委員 立憲民主党の重徳和彦です。党の政調会長を務めさせていただいております。
今、日本は、物価高、特にお米の値段なんかが大変上がりまして、食料品も大変なことになっております。また、人手不足、これも慢性化しております。経済も、そして国民の皆さん方の生活もなかなか先が見えない、こんな状況であります。この国民の皆さん方の暮らしに先をちゃんと見せていく、これが政治の役割だと考えております。
そして、それ以前に、日本には、暮らす家、働く場所もままならない地域があるんです。それが被災地能登であります。
三日前、私は、地元の近藤和也議員に御案内いただく形で、能登の輪島市町野地区、豪雨災害が最もひどかった箇所の一つと聞いております、に現地調査に入ってまいりました。雪もちらつき始めました。大変寒い季節が始まってまいりました。建物の新設はもちろん、解体すらままならない状況を目の当たりにしてまいりました。そういう中で、重機は動いてはいましたし、ボランティアの皆さん方もたくさん活動されておりました。みんな必死であります。
観光地も、白米千枚田というところを見てきましたけれども、なかなか、地震に次いで豪雨災害、土砂が流れ込んで復旧、復活できることができない、こんな状況でありました。のと里山海道という幹線道路がありますが、道路が崖にそのまま落ちたということもありまして、ひっきりなしに迂回路が続くようなくねくねの道路であり、またアップダウンも続く、そんな波打った道路、継ぎはぎの道路という状況がまだ解消されておりません。
課題を挙げれば山ほどまだありますけれども、私は、あそこで、一つ一例を挙げれば、やはり、地震と豪雨、この二重災害に対して、制度が、やたらと線引きがいろいろなところにあって、うまく機能し得ないところがある。これはもう知れば知るほどでありますが、一つだけ私の気がついたことを申し上げさせていただきます。
まず、被災地生活再建支援金という制度がありますね。家屋が全壊した方に対して三百万円支給するというものです。支援金です。そして、我々は、この支援金三百万円、小さな額ではないかもしれませんが、しかし、これでは生活の再建に当たってはとても足りないということを申し上げてまいりました。倍増しなきゃいけないと考えております。
そこで、政府の方でも考えていただいたのが地域福祉推進支援臨時特例給付金。給付金、これを、今の支援金三百万に上乗せをして、いろいろと積み上げますけれども、例えば、家屋の修繕をするなら五十万円とか、車が壊れたら五十万円、いろいろ積み上げるとトータル三百万円の上乗せになる。実質倍増という仕組みに一応なっておりますが、例えば、これは、地震の場合には適用されるけれども、その上乗せの給付金ですね、地震には対応していても豪雨に対応できないとか、いろいろなところが見受けられます。
私が見てきたのは、地震の被災者となって仮設住宅に入られた、そして、ただ、その仮設住宅の立地が、ちょっと低い地域にあったものですから、そこに豪雨で、雨が浸水をいたしまして車が被災してしまった、この車に対して給付金五十万円というのは手当てされないという話を聞いてまいりました。
このように、地震には対応するけれども豪雨に対応しないというんだったら、二重災害に対応できていないじゃないかということであります。
総理に、この点どのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
○石破内閣総理大臣 略して特例給付金と申しましょう。これにつきましては、石川県からの御要望もございました。
地震で被害を受けました、住宅が半壊、すなわち被害が二〇%未満、半壊未満となった世帯が豪雨によって被害が拡大して半壊以上となっちゃいました、こういう場合にも支給対象とするということにいたしております。
ですから、今重徳議員が御指摘なさったようなケースにおきまして、自動車を買いますということにつきましては給付金が支給され得るということで考えておるところでございます。
○重徳委員 いろいろな要件が、いろいろあるんですね。だから、今総理がおっしゃったような条件を満たした場合にはということでしょう、今のでいえば。ですから、みんなが安心できないんです、一言で言えば。この制度があるから、国の制度があるから安心だね、こういうところを見せていかないと、冒頭申し上げました、先が見えない、これが私は本質的な問題だと思っております。
つけ加えますと、この特例給付金、能登の六市町、確かに一番ひどいところから数えての六市町かもしれませんが、に限定されているんですね。六市町以外の地域にも広げていかなければ、これは境界線をまたいだらもらえる、もらえないということが続くわけですから、こんなことは私は非常に余計な線引きだと思います。
受けられるのも六十五歳の高齢者とか、いろいろな条件がついております。現役世代だってみんな困っているんです。そういう方々を助ける制度にしなければなりませんと思うんですが、総理、どうですか。
○石破内閣総理大臣 条件の緩和というのは、私どもも真剣に検討していかなければならない。要は、お困りの方をどうやって助けるのだと。助けるというのはおこがましい言い方かもしれませんが、ただ、こういうような仕組みは過去は設けられていなかったものでございます。
今回は高齢の方々もおられますので、そういう方々に長期の貸付け、それはなじまないですねというようなことにもなりまして、最大限できることは何だろうかと。六市町の非常に厳しい損害を受けられた方、被害を受けられた方、ここは特に顕著でしたので、行って御覧になった方はお分かりですし、委員も何度も行かれて御存じだと思います。それは近藤委員が一番御案内のとおりですが、この六市町が特に被害が甚大だったということがございますので、そこへ限ってやるということでございます。
ですから、過去の災害はどうでしたかと。現在も再建途上のほかの災害もあるわけで、じゃ、それとの公平性をどう確保しますかという、それは何か官僚的な理屈かもしれませんが、それとの公平性というのをどうやって担保するかということも併せて考えていかねばならないことだと思っております。
支給対象外の世帯というのも当然あるわけで、じゃ、そこは何もしませんかといえば、そんなことを私どもは申し上げておるわけではございません。その支給対象外の世帯につきましても、被災者の方々の状況に応じまして、復興基金、基金の評判は余りよくないですけれども、そういう方々に対して復興基金を使って支援をさせていただく。あるいは、生活再建が図られますように、いろいろなやり方がございます。先ほど国光委員との議論でもございましたが、いろいろなメニューはあるんだけれども、こういう場合に何が使えるかよく分からぬねということがあって、対象が限定されておって、そうじゃないところとの差が大き過ぎるという例があることは私どもも承知をしておりますので、ほかにどういうものがあって、援助できるかということ、オール・オア・ナッシングでやろうとは思っておりません。そういうものをきちんと見せてやっていきます。オール・オア・ナッシングなどということを私は言っていません。いろいろな段階をもっていろいろな困窮者の方々に支援をするということをオール・オア・ナッシングとは申しません。(発言する者あり)
○安住委員長 御静粛に。
○重徳委員 総理の、真剣に考えなければなりませんとか、そのお気持ちは分かるんですが、その仕組みがそうなっていないというところを私は問題視しているわけであります。
そこで、我々は、決して政府を批判したり、政府がおかしいと言っているだけではありません。自公少数となったこの衆議院において、我々は責任を持った対応をしてまいります。
幾つかテーマがあります。こんなボードに書き切れないほど我々立憲民主党が議員立法で取り組むテーマはたくさんあるんですが、その一つ目、御覧ください。
被災者生活再建の支援、ここに支援金の倍増とあります。今総理が、何か基金が使えるとか、いろいろなものを駆使すれば、分かりにくいかもしれないけれども何とかなるんだみたいなことをおっしゃっていますが、現場はそうなっていないんですよ。
そこで、やはり立法府としては、我々野党みんな力を合わせれば多数を握る結果となりましたこの衆議院において、私たちは、被災者生活再建支援法の法律を改正して、そして、今、特例給付金なんという中途半端な上乗せの仕方でなくて、そもそも上限三百万を六百万に法律上倍増しようじゃないか、こういうことを申し上げておりますが、防災に何よりも力を入れておられると思われる石破総理に御見解をお願いします。
○石破内閣総理大臣 能登の方々の再建支援といたしましては、御指摘いただきました三百万が受け取れる再建支援金がございます。現地との調整が必要でございますので、先ほど来申し上げておりますように、六市町を対象とした、最大で被災者生活再建支援金と同額が受け取れる、そのようなものを創設をしたということでございます。
これは要件等々も今申し上げたとおりでございまして、要件が複雑過ぎるとか、そういうことの御指摘もいただきますが、そういうものをきちんと精査をしていくということは私は大事なことで、それが分かりにくいとか、交付までに時間がかかるとか、そういうことを極力排除していきたいと思っております。
御質問がありました被災者生活再建支援金の六百万への引上げのお話、これはなかなか難しいと思っておりますが、このほか、特例交付金の支給対象外の世帯につきましても、被災者の状況に応じて、先ほど来申し上げておりますような復興基金を活用する、住宅再建のために融資を受けている方が活用できる住宅再建利子助成事業というものがございます。あるいは、液状化などによりまして被害を受けた宅地の復旧、住宅の耐震化を行う方が活用できる被災宅地等復旧支援事業などなどございます。
ですから、こういうメニューがございますということが周知されていない。まず周知されていなければ使いようもないわけで、それも言わないで、使いにくいとかゼロだとか、そういうことを言われても、行政の側としては困ります。こういうものをきちんとお示しするとともに、早く届くような仕組みには更に工夫が必要だと思っております。
○重徳委員 総理の気持ちは分かります。だけれども、今の御答弁を聞いていても、大体分かりました。私が問うた被災者生活再建支援法を改正しようじゃないかということに対しては、一言、難しいで終わりじゃないですか。あとはそのほかの仕組みをずっと延々と説明されただけで、真っすぐ向き合おうとしていないじゃないですか、総理。私は、これは被災者に対して向き合っていないも同然だと思いますよ。
そして、我々は、この法整備もそうですが、能登の復興に向けた予算も、今回の復興予算、足りないと思います。これはもっと増額を求めたいと思いますし、そのための修正案を今準備をしております。
ところが、総理、この能登が全然足りていない、そして法整備も行き届いていないのに、総理が、今回の補正予算規模、過去の、昨年を上回る規模にする、ここだけは忠実に実現されているんですよ、今回の補正予算。補正予算、ここ数年、十兆円を超えてきております。コロナの前と比べて異常な事態です。コロナが終わっても今の状況。
そして、会計検査院もこの点については大変問題意識を持って、我々も話を聞いてまいりました。令和四年の補正予算に関して言えば、ざっと確認できる十九兆円、補正予算のですよ、補正予算の十九兆円のうちの半分近くはそのまま繰り越されているんですよ。年度内に執行できないほど大きな予算を補正でつくっておいて、そして繰り越されているんです。
補正予算というのは、財政法二十九条というのがありまして、緊要性、どうしても年度内にやらなきゃいけないことがあるから補正を組むわけでしょう。これを大きな問題として指摘をさせていただきます。
また、中身も問題ですね。基金、これが今回の補正でざっと三・五兆円ですよ。大きなものから小ぶりなものまでありますけれども、三十一の基金に三・五兆円が積み増されております。
このような異常事態というのは、政府自身が問題意識を持っているんですよ。去年の終わりに、デジタル行財政改革会議がルールを決めました。それは、基金の、基金というのは、要するに、五年、十年、長い事業だから、その間できるだけ柔軟に弾力的に支出できるような仕組みなんですが、その十年なら十年のうち、新たな予算措置は三年程度とするというルールを決めております。そして、その先、積み増すのであれば、成果目標の達成状況を見て次の措置を検討する、こういうルールに、ルールを守るのが自民党でしょう、ルールがあるんですね。
ところが、今回の予算を見ますと、今言った三十一基金に積み増しておりますが、そのうち十三基金は去年新設されたばかりの基金じゃないですか。三年ルールもへったくれもないですよね。まして、成果の検証なんか何もされていない。この状況で積み増しているわけです。
一例を挙げますと、宇宙戦略基金。物すごく大事な予算ですよ、それは。宇宙戦略、これから非常に熾烈な国際競争の中で日本は戦っていかなきゃいけない。だけれども、そのことと、去年つくられたばかりのこの三千億円の基金に、支出されたかどうかも私たちは聞かされておりませんが、何か年度内には間に合うんですか、それで、出されるか出されないかぐらいの段階でもう三千億積み増すんですよ。こんなむちゃくちゃなルール違反はないんじゃないかと思います。
石破総理は、十月十五日、総選挙の公示の日です、この日に、昨年を上回る規模の補正予算を組むんだと高らかに宣言されましたが、中身がこれでは、そして恐らく、多くの財源は来年度に繰り越されるでしょう。こういったことまでやって、でも、昨年を上回る予算を組みたかったんですか。ここは大きな責任が求められると思いますよ。責任についてどう考えますか。
○石破内閣総理大臣 昨日の本会議でも申し上げたかと思いますが、これは積み上げの結果こうなったものであって、まず規模ありきということで考えたものではございません。ですから、それを審議いただくためにこの予算委員会をやっておるということだと思っております。
先ほどの宇宙についてのお話でございますが、これはもう本当に最近の、軍事に限りません、いろいろな宇宙関連の各国の熾烈な競争というのを見たときに、基金を積み上げていかないととても対応できない。それは、我が国とほかの国と比べて誠に劣後しておるところがございます。そこに緊要性というものを見出しておるところでございまして、これを急いでやっていかねばならぬ。
要は、その緊要性というものをどこに求めるかという見解の相違でございますが、私どもとして、これは緊要な事態であるというふうに判断をしなければ補正にのっけたりはいたしません。財政法の基準はよく承知をしておるつもりでございます。
○重徳委員 じゃ、二つ確認しますよ。
その今の宇宙戦略基金について、新たに今回積み増そうという、その前提として何か成果検証はされたんでしょうか。これが一点。
そして、そこまでおっしゃるのであれば、今年度中にどうしても緊要性があって積み増さなきゃいけない予算なのであれば、今回の十三・九兆円、全部今年度中に使い切る、このように宣言できますか。繰越しが過去の例のように四割も五割もどんと翌年に繰り越されて、最後は不用になっているものだってあるんですよ。こんな税金の使い方がありますか。このことについて、つまり、使い切るんだというふうに宣言してください。責任を持ってください。
○加藤国務大臣 後者の方の使い切るというのは、ある意味で、基金というのは、要するに、当該年度で……(重徳委員「基金に限らず」と呼ぶ)いやいや、まず基金についてお話があったわけですから。
○安住委員長 手短に。
○加藤国務大臣 それは基金で使いこなすということであります。
それから、物によっては、執行といっても、制度をスタートしなきゃいけない、そういったものもあります。そして、実際のお金が出るのは後になってくる、これはこれまでもあったわけでありますから……(重徳委員「いや、これまでがおかしかったんでしょう」と呼ぶ)いやいや、中にはそういったものもあります。先ほどのいろいろな復興に対する支援であってもそういったものがあるんだろうと思いますから、そういったことをしっかり見ながら、精査をした上で今回計上させていただいたということであります。
○重徳委員 総理、今の財務大臣の答弁を聞いても、過去にも使い残して繰り越されたものだってある、しようがないんだと言わんばかりの御答弁でしたけれども、この緊要性について、ちゃんと責任を持てますか。
それから、検証もしたのかどうか。答弁漏れですよ。検証したのか。大きな話として、そんな細かい話はいいですから、検証したのかどうか、イエスかノーかで答えてください。それだけで構いません。
○石破内閣総理大臣 検証は、それはいたしておると承知いたしております。
後段のお話でございますが、今財務大臣がお答えをしたとおりですが、これは重徳委員もよく御存じかと思いますが、宇宙技術の確実なというか着実な進歩で、打ち上げた衛星の数というのは、アメリカ、ロシア、中国、インド、これは本当に物すごい、日進月歩どころの騒ぎではないのであって、これはどうやって国際競争力を強めていくか、それはもう年度内にやっておきたい、そして、こういう形でやっていく、この緊要性は、ほかにこれ以上のものはないと言っても過言ではないと思っております。
○重徳委員 検証をしたということでありますから、それはきちっとその検証結果は我々に示していただきたいと思いますが、この点は委員長にお取り計らい願いたいと思います。
答弁は、時間もありませんので。ちょっとこちらの質問権の問題です。
○安住委員長 ちょっと、重徳さん、担当大臣に手短に答弁をさせますから。ちょっと待ってください。
短くね。だらだらは駄目よ。
○城内国務大臣 はい、済みません。
実は、これは同一事業の後年度分の積み増しではないのでありまして、これは実は基金ルールに反するとの御指摘は当たりませんので、申し上げておきます。(発言する者あり)
○安住委員長 ちょっと静かにして。
○重徳委員 全く違うものであるかのような御答弁ですけれども、そんな説明は我々全く聞いていませんよ、これまで予算の説明の中で。こんないいかげんな話は、我々は受け入れるわけにはいきません。
それで、私たちは、この基金の問題は大変問題意識を強く持っております。それはどう考えても説明し切れない問題だと思いますよ。そこで、先ほど能登の予算の増額修正の案を出すと申し上げましたが、この基金の削減についても修正案を作成し、提出したいと考えております。
さて、配付資料がありますが、ちょっと話が変わります、我々、超高齢化の時代にこれから入ってまいります。高齢化は能登だけの問題ではもちろんありません。
特に、八十五歳以上の人口がこれから物すごく増えてまいります。人口は減るんだけれども八十五歳以上が増える、こういう推計がございます。八十五歳というのは、身体機能、認知機能が低下し、要介護状態になる人が約六割となる年代の方々です。それは何となく理解できると思います。そういう方々が、これから約十年後の二〇三五年から、今は六百万人ぐらいなんですが、一千万人を超える数となってまいります。そして、人口全体が減るんだから八十五歳以上の方も減るんだと思っていましたら、そうではなくて、この状態が二〇七〇年まで続くということでございます。
その間に私自身も八十五歳になります。今、四十歳ぐらいの方々が二〇七〇年までには八十五歳になる計算でありますから、これはみんなの問題です。そして、介護がここには当然必要になってまいります。
そこで、今、介護業界において大変な問題が起こっております。それは、政府が訪問介護の基本報酬を引き下げたという問題であります。その代わりに給与の処遇改善加算を設けたとか言っておられますけれども、これは他職種との給与差は元々大きいわけですし、今の物価高の中で、とてもじゃないけれども、経営に大きな穴が空いてまいります。そのようなことから、今からでも遅くはありません、訪問介護の基本報酬、総理、元に戻してはどうでしょうか。
○福岡国務大臣 御指摘のとおり、介護報酬改定で基本報酬は見直しましたが、処遇改善に充てる加算措置についてはさせていただいています。その取得率が余り上がっていないという声もありますから、そこの取得を上げるための取組を今回の補正予算でもさせていただいています。
加えまして、今回の補正予算において更なる処遇改善のための予算も措置させていただいておりまして、そういったことを組み合わせて人材確保に努めてまいりたいと考えております。
○重徳委員 訪問介護の事業者の倒産件数、過去最多となっておりますよ、今年。そのような状況を直視していただきたいと思います。
そして、我々は法案を提出する準備をしております。介護士、保育士の処遇改善と書いておりますが、訪問介護の基本報酬を元に戻す、このような法案を準備しておりまして、野党まとまって提出することができればということを目指しております。
じゃ、午前中最後の質問になります。
学校給食無償化、これは昨日の本会議場で酒井なつみ議員からも質問がありました。石破総理も総裁選では随分前向きに考えておられたというふうに仄聞いたしておりますが、これは昨日の答弁の中でもいろいろおっしゃっていましたね。実態調査をやって課題が浮かんだ、喫食しない児童との公平性がどうだとか、財源がどう、少子化対策への政策効果がどう、学校給食法の法制的な問題がどうというふうにおっしゃっていましたが、結局どうしたいんですか、石破総理。やるんですか、やらないんですか、どういうつもりなんですか。そこをお答えください。
○石破内閣総理大臣 今、経済的な困窮等の理由によって学校給食が受けられない方、そういう方々に対しては給食はきちんと行わせていただいております。食材費の負担というのも随分と軽減をいたしてまいりました。
だけれども、御存じのとおり、やっていないところというのはあるわけですよね、給食というものをそもそもやっていないという地域はある。財政力がないわけじゃない、やらない。そうするところとの公平性をどのように取っていくのかという課題はございます。学校給食全部やるというのは、それはそれで一つの形だと思いますが、そこにおいて不公平がないようにするためにはどうすればいいかということで、昨日も課題を申し上げたところでございます。
私どもが申し上げた、論点でもいいです、課題でもいいです、それをきちんと解決をしましたときに次の段階に移行するということで、私どもとして、そういう論点をきちんと問題意識として把握した上で、これをどう解決するかということにはきちんと取り組んでまいりたいと思います。
○重徳委員 じゃ、最後、ここはコメントにさせていただきますが、総理、我々は、自治体で取組がいろいろ行われている学校給食の無償化なんですが、自治体によってやったりやらなかったり、こういう差があるんですよ。そして、別に財政力が著しく弱いところだけがやっていないわけではない。比較的、中核市ぐらいの、そういうところは、人も多い、お金もかかる、こういうことでやれない。しかし、生まれた場所によって、教育を受ける環境によってそういった差が出ることが、国として責任を持って埋めていかなきゃいけない課題なのではないか、是非やらなきゃいけないことなんだと我々は明確に意思を表示しております。総理も是非ともそのような意思を持って進めていただきたいと思います。
午前中、終わります。
○安住委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
正午休憩
――――◇―――――
午後一時開議
○安住委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。重徳和彦君。
○重徳委員 本日の日本時間夜九時から、ノーベル平和賞の授賞式が行われます。我が国から、日本被団協が平和賞を受賞しまして、参加をされることとなります。
総理から日本被団協の皆様に対してメッセージをいただくとともに、日本被団協のこれまでの様々な取組がこれまで以上に国際的にプレゼンスを高めて、そして、核兵器禁止条約、ここに署名、批准するというのはなかなかハードルが高いということは重々承知しておりますが、せめてオブザーバー参加を、来年三月にニューヨークで行われます第三回の締約国会議においてしていただけないか、これについて石破総理のお考えをお聞きしたいと思います。
○石破内閣総理大臣 今回のノーベル賞受賞は、本当に、私どもとして、長年の核廃絶に向けた発信というのか、その御努力が報われたものだということで、おめでとうということなのかどうなのか、御苦労さまでしたというのか、言い方は難しいのですが、やはり私どもとして、本当に御苦労さまでしたと。その思いを実現するために、またこれから先も御活動いただきたいし、私どももお教えいただきたいというふうに思います。
では、今重徳委員おっしゃるように、我々として正式に参加をすることは、それは極めて困難だと思っております。実際問題、核の傘というもの、拡大抑止というもので、今、最も厳しい、北朝鮮であり中国でありロシアであり、核を持ったそういう国々が周りを取り囲んでいる状況にあって、拡大抑止を否定するという考え方を私は持っておりません。むしろ、その確実性、実効性をいかに高めるかということに腐心をしておるところであります。
それと、このオブザーバー参加なるものがどのようにして役割を果たせるかということは、検討はいたします。オブザーバーとして参加をすることにどんな意義があるかということですね。
要は、NPT体制でいかに核軍縮をするかということで我が国は最大の努力をいたしてまいりました、非核三原則の下で。そして、それは少なからず実効を上げてきたと思っております。
オブザーバー参加ということでいかなる役割を果たすことができるのかということを考えないで、参加するもしないもございません。まず、その作業をやらせてください。そこはまた、外務大臣の下でいろいろな議論がなされると思っていますし、この国会の場で議論がなされる。
要は、核の悲惨さというものを訴えるということには大変な意味があると思っています。私自身、そこから大きな影響を受けております。それと、核のない世界と拡大抑止の中でいかにして日本の独立と平和を守るか、抑止力の本質とは何なのかということをまた委員との間で議論させていただきたいと思っております。
○重徳委員 この度のノーベル平和賞受賞、そして、来年は原爆被爆から八十年であります。この機を逃して、違うタイミングはないと思っております。どうぞ積極的に御検討いただきたいと思います。
外交問題で、もう一点。国交正常化から来年六十年をちょうど迎えます韓国との関係であります。
尹大統領の非常戒厳の宣布、そして、弾劾訴追案は一旦廃案とはなりましたけれども、まだ韓国の野党の再提出の構えというものも見られます。こういう中で、これまで尹大統領、日韓関係を改善しようと一貫して努めてこられた、この功績は本当に大きいと思っております。そういう中での韓国の政局の混乱でございます。
こういう中で、ロシア、北朝鮮は、こうしたところに乗じて、そして、トランプ次期大統領の動き方に、ともすると何らかの期待をしている感もあると思っております。
そして、我々は、日米韓の三国によります安全保障体制というものをずっと大事にしてきたわけであります。私自身も、超党派の日韓議員連盟の役員でもありますが、立憲民主党の日韓友好議員連盟の幹事長も務めさせていただいております。ちょっと申し上げづらいんですが、日米韓でいいますと、実は、石破少数与党政権も不安定材料の一つだと私は思うんですよ、国際的に見れば。しかし、こういったことは、我々議会の中で、少数自公かもしれないけれども、我々野党が一定の数を持っていますから、こうした安全保障体制、そして日米韓の三国の取組を議員外交としてしっかりサポートしていきたいと思っております。
こうしたことについて、石破総理のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○石破内閣総理大臣 超党派の議員外交というのは、今ほど大事なときはないと思っております。これは、我が党のみならず、御党もそう、公明党さんもそう、維新の会さんもそう、国民さんもそうでしょう。
そういう、政権は移る、特に韓国の場合には政権が移っていくということが顕著な国でありますが、どんな政権であっても、日韓の関係は揺るぎない。まして来年は六十周年を迎えるわけでございます。そうすると、私も随分と、文在寅政権のときも何度か訪韓はいたしました。いわゆる革新の立場の方々とも議論もいたしました。話せば分かる部分はあります。分かり合えない部分ももちろんあります。どんな政権であったとしても、尹政権がこの後どうなるかについて私は予断を持って申し上げることは一切いたしませんが、どんな政権であっても、日韓の揺るぎなさというものを確立する努力は政府もいたします。議員外交もやっていかねばならない。民間もそうです。文化もそうです。それで、私たちは、この隣国というものがいかに重要なものであるかということ、単に口で言うだけではなくて、歴史や文化も含めてよくよく学ぶ必要がある、日頃よりそのように思っております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
○重徳委員 最後に一点だけ。
今、外交面では、与野党協力して、我々もサポートすると申し上げました。一方で、今、いわゆるハングパーラメントの状況です。今までと違って、政府の方針が、今日申し上げました各種議員立法あるいは予算の修正によりまして、野党主導の立法などで変更されることがあり得る、こういう状況です。この状況をどのように御覧になっているか、最後に御答弁ください。
○石破内閣総理大臣 それは、議会ですから、そのようなことは当然あり得ることだと思っております。
一方において、予算の提出権を誰が持っているか。これは、憲法の解釈によりますが、政府ということになります。これはもういろいろな解釈がございますが、予算の提出権というものは政府が持っておるわけでございまして、国会においていろいろな御審議をいただくということは必要なことです。そこにおいてよりよい議論をいただくということでございますが、今の私どもといたしまして提出させていただいております予算、ここで真摯な説明をさせていただき、濃密な議論の下でこの予算を御可決あらんことをお願い申し上げるという立場に変わりはございません。
○重徳委員 私たちは今、衆議院で、野党みんなそろえば多数を握っている側というふうになります。しかし、私たちが決意をしているのは、これは、国民の皆さん方に対して無責任なことをしてはいけないということであります。野党は、私は、野党の仕事は与党になることだと考えております。我々は半分既に与党であると考えております。
そういう中で、今回の予算についても、国民の皆さん、納税者の皆さん方の立場に立ってよりよいものを修正案として出していこう、こういう考えでございます。これは、野党の皆さん方、各党の皆さん方とも大いに協議をしながら進めて取り組んでいかなきゃいけないし、提出者がどの会派かによりますが、提出者以外の会派の皆さん方にも、同じ野党の中で賛同をいただいていく、こういうことも、これまでないことでありますが、取り組んでいきたいと考えているところであります。
そして、何よりも議員立法、これはもう各党、本当に取りそろえておりますので、野党も、まあ与党もあると思いますが、この議員立法というものが結実するような国会に何とかしてみせたいと思っておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
○安住委員長 この際、長妻昭君から関連質疑の申出があります。重徳君の持ち時間の範囲内でこれを許します。長妻昭君。
○長妻委員 長妻昭でございます。
今日は、私は生まれて初めて野党からの委員長の下で質問をさせていただきます。委員長、よろしくお願いいたします。
そして、石破総理、ちょっと国際会議でお疲れではなかったかなというふうに心配をしたんですが、予算委員会に入ってまいりますと俄然お元気になられて、非常に体調もよろしいように感じますけれども、体調は万全でございましょうか。
○石破内閣総理大臣 御心配ありがとうございます。
何があっても国政に支障があってはならないということをよく承知をいたしております。
○長妻委員 本当によどみなく予算委員会で御答弁されて、私も、初めの正論の部分は聞き入ってしまうんですが、ただ、帰って議事録をよく読みますと、質問にほとんどお答えになっておられない、すごくはぐらかされているなというふうに思っています。今、一部マスメディア、ネット上では石破論法というようなことが言われておりまして、今日は石破論法にまやかされない、ごまかされないようにしっかりと質疑をしていきたいと思いますので、是非、初めに結論を言って、そして正論は後からお願いできればというふうに思います。
そして、石破総理、来年、私は、社会保障新改革元年にしないといけないというふうに思っています。二つありまして、来年は昭和に換算すると昭和百年、昭和百年対策をしなきゃいけない、そしてもう一つは、二〇四〇年対策をしなきゃいけないというふうに考えております。
御存じのように、来年は、団塊の世代の方々が全て、全員が七十五歳以上になる、いわゆる後期高齢者になられる。前期高齢者と後期高齢者では、医療費が一・六倍違う、介護費は十倍になる。非常にこの社会保障の綻びが致命傷になるような、社会の分断を生むようなことになりかねないということで、綻びを正すということが来年重要になってまいります。
そして、その団塊の世代の方々のお子さんたち、第二次ベビーブームで生まれた団塊ジュニアの方々が、今ちょうど五十から五十三歳の方々が、いよいよ来年以降、卒業態勢になってまいります。卒業といいますのは会社を卒業するということで、六十五歳で定年を迎える方々がどんどん出てくる、そして二〇四〇年には全ての方が退職される、こういうような状況になってまいりまして、六十五歳といえば年金の受給開始年齢でございます。
そういう意味では、年金も含めて社会保障が本当に大切になってくるということで、今のままでいきますと相当綻びが出てくる可能性がございますので、来年は、与野党力を合わせて、社会保障新改革元年ということで、しっかり各種手当てをしなければいけないというふうに思っております。
その中でも、今申し上げた団塊ジュニアの皆様方への対応として重要なのが年金でございます。これまで私どもは、かつて消えた年金問題というのを私も追及させていただきまして、今、おかげさまで、一千六百万人の方、日本国民の記録が戻りました。一人二記録戻った方も大変多うございます。回復額でいうと二・九兆円という年金をお戻ししました、今。自民党が当時ほっかむりをして逃げ回って、我々が大騒ぎしなければ、これは多くの方が泣き寝入りだったと思います。今も、残念ながら、与党、自民党ですけれども、ほとんど関心がありません、この問題は。まだ難易度の高い方々が残っているんですが、それを我々はこつこつ今も対応しているということでございます。
そして、ねんきんネットという、これは日本年金機構がやっているネットでございますが、その中に、我々が強い要請をして、持ち主不明記録検索というコーナーをつくっていただきました。これは、宣伝をなかなかしていただいていないので、御存じない方もおられるんですが、申し上げますと、名前と生年月日だけを入れれば、その方の消えた年金の可能性のある記録がぱっと出てくるんですね。ある方がそれをやりましたら、亡くなったお母さんの記録を検索しましたらヒットして、年金事務所に持っていったら、七百八十万円、相続できますので、これをもらうことができた。ほとんど知られていませんので、是非このテレビ、ラジオを見ている方は、ねんきんネットの中で名前と生年月日だけ入力すれば、可能性のある記録が出てきますので、こういうことも是非宣伝していただきたいというふうに思います。
私どものかつて民主党政権のときに、年金生活者支援給付金というのを始めました。年金額が低い方に年最大六万円上乗せするというもので、今七百八十万人の方が受けておられます。これもありがたいことに自民党が引き継いでいただいて、今取り組んでいただいていますけれども、これもPRが足りない。
そして、年金は、これまで延べで二十五年掛けていないと一円ももらえない、保険料没収だったものを、かつての民主党政権で、十年保険料を払えば年金がもらえる、こういうような海外先進国諸国並みの対応にいたしました。
そして、いよいよ来年が年金改革の年になるということで、今、政府もねじり鉢巻きで準備をしていただいているというふうに聞いておりますが、団塊ジュニアの方々が大量に退職されるときに、団塊ジュニアの男性は三人に一人が結婚されておられないということで、そして、実は本当に団塊世代の方々は大変な状況で、就職氷河期と重なったんですね。そういう意味では、非正規雇用の方も多いし、賃金もそれほど高くない方がおられるので、老後、多くの方が生活保護に移行せざるを得ない状況、今のままであるとですね、そういう状況でございます。今、生活保護は三・五兆円かかっておりますので、それが更にいろいろな、御本人にとっても不本意だと思いますので、そういう意味では、年金を何とか下支えをしなきゃいけない。
そして、基礎年金が、今後、実質価値で三割目減りするんですよ、三割。これを何とか止めなきゃいけないということで、政府が、マクロ経済スライドの終了期間を、厚生年金と基礎年金を合わせるという案を、対策を打ち出しておられますが、この対策について、狙いは、将来、基礎年金が実質価値で三割下がるところを一割減で抑えよう、一割下げるだけでとどめようという案で、その基礎年金の目減りを減らすという狙いは私は賛同するんですが、ただ、この対策の説明の中で私は本当にあきれたのは、重要なことを隠して、そしてマスコミに報道をさせるというようなことがありました。
これも御存じだと思いますが、基礎年金を下支えして三割増やすという記事を見た国民の皆さんは多いと思うんですが、そこに書いてあるのは、どのマスコミも大体が、九九・九%得をします、厚生年金受給者の方の九九・九%の方の受給額が増えます、こういうような報道になっているんですね、ほとんどのマスコミが。
数字を出してほしいということで、私も再三再四ずっと申し上げましたら、やっと今日この場で出していただけるということになりまして、これは、本来は年金部会で、今日も二時から年金部会があるんですが、本当は年金部会でちゃんとこれを説明するときに出して、マスコミにも出して、誠意のある説明をしていかないとまた、ちょっと言葉は悪いですけれども、悪いことは言わずに突破するみたいな話になると、逆効果になると思うんですね。
一つ一つ、ちょっと数字を明らかにしていただきたい。
大臣にお伺いしますが、結局、この趣旨というのは、ルールを変えるということなんです、これまでの。ルールを変えて、厚生年金の二階部分を削って、そのお金を将来の基礎年金に充当するという案なんですね。
そうすると、二階建て部分を削るということは、この1を削って、つまり、ブルーの線が従来のルールです、ところが、この赤い線にして、厚生年金の二階部分を低くして、そして右側、基礎年金を分厚くするということなんですが、この二階部分を削る1の金額というのは、三十年投影モデルでは幾らぐらいですか。
○福岡国務大臣 まず、モデル年金で見ますと、実質一%成長を仮定いたしました成長型経済移行・継続ケースでは全ての方々で給付水準が上昇する一方で、今御指摘がありました実質ゼロ成長を仮定した過去三十年投影ケースにおきましては、二〇四〇年度までに受給される方は、現行制度と比べて給付水準が低下する……(長妻委員「1は幾らですか」と呼ぶ)そこは、仮定を置いた数字でいうと十五兆円と。様々な経済前提がありますが、今おっしゃられた経済前提を基にいうと十五兆円ということです。
○長妻委員 十五兆円。これは、いろいろな経済前提を、今年の財政検証で四パターン出していただいているんですが、今、非常にいいケースをおっしゃって、いいケースはこれが下がらないということなんですが、政府もおっしゃっている過去三十年投影ケース、これも私はいいケースだと思うんですね、このケースは実質賃金上昇率が〇・五%ずっと今後上がるということなんです。今、実質賃金はマイナスですよね。ですから、過去三十年投影ケースでも私は過大だと思うんですが、そのケースでいうと、1は十五兆円。
ということは、ルールを変更して、二階部分を十五兆円削って、それを将来の基礎年金に充てていくということをちゃんと国民に説明しないと。ですから、1にいる方々は、はっきり言えば年金額は減ります。だから、減るけれども我慢していただいて、ルールを変えて将来世代を豊かにしましょう、お願いしますということをちゃんとおっしゃらないと、誤解を招くというふうに思います。
ということは、この分岐点、ブルーと赤の分岐点は、これもずっと聞いていて、今日初めて明らかにするということで、先ほど聞きましたら、二〇四〇年ということなんですね。つまり、二〇四〇年に六十五歳になる、二〇四〇年に受給される方は、これは全員年金が増えるということで間違いないですか、それ以外の方はなかなか分からないということで。
○福岡国務大臣 様々な前提はありますが、委員が御指摘になられた過去三十年投影ケースということでいうと、そういうことです。
○長妻委員 つまり、二〇四〇年に六十五歳になる人ということは、今五十歳ですね、大体。つまり、五十歳以下の人は、二階建て部分も減らずに、基礎が下げ止まるので得をするんです、ルールを変更すれば。ところが、それ以上の方はそうじゃない可能性があるということで、これは、私は、何らかの手当てをしないと、世代間格差というか世代間論争を生んでしまうんじゃないかということで、こういうこともはっきりと明確に言っていただきたいというふうに思うんですね。
そうすると、もう一つ確定的なことが言えるのではないかと思うのは、じゃ、この交差するブルーと赤のところは二〇四〇年ということですが、この二〇四〇年までにお亡くなりになる人は全員、年金額がルール変更によって減らされる、こういう理解でよろしいですか。
○福岡国務大臣 そこは、二階建ての部分の高さによって、全ての方が減るというわけではないというふうに承知しています。
○長妻委員 そうすると、二階建ての部分が幾らぐらい、ただ、二〇四〇年にお亡くなりになる方は、ルール変更をした場合、ほとんどの方が、基礎年金と合わせて減るんじゃないんですか、年金は。増える方というのはどういう方なんですか。事前の説明では、基本的に全員が減りますということだったんですが。
○福岡国務大臣 今、試算の仮定となっておりますモデル世帯においていうと皆さん減るということでありますが、そこは様々な属性の方がいらっしゃいますから、そういう中で、先ほど申し上げたということです。
○長妻委員 そうしたら、私は、二〇四〇年までにお亡くなりになる方は、じゃ、減らない方の類型を、後刻、委員会に出していただけますか。そういう方はほとんどいないと思うんですけれども。
○安住委員長 答弁しますか。
○長妻委員 じゃ、委員長、それは委員会でお願いします。理事会で御協議いただければと思います。
○安住委員長 理事会で協議した方がいいですか。答弁させますか。
一度答弁して、厚労大臣。
○福岡国務大臣 済みません、先ほど申し上げましたように、二階部分が低い方について増える可能性があるというふうに承知しておりますので、またそこは理事会の方に、精査をさせていただきたいと思います。(長妻委員「増える可能性はあるんですか」と呼ぶ)増える可能性がある方もいらっしゃるというふうに承知していますので、そこは精査をさせていただきます。
○長妻委員 ちょっと事前の説明と違うので、そういう方はほとんどいないと思いますけれども、是非よろしくお願いをいたします。
そして、結局、何人ぐらいの方が基礎年金、二階部分を合わせて減るのか、人数ですね。少なくとも、今受給されておられる方、三千万人は減ると思うんですが、トータルでいうと、年金をこれから受給される方も減る方がおられると思うんですが、大体何千万人ぐらいの方が減って、将来世代にその年金を給付するというか、ルールを変更してつけ替えるというか、何人ぐらいですか。
○福岡国務大臣 まず、経済成長型では全ての受給者の方が水準が上昇するんですが、今おっしゃった過去三十年の投影ケースでいうと、現在、老齢厚生年金の受給者の方が約三千百万人いらっしゃいます。現在もその方々はマクロ経済スライドの調整を受けておられるところでございますから、そこの調整が継続する間は、そこの方々については引き続き影響を受けられるということになります。
そして、今後のことについては、生涯で見たときにマイナスの影響を受ける方の数については、どのような加入履歴をお持ちの方がいつお亡くなりになるかを仮定することは困難でありますため、算出は難しいと考えております。
○長妻委員 そうすると、今おっしゃったのは、今、厚生年金受給者が三千百二十五万人ですから、三千百二十五万人の方は全て基礎部分と二階部分を合わせて減る、ルール変更によって、ということでいいんですね。
○福岡国務大臣 マクロ経済スライドの調整が継続する間は、当然、そのスライドの期間、そのスライドの影響を受けるということでございます。(発言する者あり)
○安住委員長 御静粛に。いいから、座ったままやり取りをしない。
答弁して。
○福岡国務大臣 はい。
過去三十年投影ケースにおいては減るということです。
○長妻委員 三千百二十五万人以上の方も、相当数が、これから入ってくる方も減るわけでございますので、その試算が一定の前提を置けばできると聞いておりますので、これも是非試算をしていただければというふうに思います。今うなずいておりますので、委員長、理事会でお取り計らいいただければと思います。
○安住委員長 本当に短く、赤澤大臣。走って。
○赤澤国務大臣 今の質疑を見られて、国民の皆さんは本当に不安になると思うんですけれども、これは、三十三年ぶりの五%の賃上げというのは実現をし、先ほど三十年トレンドが続くとおっしゃいましたけれども、あれはまさに分岐点で、そこから離れようとしているわけですよ。
この試算の中でも、成長型経済移行・継続ケースに移行した場合には、損をする方は出てこないということがほぼ出ていたと思うので、そういう意味では、やはり前提によるんだということをはっきりさせていただきたく、我が政権においては、今おっしゃったケースに行かないように、まさに分岐点だと言ってやっているということについては御指摘をしておきたいと思います。
○長妻委員 今、実質賃金はマイナスなんですよ。年金の財政検証の鉄則というのは、堅めに取るということなんですよ。過去三十年投影ケースでも堅めじゃないという学者さんがほとんどなんですよ。堅めに取る。楽観的な数字で、全然大丈夫ですと言って、今まで全部失敗したじゃないですか。だから、そういうような試算をするには、年金の財政検証というのはそぐわないということを申し上げます。
延べ人数を理事会で御検討いただければと思います。
○安住委員長 理事会で協議します。
○長妻委員 今見ていただいたように、それぞれ、過去三十年投影ケースでは、事前にいただいているものでいいますと、厚生年金二十年以上加入の平均受給者が平均余命まで生きた場合はトータルで七十六万円減るケースもある、過去三十年投影ケースで。一か月でいいますと、モデル年金で、これは過去三十年投影ケースで二〇三五年に月額七千六十円減る。これは配付資料の四ページにございます。
ですから、私どもも、基礎年金の目減りを減らす、このことについては、これは必要なことだというふうに思っておりますが、今のような数字を言わずに、マスコミに、九九・九%得をします、全員が得をしますというのは、遠い将来はそうですけれども、その前の方々から削って給付するということがあるわけで、それをきちっとやはり言っていただかないと誤解を招くと思います。
この件については最後の質問にいたしますが、是非お答えいただきたいんですが、この対策を実行する場合、私は年金が減る方に対する何らかの対処というのが必要だと思うんですが、それは考えていただけますか。
○福岡国務大臣 まず、今、先ほどから議論していますのは、経済前提について様々な幅を持たせている中の一つについてのお話をさせていただきました。そういう中で、今後、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を目指している中で、この前提の下で、関係審議会での議論も踏まえて、年金制度改革全体の成案が得られるようにしっかりと検討してまいりたいと考えております。
○長妻委員 そうすると、1で年金が減る方々に対する対処は何にもしなくてこの案を強行することもあり得るということですか。
○福岡国務大臣 まず、今、年金部会において御議論をいただいているわけです。そこで御指摘の点も踏まえて制度の見直しについて御議論をいただくところでございまして、そうした議論も踏まえて、成案が得られるようにしていきたいと考えております。
○長妻委員 石破総理、是非、減る方についての何らかの対処、これを指示していただけませんか。
○石破内閣総理大臣 それは、どこからこの手当てをするのが公平かというお話なんだろうと思っております。じゃ、それを公費、税金で補填をするのが公平なのかというと、それは世代論からいってどうなんだろうねというところがございまして、いかにして経済成長を上げていくかということで、そこをなるたけ影響を少なくしていくということを現在考えておるところでございます。
そこに不公平論があるとするならば、委員のお話を聞いていると多分あるんでしょう、では、そこを公費で埋めるということが正しいのかどうなのかということにつきましては、なお議論があるところだと思っております。
○長妻委員 ちょっと残念ながら、評論家的な発言だというふうに思いますし、経済成長が全て解決する、これまでの自民党政権の常套句だと思うんですね。それで社会保障もいろいろな政策も先送りされてきたと思います。
是非堅めに見積もって、決して過去三十年投影ケースというのは、この五ページに配付資料がありますけれども、過去三十年、これは全要素生産性が〇・五%ずっと上がる、実質賃金も〇・五%ずっと上がるという前提で、過去三十年の実質賃金上昇率は事実は零%です、ですからちょっと過大な形だとは思いますが。ですから、これに基づいてやはり議論をしないといけないというふうに思いますので、是非しっかりとした議論をしていただきたいと思います。
そして、次に、これは政治改革について話題を転じますけれども、石破総理が若かりし頃、三十年ほど前に石破首相は、自民党の党議拘束を破って、果敢に法律に賛成をいたしました。すばらしいことだと私は思いました。
その法律に書いてあるのは、企業・団体献金を禁止するという法律なんですね、禁止するといっても、この表にありますように、今は、政党と政治資金団体、政治資金団体というのは、大体、党の本体に献金するところの窓口でございますけれども、それと政党支部、これは除外されているわけでございますが、この案に石破さんは当時賛成をされた。
でも、この国会の議論をるる聞いておりますと、いや、企業・団体献金は悪くないんだ、個人献金と同じだ、企業・団体献金を非難するのはおかしい、ずっとそういう論調でおっしゃられていた。
でも、これは企業・団体献金を制約しているんですよ、石破さんが党議拘束を破って賛成した法案というのは。つまり、普通の政治団体には献金できません、献金できるのは政党と政党支部だけですというふうに絞ったわけですね。これは、絞ったというからには、企業・団体献金は問題だということで絞った案に賛成されたと思うんですが、いかがですか。
○石破内閣総理大臣 その当時のことを御存じの方というのは本当に僅かになりました。恐らく、この議場におる者では、中谷防衛大臣、岩屋外務大臣、あるいは村上総務大臣ぐらいだと思います。当時何があったかということをよく認識しながら議論しないと議論がおかしくなりますよ。だから言っているのであって、昔の話を聞きたくないなんぞと言われては、それは困ります。きちんと過去のことを検証してから議論してください。
御指摘の細川政権において、これがどういう法案であったかということですが、おまえはそれを知った上で賛成したのかというお尋ねですから、申し上げておきます。
平成五年十月十四日、衆議院本会議で、細川総理がこのように答弁をしておられるんですね。
政党に対する寄附の法的根拠はどうかということでございますが、政党、政治資金団体に対するものを存続させることといたしておりますのは、企業・団体献金の廃止に向けての現実的な対応を考えました場合に、このような考え方は、従来の経験からいたしましても腐敗のおそれが少ない上に、政党中心の選挙の実現という今回の政治改革の趣旨からしましても許容されると判断をいたしておる、これも繰り返して申し上げているように、政党、政治資金団体に対する企業などの団体献金につきましても五年後に見直しを行うこととしておりますので、これは既に御説明をしておるとおりでございますというのが十月十四日ですね。当時の政府の立場を申し上げております。
この後、一月たちまして、十一月二十六日の参議院本会議、同じように、細川総理が何と言っておるかというと、企業・団体献金の禁止以外に制度の抜け道や欠陥を封じる手段があるか、こういう趣旨のお尋ねをいただきました、政党支部を利用することによって企業などの団体献金が政治家個人に流れることは抜け道ではないかということですが、この企業・団体献金の受け手を政党に限って、政党が介在することによって企業と政治家個人との結びつきに起因する政治腐敗事件の防止に大きな効果を持つものと考えておりますということを答弁しておるのであって、当時の政府の立場として、企業・団体献金を禁止しますという立場には立っておりませんでした。それは、当時の議員のみんなの共通認識であって、そういうことであれば、もっとかんかんがくがく、ごうごうたる議論が沸き起こったはずでございます。
当時の細川連立政権の意識は、企業・団体献金は廃止ということではなくて、五年後に見直しということでございまして、あのときに、公的助成を入れるから企業・団体献金は廃止だというような、それがコンセンサスだったとは私は全く記憶をいたしておりません。
○長妻委員 石破総理、石破総理がこれまで国会で、いや、企業・団体献金は悪くないんだ、個人献金と同じなんだというふうに繰り返されるから、これは、確かに全面禁止ではないけれども、政治団体は禁止しているんですよ、制約しているわけで、それに賛同されているということは、何らかの弊害があるということがあるからこういうことになっているわけです。
しかも、河野さんの、最終的にこの法律が成就するときに細川・河野会談というのがありまして、河野さんは自民党総裁です。そのときに、オーラルヒストリーでどういうふうにおっしゃっているかというと、今おっしゃっていただいたこの附則のところですね、こういうことをおっしゃっています。自民党は、今は何億と企業献金をもらっていて、来年からいきなり廃止というわけにはいかないので、激変緩和のための時間が欲しいと提案し、五年後に見直しという条件で企業献金を廃止することで合意できたと言っているんですよ、オーラルヒストリーで。だから、五年後見直しというのは、五年後廃止ということなんですよ。こう本人は言っているんですよ。
そういうようなことで、石破首相も、実は大西健介議員への答弁で、先週木曜日でしたか、こういうことをおっしゃっておられるんですね。これは私は真っ当な石破さんの答弁だと思いますが、経団連が去年もおっしゃっているんですね。いつも言っているんです。政党に企業献金をするのは一種の社会貢献だ、こういうふうに経団連は言っているんですが、石破首相はそれを否定された。私もこれは同感なんです。
こういうことをおっしゃっておられます。その言葉、社会貢献にはやや違和感がございます、企業が、営利企業であります以上、利益を見返りと全くせず献金をするということは、それ自体がおかしなことでございます、これは全く私は同意なんですよ。
これは、こういう認識でやはり企業・団体献金は私は禁止すべきと思うんですが、この認識は変わらないわけですね、今も。
○石破内閣総理大臣 それは変わりません。
つまり、この資本主義社会における民主主義を誰が支えるのか、そういうような根本論に立ち返ったときに、企業は確かに投票することはできない、しかし、この社会経済生活において一定の役割というか大きな役割を果たしている。それは、我々は学校で会社法を学びましたね。五百条にも及ぶ条文で相当の規制がなされている、そういう存在が、資本主義における民主主義において、じゃ、どうやって自分たちの意思というものを反映をするのかというときに、投票ができないということになるとするならば、それは企業・団体献金という形を取るということは当然あり得ることだと思っております。
そこにおいて、その会社が社会のために果たしている仕事、そういうものに適合するような政策であり、あるいは法律でありということを望むということは、それは当然あり得ることではないか。
ただ、それによって、本来あるべき国家の姿、本来あるべき社会正義、それがゆがめられるということがあってはならないのであって、私たちが常に申し上げておるのは、禁止よりも公開だということを申し上げている、きちんと分かるようにと。この政治家は、この政党は金によってそういうものを曲げたねということになれば、有権者の判断によって、それは選挙に当選することができない、あるいは政権を失うということは、資本主義の民主主義社会のあるべき姿だと私どもは考えております。
○長妻委員 公開が重要だというのは私も同感ですが、今も一定程度公開しているんですよ。
これは昨年の政治資金収支報告書を調べたものでございますが、自民党に、自民党の本部の国民政治協会へ献金額が多かった企業、団体は、一社で五千万円をぽんと献金しているところもいっぱいあるわけですね。これは公開されているから分かるんだけれども、これはかないませんよ、ほかのところ、要望をしたいところは。これはほとんど経団連じゃないですか。
配付資料の七ページに経団連の通信簿というのを出しているんですよ、二〇二四年、主要政策の政策評価。自民党はすばらしいという評価です。そして、その右側に要望がどっと書いてあるわけですよ。ですから、この要望を実現する、聞く耳を持ってもらうということでこういう献金が行われていると承知を私はしておりますし、私も長年国会議員をさせていただいて、本当に悔しい思いをしてまいりました。
例えば、少子化対策は、大切だ大切だといいながら、ほとんど予算がつかない、これまで。パーティー券は売れませんよ、少子化対策。企業・団体献金も集まらない。非正規雇用、格差対策だって、我々は法案を何度も出していますが、審議拒否。これもパーティー券は売れないし、むしろ、非正規雇用を便利に使う巨大業界からは、パーティー券や、潤沢な企業・団体献金が入ってくるじゃないですか。あるいは、大学の研究費だって、先進国に比べたら本当に微々たるものですよ。これもパーティー券も売れないし、献金も集まらない。
私は、献金が非常に潤沢なところに、税の優遇を含めていろいろな恩恵があるということを肌で感じているからこそ、企業・団体献金は禁止しなきゃいけないというふうに強く思うわけです。
企業、団体、こういうところは、いろいろ発言の機会というのは、それはありますよ。経団連との、皆さんとの交流とか、いろいろな意見表明の機会というのはたくさんあるので、そういうところで意見を表明すればいいし、先進七か国では、アメリカもフランスもカナダも企業・団体献金は禁止となっています。この前、山下さんが出した資料でも、国会図書館で入手していただいた資料でも禁止と書いてございます。
そういうようなこともありますので、是非真摯に企業・団体献金禁止についても議論をしていただきたい。年内に決着をつけていただきたいと思うんですが、いかがですか。
○石破内閣総理大臣 それは各党間で今真摯な話合いがなされておるのであって、政府の立場でいつまでにということを申し上げるのは越権でございます。
申し上げておきますが、私どもも、三年三か月、野党をやりました。今、山井さんが座っておられるところに私は座っておった。三年三か月、野党の時期がありました。それは、与党というのは大変なものだなと思いましたよね。当時、委員も民主党に籍を置かれて、枢要な地位におられたかと思います。厚生労働大臣もお務めであったかと思います。
あのときに、陳情は全て民主党の幹事長室を通してこいというふうにおっしゃいましたね。私たちの県連は、自民党の本部なんかに来たら、かえって予算がつかない、民主党の幹事長室を通さなければ、びた一文予算をつけないという時期がございました。与党というのはこういうものだというふうに思って、私どもも、委員がおっしゃるようなつらくて悔しい思いをした。同じ経験を持っております。
だからといって、何をやってもいいということを申し上げているわけではございませんが、御党の前身である民主党が、二〇一〇年、企業・団体献金を受け入れるということを幹事会でお決めになったという新聞記事を私は拝読をいたしました。
そのときに、今御指摘の経団連は米倉さんが会長でいらっしゃいました。私は、個人的には親しくしておりました。米倉会長が、十月の二十六日、二〇一〇年のお話でございます、記者会見で、企業は社会的な一員であるから、日本をよくするための企業献金は必要なことだとした上で、民主党が企業献金を受け入れるのであれば、喜んでこれに沿ってやっていきたいということをおっしゃっておられるわけで、その前に、民主党の幹事会において献金の受入れというものを再開するということを決めた。
なぜならば、政権を交代した、つまり、自民党から民主党に政権が交代をした、だけれども、その後、個人献金は伸びなかった、民主党の収入のほとんどを政党助成金が占める実態は変わらなかったということで、小沢一郎氏の後に後任の幹事長に就かれた枝野幸男さんが、税金で運営されている政党という批判はかわさねばならないということで、企業・団体献金の受入れ再開について検討を始め、その後、幹事長に就任した岡田さんが、企業、団体が政治の面で資金を出すことは一定の範囲で認められるというお立場だった。だから、いろいろな党がそういういろいろな、時によって立場が変わるわけです。
だから、私が言いたいのは、私たちが正しくて皆さんが間違っているとか、そんなことを言っているんじゃなくて、民主主義を支えるコストは誰が負担をすべきなのか、そして、それはきちんと公開をされて、主権者たる国民が判断を下す。いやしくも、個人であろうが企業であろうが団体であろうが、それが公の利益に反するようなことをすれば、それは主権者たる国民の審判によって断罪される、断罪という言葉はよくないな、きちんとした判断が下される、それが民主主義というものだと私は思っております。
○長妻委員 これは、なぜこの議論がここで今起こっているのかという反省が全くないですね。
裏金の問題が起こって、パーティーの問題が起こって、それで企業・団体献金、企業、団体によるパーティーの券の購入というのが大問題になっているわけじゃないですか。この機に廃止しようというふうに今機運が盛り上がっているわけですよ。
そういうことをきちっと反省して、きちっとした判断をしていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。よろしくお願いします。
○安住委員長 この際、米山隆一君から関連質疑の申出があります。重徳君の持ち時間の範囲内でこれを許します。米山隆一君。
○米山委員 それでは、会派を代表して御質問させていただきます。
今ほどの企業献金のことにつきまして、ちょっと補足で、私はこれは飛ばそうと思ったんですが、質問させていただきたいんですけれども、石破総理がおっしゃるように、そういう考え方もあるとは思いますよ、それは結構です。それはいろいろな考え方がありますから。
でも、昔はどうだったというのは余り関係なくて……(発言する者あり)いや、関係ないです。だって、今どういう政策をするかを今我々は論じているわけですから。昔は昔で、それはどうぞ御総括ください。でも、今我々が論じているのは、これからやる政策です。これからどういう政策が正しいかを議論しているんです。
それに当たって、ちょっと何かと誤解があると思うんですけれども、石破総理、何度も八幡製鉄所政治献金事件判例をまるで金科玉条のようにおっしゃって、かつ、企業献金を禁止すること自体が違憲であるようなことをおっしゃられるんですけれども、それは違うでしょうと。
判決で言っているのは、豊富潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成するというのであるが、その指摘するような弊害に対処する方途は、差し当たり、立法政策にまつべきことであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ず、これをもって国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用の限りでないということであって、だから、別に、献金を許すという政策自体を否定するものではない。
それは、確かに憲法には反しないと思いますよ。同時に、献金を禁止するという法律も、別に憲法には反しないです。それは立法政策の問題なんです。それはそれぞれの、そのときそのときにおいて考えればいいことです。
今、首をかしいでいらっしゃいますから、では、どうやら石破総理は憲法に反すると思っているらしいので、憲法に反すると思っているのか、思っていないのか、教えてください。
○石破内閣総理大臣 これは、憲法上の根拠は憲法第二十一条だと思っております。表現の自由ということで、参政権ということには相なりません。
企業も表現の自由は有しておるわけで、それは自然人たると法人たるを問いません。これは……(米山委員「イエスかノーかで答えていただければいいんです」と呼ぶ)いや、ですから、理由もなしにイエスかノーということを言いますと誤解を招きますので。
それは、憲法違反、企業、団体の献金を禁ずるということは、私は少なくとも憲法二十一条には抵触すると思っておる、私自身はそのように考えます。
○米山委員 企業・団体献金を禁止することが憲法に反すると。
資料三ですと、現行の政治資金規正法は、全面禁止ではありませんけれども、一定の範囲で、資金管理団体、上記以外の政治団体に対する寄附を禁止している部分があるんです。
では、今の政治資金規正法は憲法違反である、違憲の法律である、今、石破さんはそうおっしゃったということでよろしいですか。
○石破内閣総理大臣 ここはばっさり禁止と書いてございますが、そこはいろいろな制約の下に認められておると考えておりまして、全面的にこれを禁止するというふうにはこの条文は読めません。
○米山委員 つまり、そうしたら、一定の範囲ならいいんですね。では、一円でも十円でもできればいいということですよね。
そうしたら、別に、確かに、本当に全面禁止しなくたって、何なら個人と同じように、百万円、全部一律百万円ですよ、そういうのがいいんですね。だって、それだったらこれと同じじゃないですか。そういうことですね。
立法政策として、例えば一企業、どんな大企業だろうがもう百万円ですよ、それはいいんですね。(発言する者あり)
○安住委員長 御静粛に。
○石破内閣総理大臣 それは、今の米山委員の御議論は、合憲ではあるが制約を決めることはどうなのかということであれば、それは立法論の問題として、認める余地があると思っております。
○米山委員 分かりました。
そうしましたら、では、結局、そういう制限はいいわけですね。全面禁止が悪いだけで、相当程度の、個人と同程度の制限をかけることは問題ないというふうにお聞きしました。違うんですか。
では、どうぞ。
○石破内閣総理大臣 それは立法論の問題ですということを申し上げております。
ですから、そこに制限することを私が是としたとか、そういう価値観を交えて言っているのではございません。立法政策としてそういう余地はあり得るということを申し上げたところでございます。
○米山委員 私は最初からそう言っています。
どっちを取るかはこの国会で決めるんですよね。ハングパーラメントで、何なら、野党の方が多数になってそういう立法政策だったら、それはそれでいいということですよね。(発言する者あり)いやいや、違わないです。
では、次に行こうと思います。この問題はこれで。
次に、加藤財務大臣にお聞きいたします。
加藤財務大臣、政治資金収支報告書、令和四年、令和五年の収支報告書で、二年間で三千八百五十万円の修正がなされております。
パネル五、資料五と書いてあるところですが、これが修正なんですけれども、令和五年五月三十日に提出して、十二月八日に修正。随分間が空くわけですよ。また、なかなか気がつかないんですねということなんですが。
これはどんな修正かというと、二と四を書き間違えました。本来は二千百八十九万七千九十七円のパーティー収入を四千百八十九万円と書きました。でも、それによって、ちなみに、勝会というんですけれども、勝会の繰越金は四千百八十九万円から二千百八十九万円に減るといいますか、貯金通帳には二千万円しかないのに、四千万円ですと書いたということなんですよね。
これはさすがに気がつきませんか。二十円を四十円と間違えるなら分かるんですけれども、二千万円を四千万円と間違える。しかも、これは結構、加藤大臣にとっては大事な政治団体だと思うんですけれども。
これは一体全体、何で会計責任者、事務担当者、また加藤財務大臣自身は気がつかなかったんですか。
○加藤国務大臣 今お話しいただいているように、記載上は二と書くべきところを四と記載をしたということでありますが、こうした間違いがあった背景なんですけれども、実は、うちの事務所でパソコンを使いながら収支報告書を作らせていただく。詳細はちょっと、私も全部知っているわけじゃありませんが、途中で何かバグが起きると一個駄目になるので、バッファーを使いながらやっていたんですね。本来、訂正してきちんとしていたものはそうなっていたんですが、もう一個予備用に持っていたものが実はあって、担当者が間違ってそっち側を出してしまった。
だから、本来のものを出しているつもりだったのが、違うものを出したということに気がついたというので、少し遅れた。これは本当に、こちらでしっかりチェックしなかったことをおわびを申し上げなきゃいけないと思っています。
○米山委員 いや、それは全然理由になっていないんですよ。だって、間違ったものが何でできたんですかという質問をしているのに、間違ったものを出したからですというのは、それは何の理由にもならないんです。何で気がつかなかったという理由にもならないんですよ。
ちなみに、この法人、八千二百八十一万三千三百九十五円の収入がありまして、一年間に六千九十一万円ほど支出しているんです。支出項目を見ますと、令和四年五月十日には西麻布のバーで十七万円、十二日には同じバーで二十一万円。十七日には客単価三万円の西麻布の焼き肉屋さんで二十九万七千九百円という、目もくらむような高額の会合飲食費が次々と支払われている上、加藤財務大臣が代表を務めていらっしゃる自由民主党岡山第五選挙区、今は選挙区変更で第三になっていますけれども、選挙区支部に三千四百七十万円も寄附している。大層重要な政治団体のはずなんですよ。
だから、まずもって、間違って作ることもそうなんですけれども、出す段階で気がつくでしょう、先ほど来そう言っているんです。だって、貯金通帳に二千万しかないのに繰越金四千万と書くんですから、どんな間抜けな会計責任者でも事務担当者でも、そもそも加藤大臣自身だって自分の通帳をたまに見るでしょう。それで気がつかないんですかと聞いているんです。
○加藤国務大臣 ですから、先ほど、PC上に二種類の資料を結果的に作ってしまっていて、一つはきちんと二と書いてあった資料がありました。何かバックアップのものに、間違えて四と打っていたものがそのままバックアップにあって、本来だったらきちんとしたものを出すべきところを、担当者が間違って、そうだと思って違うものを出した、こういうふうに聞いているわけであります。
○米山委員 まあ、分かりましたよ。では、出すときは見ません、そういう主張ですよね。
出すときに、一応その中身を見ようとか、普通思うでしょう。だって、それは今、要するにプリントアウトして出すわけですからね。そのときは会計責任者も事務担当者も全然見なくて、ただただ自分のパソコンの中にある、四という、正しいものだけを信じ込んでいました、今、そういう御主張ですよね。そうおっしゃるならもうそれで、そこは押し問答だからいいんですけれども。そういう加藤大臣が財務大臣をされている。
そうしたありとあらゆる書面というものは、直接、出すときには見ないということですよね。もう自分のパソコンの中にあるものを信じ込んで、出すときには一切チェックも何もしない人が大臣をされているということとお聞きしました。
ちなみに、この事務担当者の方は、加藤大臣が厚労大臣のときに大臣秘書官をされていると思うんですけれども、そういう大層間抜けな方が、自分で出すのに何もそれを見ないという人が大臣秘書官をされていたということなんですかね。そうおっしゃいますので、それは結構です、そうしたら。
ちなみに、二と四を書き間違えたということなんですけれども、それが一か所なら分かるんですけれども、これは特定パーティーなんですよ、この間違えているパーティーは。なので、その三とその十の二か所に記載する場所があるんですね。書き間違いで、同じように二と四というのをそれぞれ別の場所に書き間違えているというのは、そんなことが起こるんですか。
ちなみに、加藤大臣、今ほど何か大分詳しく、いや、こっちのバッファーにあるみたいなことを言われましたから、その作った方、会計責任者なのか事務担当者なのか知りませんけれども、その方にヒアリングしたんですよね。そうしたら、その方に、何で二か所おまえは同じように間違えたんだと聞いたんだと思うんですけれども、何でこんなふうに二か所間違ったんですか。
○加藤国務大臣 済みません、そこまで詳細には聞いておりませんが、ちょっと確認しなければなりませんけれども、一つ何かそういうシステムがあるんだそうです、総務省から出されている。何かそれを使って作ったと。その代わり、途中でミスがあると消えてしまうので、バッファーでもう一個作っておかなきゃいけなかった。それが今申し上げた背景にあるということは御理解いただきたいと思います。
○米山委員 いや、加藤大臣はどうやら自分でやられたことがないんだなと思ったんですけれども、政治資金収支報告書、これは総務省がエクセルを出してくれております。ですので、合計等々は自動的にいきますよ。だから、そういう意味では、合計の数字が合わないということはむしろめったに起こらないわけなんですけれども、個別に入れる数字は個別に入れるので、それは二と四を二か所で、個別に、同じように間違えないとそういうことは起こらないんですよ。
今ほど、加藤大臣は聞いていないとおっしゃられましたけれども、こんな深刻なことをちゃんと聞かないんですか。だって、これは結構大事な話だし、実際問題、今、加藤大臣、こうやって気に入らない私にあげつらわれているわけですよ。そんな大きなミスをした秘書官に、しかも、別にその人をあげつらえというんじゃないですよ。せめて、だって、不可解なところがあったらちゃんと聞かなきゃいけないのに、聞かないわけなんですね。
では、そんなお仕事を財務省としてもされるんですね。何か二と四を二回も三回も、なぜか二と四を、違うところなのに、同じように間違えた官僚の方がいても一切それを聞かない、そういうお仕事をされているのかと、ちょっと、なかなか驚いたわけなんですが。
ちなみに、政治資金規正法第九条一項において、会計責任者はパーティー収入を会計帳簿に記載しなければいけないと定められております。加藤大臣のところでは、この会計帳簿はちゃんと記載されているんですよね。そして、会計責任者の帳簿を参照して収支報告書を作ったんですよね。そちらは確認されましたか。
○加藤国務大臣 会計帳簿に記載をする云々というのは、政治資金規正法にのっとってやらせていただいております。
ただ、うちの事務所の場合は、基本的に政治資金パーティーごとにまとめて記載をし、実際に資金を出していただいた方については預金通帳に、振り込みをいただいていますので、その預金通帳と、それからあと、参加者名簿ですね、それを含めて全体で管理させていただいているところだと聞いています。
○米山委員 分かりました。
では、次に、令和五年の収支報告書を見てください。資料七のところ、パネル七ですね。
こちらはもっと強大な、物すごい修正がいっぱいありまして、六個パーティーをやっているんですけれども、パーティーというか、昼食会とかいろいろなものがあるんですが、二月十三日がマイナス二百五十万円、三月二十七日の昼食会はマイナス二百五十万円、六月五日の昼食会は四百万円、七月二十四日の昼食会はマイナス六百万円、九月二十八日のパーティーが百万円、十二月八日の昼食会はマイナス二百五十万円と、六か所のパーティーがやられているわけです。
でも、今ほど、大臣、各パーティーごとにちゃんと帳簿をつけているとおっしゃいましたよね。どのパーティーもみんな五十万単位で間違っている、そんなことが起こりますか。それぞれ別の帳簿についているんでしょう。それぞれ別の帳簿についていて、それぞれつけているのに、全部の帳簿でなぜか五十万単位で切れよく間違える。そんなことができるんですか、人間というのは。何でこんな間違いが起こったんですか。
○加藤国務大臣 それぞれ別というか、会計帳簿は一つですから。(米山委員「でも、別と言われたんですよ」と呼ぶ)いや、だから、それをパーティーごとに計上させていただいている。
その集計に当たって、この間は、先般の本会議で申し上げましたけれども、重複してしまったり、そうしたミスがあって、それを届け出た後気がついたので、至急訂正させていただいたということであります。
○米山委員 帳簿自体は、冊子自体は一つだとして、ページが分かれて、各パーティーごとにちゃんと集計しているとおっしゃられましたよね。しかも、その中で重複があったみたいな話ですよね。
全部、切れよく重複するんですか。二百五十万、二百五十万、四百万、六百万、百万、二百五十万、そんな重複というのはどうやってするんですかね。どう考えてもといいますか、それは疑って恐縮ですけれども、こんな、ちゃんと別々に六つ集計しているのに、六つ全部でこんな切れのいい修正が起こるということは、実はそれぞれのパーティーに何か別の収入をつけておいて、何百万円ずつか。だって、パーティー収入は正直分からないですから、それぞれ計上しておいて、後で、ああ、これを何か計上しておいたらまずいなと思って全部引き揚げたから、全部減っているんでしょう。そういうふうに人為的にしなかったら、こんな切れよくなるわけがないじゃないですか。そんな都合よく、二百五十、六百なんて重複はできないです。
所詮、それは私は疑いのレベルで言うしかないことなんですけれども、それを最も疑うべきは、加藤大臣、その人じゃないですか。だって、自分の部下がそんなとんでもない間違いをしていて、場合によっては、自分の部下が何か不正をしているかもしれない。だって、これは疑いますよ。通常、そんな重複だけではこんなことは起こらないから。
それは聞いたんですか。何でこんな切れよく六つのパーティーでそんなふうに重複するの、おまえ、ちゃんとそれを見せてみろ、何がどう重複したのか、何でそうなんだと確認しましたか。
○加藤国務大臣 ですから、先ほど申し上げた会計帳簿には一回一回の数字が書いてあって、そこの集計において間違いがあった。
そういう説明を受け、私も、これだけ頻繁にあることに対してはかなり強く言ったところでありますけれども、そこはちょっと、本人がやはり自分のミスだということでありましたので、それはそれとして、私自身は受け止めた。実際、提出して直ちにそこを気がついて、訂正して出させていただいた、こういう経緯でもあります。
○米山委員 要するに、今のお答えは、秘書の説明をうのみにしました、自分は一切、具体的にどんなミスが起こったかは確認しませんでした、そういう御回答なわけですよね。
百歩譲って、それは加藤事務所の中のことですから、加藤大臣とその秘書の間ではそんなに信頼されているのは、それはそれで、結構かどうかはともかくとして、そうなんですかとしか言いようがないんですけれども。
大臣、大臣と言っていますが、財務大臣なわけです。財務大臣としても、そういうふうに同じような仕事ぶりでされるんですか。何か、どう見たって怪しいだろう、だって、これは通常、どこかの会社でこんなことをしたら怪しいですよ。そういうことを発見しても、いや、いいんだ、会社の人がこれは重複をしたからですと言ったら、具体的な証憑を一切確認せずに、ああ、そうですね、それでいいですよ、そういうふうに確認される。それが加藤大臣の仕事ぶりだということでよろしいですか。
○加藤国務大臣 正直言って、パーティーの収入、それぞれの集計等は事務所の秘書に任せてやっているわけであります。
今回、こういったミスがあったこと、これは大変重たいことだというふうに私も認識をしておりますけれども、長年私のために働いてきた人間でもありますし、これまでの仕事ぶりとしても、そうした事務的なミス、本当はあってはならないことではありますけれども、それはそうした説明として私としては受け止めさせていただくと同時に、こうしたことが起きないためにこれからどうすればいいか、この中で今検討させていただいているところであります。
○米山委員 どうも、麗しい人間関係には敬意を表しますけれども、それはその限りではいいですけれども、もう少し幅広く見ていただきますと、結局、政治資金自体の信頼性に対する問題なわけですよ。
先ほど来、石破総理は何度も何度も公開、公開とおっしゃられていますけれども、幾ら、こんな間違ったものを出して、しかも、明らかにおかしいだろう、普通、常識で考えておかしいだろうという修正をしても、その中身は何にもこうやって確認されないわけですよ、具体的には。具体的に確認せず、それでいいですといって、それでは、結局、公開なんて意味がないんですよ。公開というのは、ちゃんと公開して、おかしいところがあったらそれの細部まで確認しなかったら、何の意味もないじゃないですか。ただ形式的にやって、間違ったら、ごめんよと言うだけ、そんなのは公開にならないわけですよ。
ちなみに、これは一応、政治資金監査というものがついているはずですよね。この監査をしている方は何にもおっしゃられなかったんですか。だって、幾ら何でもおかしいでしょう。特に、先ほどの令和四年の分だと、それはもう繰越金が全然おかしいわけですから。繰越金が倍になっちゃっているわけですから、通帳等々を見たら、いや、合わないでしょうとなるわけなんですが、それは監査の方は何にも言わなかったんですか。
○加藤国務大臣 ですから、最初の令和四年度の分については、まさに出すときにさっき言ったミスをさせていた。そこまでのプロセスは一つ一つ踏んできたということであります。
それから、今回を含めて、収支報告書に関しては、さっき申し上げた会計帳簿など一式は出させていただいています。
ただ、委員御承知のとおり、政治資金規正法で会計監査の対象は支出になっているので、会計監査の方としては、支出のところを見ていただいていた。だからいいという意味じゃなくて、だから、監査人としては、ある意味ではそこは見ていただいていたんだと。
ただ、今後、先般、政治資金規正法の改正がされました。これから収入についてもしっかりやるということでありますから、更に、こういうことがないように取り組まなければならないというふうに思っています。
○米山委員 そうなんですよ。おっしゃるとおりといいますか、そこは。
公開、公開とおっしゃいますけれども、実は全く、収入に関しては監査も何にもされていない。政治資金規正法上は、帳簿とチェックする必要すらない。要するに、収入に関しては、どんなでたらめな数字を出して、そして、それが間違っていても、基本的には修正すればそれでいいというのが、今回の問題の根本なわけですよね。根本なわけなんです。
政治資金規正法の改正案ということで、我が党も前国会で、ちゃんと収入にも監査をしましょうと。それはそうですよねということだと思うんです、そうしないと何の意味もありませんのでと思うんですけれども。
そこで、石破総理にお聞きしますが、そうしましたら、収入はこれからは監査する、そういう法改正を進めることに関して、今、加藤財務大臣もおっしゃいましたし、それはもう進められるということでよろしいんですか。
○石破内閣総理大臣 さきの常会で、政治資金規正法の一部を改正する法律案、これが成立をしたところでございます。そこにおきましては、国会議員関係の政治団体について、現行の支出だけではなくて、新たに収入につきましても公認会計士などによる政治資金監査の対象とされたということでございます。
先ほど来、米山委員が御指摘になっておられます会につきましても、国会議員関係政治団体でございますから、改正法の施行後は、収入につきましても適切に監査がなされるということだと理解をいたしております。
○米山委員 それは結構なことでございますので、しっかり監査をして、そうすればきっとこういう訳の分からない修正はないんでしょうから。かつ、そういう訳の分からないことが起こったら、それはきちんと内容を言っていただくということになろうかと思います。
では、次に、資料十一の方をお願いいたします。
こちらは、まだ続いているキックバック問題といいますか、裏金問題ということで、大変恐縮ながら、これはしつこいと言われますけれども言わせていただきたいんですけれども、元安倍派事務局長の松本淳一郎氏の裁判におきまして、松本元事務局長は、二〇二二年八月に開いた協議で還流再開が決まり、その後、幹部らが手分けして所属議員に伝達した、こう証言されているわけなんです。
ところが、三月一日の政治倫理審査会において、西村康稔議員は、八月の上旬の会ではいろいろな意見が出されましたけれども結論は出なかったと証言し、松野博一議員は、そういった会合があったのかなかったのか、有無も含めて承知しておりませんと証言し、三月十八日の政治倫理審査会において、下村博文氏は、八月五日の還付の継続はこれは決めていない、どんな形で決まったかは私自身は全く分からないということでありますと証言し、三月十四日の政治倫理審査会において、世耕弘成議員は、八月五日の還付の継続はこれは決めていない、どんな形で決まったかは私自身は全く分からないということでありますと証言しております。
これは松本元事務局長の証言と全然矛盾していますし、さらに、実は三月一日の政治倫理審査会において、塩谷元議員は、困っている人がたくさんいるから、それでは継続でしようがないなという、そのぐらいの話合いの中で継続になったと。これは今度は松本元事務局長と合致する証言をしているんですよ。
そうすると、松本元事務局長とも矛盾するし、塩谷氏と西村、松野、下村、世耕氏のこれも矛盾している。そうすると、少なくとも塩谷氏と西村、松野、下村、世耕氏のどちらかはうそをついている。どっちかがうそをついていないとあり得ないことになるわけなんです。
これも放置しちゃ駄目じゃないですか。先ほどの政治資金収支報告書だって、まるっきり間違ってまるっきりうそなものを公開したって、そんなものは公開にならないでしょうということですから、同じように、いや、政治倫理審査会に出たからいいですという話じゃなくて、まるで矛盾しているのでしたら、それはちゃんと矛盾を解く、それがあるべき姿だと思うんですよ。
総理は総裁ですから、自民党総裁として、さすがに議員じゃない方はともかくとして、議員になられた西村さん、松野さん、世耕さん、それは自発的に政治倫理審査会に出るように申し立てる、申し立てなさいと御指導されたらいかがですか。御所見を伺います。
○石破内閣総理大臣 自発的に出ることを促す、何か日本語としてよく理解ができないところでございますが、それは、政治倫理審査会というのはそういうものであって、それぞれの議員が自らの意思によって政倫審に出て、いろいろな疑いというものを、そうではないのだと、自分はそうではないということを申し述べる場でございます。ですから、私は、議員個人個人としてはそうあるべきだと思っております。
それは、自分自身が何らそういうことがないということであれば、そういう場を通じて、そういうことがないということを理解いただくということは活用されるべきだが、繰り返しになりますが、自発的である以上、総裁としてそれを促すということは、それはでき得る立場ではございません。
岸田さんが出られたのは、自身が出て、では、皆、我に倣えということであったかなというふうに思っております。
○米山委員 それはもちろん自発的ですから。でも、促すですからね。促すのは別に、どうぞと、した方がいいんじゃないですかというだけであって、しろというんじゃないですからね。
では、自発的だからいいですよと。相互に矛盾しています、どう考えてもどっちかがうそをついています。だけれども、それは、いや、総理・総裁としては知らぬよと。それぞれがそれぞれに自発的に行かれて自分の思うところを言ったから、矛盾点はあるけれども、知らぬ。では、全員、矛盾点はあるけれども、どっちももうみそぎは済みました、公認します、二千万上げます、そういう主張ですか。それが自民党の在り方だということですか。
何か矛盾していたら、それは総理として、ちゃんとお調べするなりなんなりで、矛盾点を解いてこいよ、そのぐらい言ったらいいんじゃないですか。それは最終的に決めるのは議員として、ちゃんと矛盾点を解いてくださいと。我々はちゃんと、だって、総理は何度も何度も、信なくば立たず、国民の信頼を得ると言っているんですから。
国民の信頼を得るためには、全員の話が一致しないとおかしいんだから、みんなで話をちゃんと合わせて、合わせてというのは口裏を合わせるという意味じゃないですよ。ちゃんと話をしたら真実が出てくるでしょう。ちゃんと話をしたら真実がどれかは分かるんだから、みんなで真実を言ってこい、そう言われたらどうですか。言わないんですか。
○石破内閣総理大臣 最終的な判断をするのは個人ですが、私は、自らがそういうことはないと言う場がわざわざあるわけだから、それは出るべきだなというふうに思います、正直言って。
そして、公開というのもあるわけで、非公開という選択もある。それは、なぜならば、そこにおいて、いついつ誰とということは言えない場合もございますから、非公開という選択も私は排除しません。
しかし、そこにおいて、政倫審の委員が話を聞いて、ああ、これはこういうことなんだなと。そして、そういうものを、黒塗りというのか、そういう部分を残して、概要の報告は議長に行くわけですね。そこにおいてどういう心証が形成されるかというのは極めて重要なことであるからこそ、政倫審というものが設けられた。この場を最大限に活用するというのがそれぞれの議員のあるべき姿だと私は思っております。
○米山委員 意味がないという言葉がありましたが、でも、今、石破総理は、いやいや、ちゃんと褒めるんですよ、これから。石破総理はやるべきだとおっしゃられましたので。この予算委員会をきっと西村さんも松野さんも世耕さんも聞いておられると思うので、それは総理・総裁がこうおっしゃっているわけですから、是非ちゃんと行かれていただきたいと思いますよ。テレビを介して申し上げさせていただきたいと思います。
だって、何せ今のままだったら、誰かがうそつきですから。そんな状態を放置するのは、それこそ自民党のためにとっても皆さんのためにとってもならないわけですし、国民のためにとってもならないわけですから、是非解決していただきたいと思います。
そして、当面は、それはもちろん自発的なところをお待ちしますけれども、それが全く解決されない、矛盾のままであるということになれば、我が党は九人いますので、政倫審への申立ては可能ですから、そういうこともあり得るというふうに申し上げさせていただきたいと思います。
それでは、資料八を御覧ください。
似たような話は実は麻生派の方々においてもございまして、これは二〇二二年に政治資金規正法違反で薗浦健太郎元衆議院議員が罰金などの略式命令を受けた事件で、元秘書が特捜部の調べに対して、為公会の政治資金パーティーのキックバックから一七年に配分された三百八十万円を裏金としていたと証言しているんですね。ちゃんと、だから、要は麻生派でも一六年、一七年まではキックバックがあったと言っているわけなんですよ。
ただし、そこはフェアにということですけれども、これはもう時効になっていますから刑事の話じゃないし、実際、その後はきちんと政治資金収支報告書に書くようにした、正々堂々。収支報告書に書けばそれは別に違法じゃないですから、キックバックしたって。それは別に結構ですよということではあるんですけれども。
しかし、それこそ信頼という話で、では、一六年、一七年はあったんですよね。時効だから刑事じゃないですけれども、それはあったという事実は認められたらどうなんですかということだと思いますので、お聞きしたいと思います。
鈴木法務大臣にお伺いいたします。
鈴木法務大臣が代表を務める国家戦略フォーラム二〇二五は、二〇一八年には志公会からキックバックと思われる九十四万円の寄附を受けておりまして、パネル九ですね、それを記載しております。二〇一七年にはそのような記載がないんですけれども、それは受けていなかったのか、それとも不記載だったのか、どちらですか。
○鈴木国務大臣 今先生お尋ねの件でありますけれども、私の政治団体の政治資金は、法令、政治資金規正法に基づいて適正に処理をしております。
その点は、今お話がありました二〇一八年、二〇一七年共にそのようだと承知しております。
○米山委員 つまり、あったかないかは答えません、そういうことですね。要するに、あったかないかは全く、今私はすごく明確に聞いたわけですよ、あったんですかと。あったけれども記載していなかったのか、なかったんですかと聞いたのに、いや、適正に処理しておりますということは、それはもう答えませんという御回答とお聞きしました。これは押し問答してもしようがないので、次に移ります。
岩屋外務大臣、こちらも、岩屋外務大臣が代表を務めます新時代政経研究会は、二〇一八年、志公会からキックバックと思われる百四十六万円の寄附を受けて記載しておりますが、二〇一七年にはその記載が認められません。
明確に御質問しますが、それはそういうキックバックはなかったからなのか、あったけれども書かなかったからなのか、どちらですか。
○岩屋国務大臣 当該政策集団は、私も長らくお世話になりました。昨年退会をさせていただきましたけれども、それまでの間は毎年パーティーに参加し、協力をしてまいりました。
一貫して、その収支は、政治資金規正法に基づいて適正に報告をしていると承知をしております。
○米山委員 こちらもあったかないかは答えられませんという御回答でございました。そうでしょう。だって、私、イエスかノーか聞いているのに、全然関係ないことを答えているわけですから。
次に、麻生派に御所属の武藤経産大臣にお伺いします。
武藤大臣が代表を務める武藤容治をはげます会は、二〇一八年、志公会から恐らくキックバックと思われる百三十万円の寄附を受けてこれを記載しておりますが、二〇一七年にはそのような記載が見られません。これはキックバックを受けていなかったのか、あったのに不記載だったのか、どちらですか。
○武藤国務大臣 米山委員にお答えさせていただきます。
私の政治団体の政治資金の収支につきましては、政治資金規正法に基づき適正に処理をしております。二〇一七年以前も同様と認識をしております。
○米山委員 私、ちゃんと通告していますから。早口で聞きづらくたって、みんな分かって答えているわけですよ。だって、分かって答えているわけでしょう。答えていますよ。
こちらもまた答えられないという回答だったんですけれども、では、斎藤財務副大臣、斎藤洋明政策研究会、二〇一八年に志公会からキックバックと思われる二十九万円の寄附を受けてこれを記載しておりますが、二〇一七年にはそのような記載が見られません。これはキックバックを受けていなかったからですか、それとも不記載だからですか、どちらですか。
○斎藤副大臣 米山委員の御質問にお答えいたします。
私も、二〇一七年以前におきましても、二〇一八年以降におきましても、政治資金規正法にのっとりまして、全て所属する政策集団からの寄附は記載をしてございます。つまり、二〇一七年以前は、委員がおっしゃるキックバックはありませんでした。
○米山委員 斎藤さんはちゃんとしっかり、ないと言ったわけです。ほかの人は言っていないです。それは、ほかの方は言えないんですかね。ない人はないと言えるでしょう。そうでしょう。だって、さっきからそういう、通告もしているし、分かりやすい質問ですから、ない人はないと言えるんですよ。
では、次に、高橋国土交通・内閣府・復興副大臣にお伺いいたします。
二〇一八年に栃木県参議院選挙区第二支部が、恐らくキックバックと思われる千二百万円の寄附を、千二百万円ですよ、寄附を受けておりますが、記載しておりますが、二〇一七年にはそのような記載が見られません。それはキックバックを受けていなかったからですか、それとも不記載だったからですか、お答えください。
○高橋副大臣 政治資金につきましては、法律に基づいて適切に処理をしてまいりましたので、ということは、適切に処理をした政治資金収支報告書に記載がないということは、なかったということでございます。
○米山委員 これはワンクッション置いていますから、何かあるんでしょうね。直ちにないとは言えないということですから。
飛ばしましたけれども、瀬戸内閣府副大臣にお伺いします。
瀬戸内閣府副大臣、香川県第二選挙区支部も六十八万円の寄附を受けておりますが、二〇一八年に。二〇一七年にはそのような記載がないんですが、これはキックバックがないからですか、それとも不記載だからですか。
○瀬戸副大臣 お答えさせていただきます。
私の政治団体の政治資金の収支につきましては、政治資金規正法に基づき適正に処理しておりまして、二〇一七年以前も同様と認識しております。
○米山委員 こちらの方ははっきり言えないわけですよ。
結局、それは、公開すればいいというものじゃないでしょうということですよ。こうして、それは時効ですから、時効にかかったものはしようがないといえばしようがないのかもしれませんけれども。これだって、やはり麻生派だってあったわけでしょう。だって、実際に薗浦さんの秘書の方がそう言っているわけですから。その事実を、ある人は隠しているわけですよ。
最後、あと二分ですからもうまとめようと思いますけれども、是非、石破総理、こういうもやもやしたものをずっと残しているから、いつまでたったって信頼なんて回復しないわけです。
別に我々も、時効にかかっているものを刑事で何か処罰しろなんて言っているわけじゃないわけですよ。それは法律は法律で結構なんですけれども、事実は事実としてちゃんと認めたらいかがですか。
先ほどの元安倍派だってそうですし、この麻生派だってそうですから、事実としてあったものは、皆さんきちんとそれを国民の前でお話しされる、その場としては政倫審があるんですから、是非、政倫審に皆さん来られてきちんと事実を話されることを、石破総理から、石破総裁から御指導していただきたいと思いますけれども、御所見を伺います。
○石破内閣総理大臣 先ほど申し述べたとおりでございます。私は、政治家としてはそうあるべきだと正直言って思っております。
そこにおいて、自らがそういうものに関与していないということを述べるのは貴重な場であると思っておりますし、非公開というプライバシーを守る手段もございます。これはセレモニーだから意味がないとか、そういうことを決めつけることが正しいと私は全く思っておりません。そういう場は最大限に有効に活用されるべきだと思っております。これは強要はできませんので、私自身はそう思っているということを申し述べた次第でございます。
もう一つは、ないことを証明するのはすごく難しいということだと思いますね。ありませんということを証明してみろ、それは証明できません、だからおまえは黒なんだろう、それは一種の印象操作なんだろうと思っております。私どもとしては、ないということも当然可能性としてはございます。
そういうこともまた念頭に置いて、いずれにしましても、私どもは、禁止というよりも公開だ、そしてまた、委員が御指摘のように、こんな穴があるじゃないかということがないように、これから先の御議論を生かしてまいるのが筋かと思っております。
○米山委員 大変結構なことでございますので、テレビの皆さんも、是非、自民党の皆さんがどうやらそうしてくださるようですから、御期待して待っております。
そして、ないということは証明できないという話は、ちょっとだけ、一言だけ言わせていただきますが、それを証明するために帳簿があります。
○安住委員長 時間を超えておりますよ。
○米山委員 以上です。
○安住委員長 この際、近藤和也君から関連質疑の申出があります。重徳君の持ち時間の範囲内でこれを許します。近藤和也君。
○近藤(和)委員 立憲民主党の近藤和也です。
少し空気を変えます。
改めまして、能登半島地震から十一か月がたちました。そして、豪雨から二か月半がたちました。復旧復興に当たっていただきました関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。
一月、二月、三月、そして九月、十月のあの惨状から見れば、よくぞここまで復旧してくれた、こういう見方は当然できます。仮設住宅も随分できてきました。家に戻れる方も増えました。一方で、十二月三十一日のあの風景から見れば、まだ悲惨だと言わざるを得ませんし、例えば海岸沿いのおうちだとか田んぼだとか、港湾はかなり修理は入ってきていただいていますけれども、小さなところはほとんどまだ直されていません。ですから、片方から見れば、よくぞここまでたどり着いた、片方から見れば、まだまだだという双方があるということを是非とも皆様には受け止めていただきたいというふうに思います。
そして、その上で、総理、十月の五日、珠洲市の大谷、そして輪島市の中心街、中心地、行かれましたよね。あの豪雨の二週間後です。なぜ、あの泥だらけのぐじゃぐじゃな状況を見て選挙したんですか。それは、私は今問い詰めたいわけではありません。あのときの能登の多くの方々の思いは、何だ、自分たちは二番目、三番目でいいのかと、置いていかれたような気持ちだったんです。悔しかったんです。怒っていました。私は今でも怒っていますけれども、総理には、この気持ちを、心のスポンジがあるとすれば、あのときの悔し涙や怒りをしっかりと吸収をした上で、これからの能登の復旧復興に当たっていただきたいと思います。
次の質問に入らせていただきます。
まず、石破内閣の災害の復旧復興に対しての基本姿勢から伺います。
これは、四月の九日の時点で出された財政制度分科会での資料です。被災地の多くが人口減少局面にある中、将来の需要減少や、維持管理コストも念頭に置きながら、集約的な町づくりやインフラ整備の在り方も含めて、十分な検討が必要ではないか。これは、要は人口減少地域に投資したって無駄だというふうに受け取れかねない資料なんです。
この右側の囲みを見ていただきたいです。こちらは、土地区画整理事業、東日本大震災の復旧復興の事業でゼロ%だとか四一%だとか、パーセンテージの低かった、成果の低かったものをわざわざ取り上げています。ちなみに、全部で六十五事業あるんです。一〇〇%達成されているものは十事業あるんですよ。九〇%以上のものは更に八事業あるんですよ。わざわざ最も悪い四つだけ取り上げて、無駄な投資はしないようにということを言っているんです。
このことについて、この精神を受け継がれていたら困るということで、総理、見解をお願いをいたします。総理、これは総理の、石破内閣の姿勢ですから。
○石破内閣総理大臣 済みません。足らざるところは関係大臣が答弁申し上げます。
憲法二十二条というのがございまして、移動の自由とか居住の自由とかを定めたものでございます。
コンパクトシティーという言葉をもちろん委員御存じだと思いますが、地方創生の議論の中で、あちこちに集落が分散している、それだけではもう自己完結で集落の機能が果たせなくなったので集約しようという議論が十年ぐらい前からございます。
そのときに出したのは、いや、そうはいっても、私はもう二軒、三軒になってもここに住みたいんだということは尊重しなければいかぬのではないか、それは日本国憲法第二十二条に定められた居住の自由であり移動の自由であるということで、私は、地方創生大臣の立場ではございましたが、そういう議論はなるべく抑制的にすべきだというふうに思ってまいりましたし、今でもそうです。
自分たちが生まれ育ったコミュニティーを大事にしたいというお気持ちは、それは最大限に尊重していかねばならないと思っておりまして、財政制度分科会においてこういうお話があったということは事実として承知をしております。これをこれからどう受け止めるかは我々政治が判断すべきことでございまして、この見解だけが私は正しいとは思っておりません。
一方において、厳しい財政事情の中で、それは、例えば水道を引くにしても下水道を引くにしてもそうですね、集落にもう二軒か三軒しかない、そこにおいて誰の負担においてそれを支えるべきかという冷厳な議論は議論としてございます。しかしながら、そこにおいて居住の自由というものは最大限に尊重していくというのが日本国憲法の趣旨にかなったものだと私は思います。
○近藤(和)委員 居住の自由というのはまさにおっしゃるとおりなんです。私たちが山から下りて町の中へ住むかどうかというのは、私たちが決めることです。財務省の役人に決められたくありません。私たちも、本当に山奥で、いつ孤立集落になるか分からないところにいつまでも住んでいいかどうかというのは、心苦しい思いでいます。よその人に言われたくないんです。そこはしっかりと気をつけていただきたいと思います。
そして、例えば、財政のことでいえば、悪い四事業を挙げて無駄だと言うんじゃなくて、十八の事業が九〇%以上の達成率になっているんです。それを生かして、能登の復旧復興に生かしてくださいという方がいいんじゃないですか。
○坂井国務大臣 今の財政審の分科会のお話でございますが、過去の被災地の案件、今、悪いのばかりとお話しされましたけれども、ただ、実際に、そこで過大なインフラ設備を造って維持費に大変今苦労しているという事例があるのも、これまた事実でございます。ですから、そういうことも含めて、これからの町づくりは、知恵を出して、そしてそこも考えながら、各市町で考えてやっていただきたいという趣旨だと私は捉えております。
例えば、今コンパクトシティーのお話が出ましたが、そうではなくて、私個人としても、今、内閣防災のメンバーにしても、一人一人の皆さんがここに住みたい、過疎でもここに住みたいとなれば、それをどう実現をしていくかということを一生懸命考えて仕事をさせていただいておりまして、だからこそ、そこに住むのに、今まで以上に、例えばインフラにお金をかけないでやるような方法はありませんかというのを共に考えて工夫をしたい。
その一つとして、例えば、例でありますが、よく御存じの珠洲市に……
○安住委員長 手短に。
○坂井国務大臣 済みません。馬緤地区というのがございますが、ここは小規模分散型のシステムに水道を入れることによって水道の維持費を小さくして、こんな工夫をあちこちでやりながら、それぞれの皆さんの希望を実現をしたいと思ってやっております。
○近藤(和)委員 どんなに正しいことであっても、時を間違えれば、相手の心情の状況によっては傷つけることになりますから。このとき馳知事が、冷や水をバケツでぶっかけられた気持ちだ、上から目線で気分が悪いと。本当にそのとおりなんですよ。こういうことは二度とないように気をつけていただきたいと思います。どんな正しいことをやるにしても、言い方というものがあると思います。
それでは、次の質問に参ります。
今回の補正予算に対して、私たちも、これは選挙に入る前からも含めて、この能登の復旧復興に対しての補正的な案を出させていただいています。その中で、この赤字で書いてあるところ、丸、三角ですね、ある程度のみ込んでいただいたところです。ありがとうございます。
例えば、災害ボランティアへの支援拡充の中でガソリン代の支援ということを要求させていただいたんですが、今回の補正の中では、ガソリン代どころじゃないそうですね、交通費、バスだとか電車だとか、その分も入れていただいているということで、もう百二十点です。もし能登空港の飛行機が使えるということであれば百五十点だと思います。これは、ただ、まだ詳細は決まっていないと思いますので、何とか使えるようにしていただきたいと思います。
そして、例えば八番目の災害公営住宅の分について、国からの支援は四分の三から八分の七にしてくださいね、これはのんでくれていないですが、土地の造成部分を入れていただいたということも含めて、これも大変ありがたいと思っています。
もちろん、今日は、これをありがとうございますと言うために来たのではなくて、まだまだやらなければいけないことがありますということで、質問に入らせていただきます。
昨日の酒井なつみ議員、そして今日の重徳政調会長からもございました、被災者生活再建支援金倍増法案を出させていただいています。パネルの次のものになります。こちらについてなんですけれども、三百万円から六百万円に増やしてくださいということで出させていただきましたが、二月に入りまして、新たな給付金、地域福祉推進支援臨時特例給付金というものになります。こちらについては、対象世帯が1から8、幾つも分かれています。そして、対象も幾つもあるからこそ、はい、イエスということで、要はややこしいんですよね、要件が。
この点について、まずは重徳委員の方から、豪雨についての、もう一度支給してくれないかということについては、総理はお答えを明確にされなかったんですが、総理が答えたのは、地震で例えば準半壊や一部損壊で、そして豪雨で半壊以上になった場合ではこれが支給されますよということですが、地震で車が駄目になった、そして豪雨で車が駄目になったという方は対象外なんです。そしてさらには、地震ではほとんど被害がなかった、豪雨で半壊以上になったという方は対象外です、対象外なんですよ。しかも、例えば地震で準半壊でした、そして豪雨で半壊でしたという場合でも、その豪雨の半壊の罹災証明の中に地震という言葉が入っていなければ対象外なんですよ。
そうなので、総理、私、これは嫌みを言いたいわけではなくて、ごくごく一部の当たりますよという例を役所の方に言われたんだと思いますけれども、そうじゃない対象の方の方がたくさんいらっしゃるから取り上げているんです。その事実を是非とも分かっていただきたいと思います。
そしてさらには、市町によって対象にならない地域がありますよね。例えば内灘町ですとか、かほく市ですとか、液状化被害で大変な被害が出ているところ、そちらに対して出さない理由とすれば、高齢化率が能登の方が高いからとか、そういうことを言われていますけれども、例えば内灘町の西荒屋というところ、最もひどかったところです、宮坂というところ、室というところと、例えば志賀町の西山台の団地で比べれば、内灘町の西荒屋などの方が高齢化率は圧倒的に高いんです。データは出ていないですけれども、顔を見たら分かりますよ。だから、高齢化率というのは、これは単なる言い訳です。
数百メーター違うだけで支援が違うというのは、同じ災害です、同じ被害です、そして同じ支援であるというのが、総理、先ほど公平性という言葉を言われましたよね、これこそが本当の公平性なんじゃないですか。いかがでしょうか。
○坂井国務大臣 こういった制度というものは、多くの方に御納得いただける制度をつくり、そしてどこかで線を引かなければ制度として使えないということになっておりまして、今回、高齢者が多いという件、それから、特に半島地区で不利な条件にあったという点を考慮して、今回このような、今、制度として運用しているということでございます。
○近藤(和)委員 公平ということについて質問したので、済みません、坂井大臣、いい方だと分かるんですけれども、お答えいただきたいのは、石破総理が公平性と言われたので、石破総理にお願いいたします。
○安住委員長 ちょっと待って。総理に質問ですか。もう一度。
○近藤(和)委員 それでは、再度質問いたします。
総理は公平性が大事だということを言われました、過去からの災害と比べてですね。過去からの比較も大変大事なんですが、同じ災害で、同じ被害で、同じ支援ということの方が公平なんじゃないですか。この公平性ということについてお伺いをいたします。
○石破内閣総理大臣 それは何と何を比べて公平ということは当たり前の話で、当たり前のことを答弁するなとおっしゃりたいのだと思いますが、そこはやはり、今防災担当大臣がお答えしましたように、公平性というものを確保し、どこかで線引きをしないと制度というものは成り立たないのであって、どこまでもどこまでも際限なく広げていくということになりますと、かえって公平性を損なうことになります。ですから、どこかで線は引きます。
じゃ、そうするとどうなるんだよということですが、そのほかに、じゃ、救済できる制度がありませんかということであって、条件が違うんだけれども救済できる制度があるはずだというものをきちんと探して、それぞれの状況に応じて、こういう制度も使えます、こういう制度も使えますというふうなことをお教えするのも私は行政の役割なんだろうというふうに思っております。
ですので、できません、なぜならばといって蹴っ飛ばすよりも、こういうやり方がありませんか、こういうやり方がありませんかということを苦しんでおられる方々にきちんと提示をする。そしてまた、書類を書くのが大変面倒くさくてかなわぬ、もう書く気もなくなるというようなことがないように、書き方も含めて、制度の有無、そしてまた書き方、どうしたらできるかということを中心に考えてまいります。ただし、同じ制度を全部に適用はできませんので、どこかで線を引かねばならないのは当然のことでございます。
○近藤(和)委員 総理が別の方法がないのかということで、この六市町以外のところでは、住宅再建利子補給と言われましたが、正確には、自宅再建利子助成事業給付金というものなんです。家を建てる、直すときのお金を借りて、その利子分の三百万円までは支給しますよということなんですが。
ちなみにですが、対象件数は、石川県内は十九市町あるんです、残りの十三市町で半壊以上の家屋がどれだけあるか、三千です。約三千なんです。この制度、今どれだけ適用されているか、三十二件の申請で二十八件なんですよ。ほとんど使われていません。一%ですよ。
もうこの要件のことは詳しくは言いませんが、要件も厳しいし、そして周知もされていないし、そもそもが、同じ制度にすれば、行政の人だって助かるし、被災者の皆さんだって助かるんです。
この点については、是非とも、地域の要件をなくす、そして所得云々という問題もなくす。例えば六十五歳という要件についても、六十二歳の人は三年と一か月はこの制度が利きますので、三年後はできるんですよ。六十一歳の人は駄目ですけれども。でも、三年後を待たないと申請できないんです。そのようなことも含めて、年齢だとか家計の状況だとか地域の要件をなくすことの方が公平だと思います。
この点については、私たちの方から予算の修正を出させていただきますので、是非とも、これは法律じゃないですから、何とか検討していただきたいと思いますし、被災者生活再建支援金倍増については、今後の未来の被災地のために是非ともしていただきたいと思います。
そして、公平のことについてはもう一点だけ申し上げたいと思います。
今、能登で家を建てようとすれば、元々、地震の前までは一坪七十万円と言われていました。それが、数か月前は百万を超えました。今、百二十万とか、場合によっては百五十万とか言われています。二十坪の小さい家を造るのにも、例えば、地震前は一千四百万で済んだんです。今だったら、一坪百二十万だったら、二千四百万円です。一千万も上がっているんです。ですから、新しい制度をつくっていただいた、これは大変ありがたいです、六市町の方にとっては、三百万円増えましたから。でも、それ以上に上がっているんですよ。
私が申し上げたいことは、過去の災害との公平性という点を考えても、過去よりも物価が急上昇しているから、本当の意味での公平性というのであれば、もっともっと金額を上げていいんじゃないですかということを申し上げたいと思います。この点については、総理は難しいということで、いい答弁がもらえないのは今分かっていますので、何とか検討を、考えて、受け止めていただきたいと思います。
それでは、次の質問に参ります。
準半壊の壁ということ、恐らく多くの方はまだ聞き慣れていないと思います、半壊の壁は聞かれているかと思いますが。
今、能登半島地震の中で、罹災証明が出始めて大体八か月、七か月ぐらいでしょうか、総理、こういう会話がされているんです。半壊になってよかったねとか、二回目、三回目の申請をして、一部損壊から全壊になった、おめでとうなんですよ。つらいことですよ。被害が重くておめでとうと言う。
これは、六段階ありますよね、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、そして準半壊、一部損壊。この半壊と準半壊の間には大きな壁がございます。一番大きな壁というのは、公費解体の対象外だということです。
パネルを御覧ください。これは、珠洲市のある家屋の方です。屋根が竜のようにうねっています。そして、基礎部分も壊れています。そして、家の中、これはカメラを傾けて撮ったのではありません。家がかたがっているんです。そして、隣の家にもう寄りかかっています。お風呂も台所もトイレも壊れています。準半壊なんです。これを直そうとすれば一千万はかかります。この方は今どうなっているのかといえば、仮設住宅に入りたいけれども入れないんです。知り合いの家を転々としています。できれば、公費解体の対象に入れていただきたい。
何でもかんでも壊せと言うつもりはありませんが、今想定される未来というのは、結果としてこのような方が家を放置する。そうすれば、例えば、珠洲や能登町や輪島などは、ある地域、数百軒のところで、もう半分以上解体しなければいけません。準半壊や一部損壊で直せない方、もちろん現役世代は直してほしいですけれども、先ほど高齢化ということを言われましたよね、引退された方はなかなか家を直せません。そのまま放置される可能性があります。
そうすると、たくさん解体をした、そこに災害公営住宅を造っていこうとしたけれども、準半壊、一部損壊の空き地がぽつんと残ってしまって、地域を再開発しようにもできない。近所の方々も大変な状況が容易に想定をできます。
総理は、できることはしっかりやっていきたいということも答えられておられました。いろいろなやり方があるということも言われました。できれば、準半壊の方で、希望すれば公費解体の対象に入れていくということ、これを一つお願いをしたいと思います。
そして、もう一つ。私は何でもかんでも壊すというわけではありません。好きこのんで自分の家を壊してと言う人は誰もいません。できれば直したいです。準半壊であれば、応急修理制度で三十四万しか出ないですよね。ちょっと直すだけですぐオーバーしてしまいます。一部損壊は応急修理制度の対象外です。
こういう、直して地元に残って暮らしていきたい、慣れた家で、それこそ老後、最後の最後を全うしたいという方のためにも、今までの支援は足りないんだということを認識してほしいですし、新しい制度をつくっていくんだということを考えていただきたい。
この準半壊の壁について、一つは、公費解体の対象に場合によっては入れる、一つは、今までの支援は足りないですよということを受け止めて、何とか前へ進んでいきたいという答弁をいただきたいんですが、いかがでしょうか。
○浅尾国務大臣 公費解体を所管しておりますので、私の方から御答弁をまずさせていただきます。
能登半島地震においては、準半壊や一部損壊の被害認定を受けた被災家屋等が大変多く存在しているということは承知をしております。
その上で、廃棄物とみなすことができる公費解体の支援対象については、原則は全壊ということになっておりますが、特定非常災害に指定された能登半島地震は、全壊と半壊の家屋等が混在して、面的に大規模な被害が発生したことを踏まえ、社会インフラ等の早期復旧を進める観点等から、全壊の家屋のみならず、半壊以上の家屋……(近藤(和)委員「済みません、できない理由を聞いているのではないので」と呼ぶ)ちょっと説明させていただいて。
○安住委員長 手短に。
○浅尾国務大臣 すなわち、損害割合が二〇%以上で一定の居住の基本的機能を有する家屋の解体についても支援対象としているところであります。
今おっしゃっておる準半壊のところは、居住の基本的機能を喪失しておらず、かつ私有物であるため、所有者による修理で対応していただくということが基本となっておりますということでございます。
○安住委員長 総理、今の答弁では多分納得していないでしょうから、総理からお答えください。準半壊の問題だ、準半壊の壁の話をしているんだ。
○石破内閣総理大臣 仕組みは、今環境大臣からお答えをしたとおりでございます。
だから、半壊に満たない準半壊、あるいは一部損壊の家屋につきましては、基本的機能を喪失していないので補修して居住できますよね、だから所有者による修理で対応いただく、こういうことになっておるわけでございますが、これでは被災者に寄り添ったことには全然なりませんわなということになりまして、令和元年度より、修理に関する支援の対象に準半壊、損害割合が一〇%以上のことでございますが、家屋を対象として拡大をしておるところでございます。
そういうわけでございますが、もう十二月も半ばぐらいになりまして、もう一年になります。ですので、私ども自民、公明といたしましても、現地をずっと回ってまいりました、私もまた元旦に機会を得て行こうと思っておりますが、なおなおいろいろな点があることは委員御指摘のとおりです。私どもの地域の議員も一生懸命把握をいたしております。これに与党も野党もございませんので、そういうのを承りながら、被災者の方々が、一年たったけれども本当によくなった、よくなったねという言い方はいかぬですね、政府は分かってくれたんだねというふうに言ってくださる方が一人でも多いように、また委員の御意見も承りながらやってまいりたいと思います。
ありがとうございました。
○近藤(和)委員 私は、一月一日からずっと、与党も野党も関係ないという思いでやってきております。是非とも、各大臣の皆様も、できないことは分かった上で何とかしてくださいという質問に対しては、できない理由は延々と述べないでください。これは被災地の皆様からいただいた貴重な時間なんですから、そこは是非とも心していただきたいと思います。
そして、その上で、基本的機能を喪失していないということは、もう喪失していますからね。若い人だったら、いざとなったら逃げればいいかとなるかもしれないですけれども、例えば、皆さんの親の世代、あの家で住めますかということですよ。そこは、機能だ云々だということではなくて、本当の気持ちに寄り添っていただきたいと思います。
そして、仮設住宅については、よく聞かれることは、二年で追い出さないでくれと必ず言われるんですね。これは、仮設住宅は建設型の仮設とみなし型の仮設がございますよね。こちらについては、例えば災害公営住宅がまだできていないだとか家が直っていないというときには、二年で追い出されることはないですよね、総理。もう時間がないので答弁は求めませんが、今うなずいていただいたということで、これは皆さんテレビで見ていただいていますので、御安心してください。
今、石破総理が御安心してくださいと言いましたので、皆様御安心をしていただければと思います。
○安住委員長 近藤委員、議事録に残した方がいいから、ちゃんと答弁してもらった方がいいよ。
○近藤(和)委員 総理、それでは、御安心してくださいという一言をお願いいたします。
○安住委員長 答弁は強要しないでください。
○石破内閣総理大臣 出ていってくださいというのは、それは誤解でございます。二年を超えることになりましても、生活再建の状況などに応じまして、供与させていただいている期間の延長が必要であれば、国として柔軟に対応させていただきますので、どうか御安心をいただきたいと思っております。
○近藤(和)委員 ありがとうございます。
こういう分かり切った答えでも、あえて総理のお口でしゃべっていただくことは本当に大事なので、ありがとうございます。
そして、今回の補正予算の中で、豪雪対策ですね、越冬対策について、ちょっと足りないと思っていることがあります。
除雪車を更に用意するとか、崖崩れを更に防ぐということはしていただいていることは分かるんです。ただ、間違いなく孤立集落は生まれます、残念ながら、これは。ですから、例えば、避難所になりそうな場所だとか仮設住宅の集会所にしっかりと、籠城できるだけの備蓄。そして、携帯はつながらなくなる可能性がまた高いです。ですから、衛星の携帯ですとか、またスターリンクのようなネット環境のものを、少なくともこの冬は越せるように準備、これは補正の中でどうやら、準備、入っていないようなので、是非とも入れていただきたいと思います。
立憲の中で少し時間調整させていただいていますので、もう少しだけ。
○安住委員長 あなたの時間は過ぎているけれども、じゃ、後ろにずらして、ほかを削るということでいいですか。
○近藤(和)委員 はい。
○安住委員長 じゃ、どうぞ、続行してください。
○近藤(和)委員 そして、私の方からは、党派を超えてということで、幾つも法案を提出させていただこうと。そして、与党の皆様とも共同で動いていきたいということが幾つもございます。先ほどの被災者生活再建支援金の倍増法であったり、公明党の河西議員が言われました、災害救助法に福祉の観点を入れる。災害対策基本法のところにも私たちは入れていくべきではないかと。ここは協力していければと思いますし、法テラスのことがございますよね。法テラスも、九月からだけではなくて、実際には更にもう一年、今年だけではなくてもう一年、これも超党派でできるのではないかと思います。
そして、さらには、家が壊れて、自分の田んぼに家を造るということが、農地法や農振法で阻害されているという事実もあります。そして、さらには、工場を別のところに造ろうとしたときに、都市計画法で邪魔されているという現実もございます。
そして、解体をしていくときにも、所有権がはっきりしていない場合でも滅失登記でできるということもしていただきましたけれども、根本的な解決には至っていません。
こちらも坂井大臣が筆頭理事のときに私もいろいろ御相談させていただきましたが、まだまだ、今を乗り越えていくために必要なことがたくさんございますので、しっかりと力を合わせて、この復旧復興、能登のこれから、日本のこれから、力を合わせて私ども頑張っていきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
○安住委員長 この際、今井雅人君から関連質疑の申出があります。重徳君の持ち時間の範囲内でこれを許します。今井雅人君。
○今井委員 立憲民主党の今井雅人でございます。よろしくお願いします。
午前中の新藤委員の質疑の中で中小零細企業の価格転嫁の話がございましたけれども、これは非常に重要なことだと思うので、少し取り上げさせていただきます。
私、三年間浪人をしておりまして、選挙区をおかげさまで毎日回らせていただいたので、大変いい時間を過ごさせていただいたんですけれども。
いろいろな声をお伺いしましたが、その中の一つが実はこの問題でありまして、御存じのとおり、岐阜県も大きい企業がほとんどありませんので、下請の企業は本当に多いんですが。そういうところに行って、価格転嫁はちゃんとできていますかということを毎回お伺いしてきたんですけれども。
エネルギー代が上がったり、電気代が上がったり、あるいは資材が上がったり、こういうものは交渉すると、ある程度、差はありますけれども、ある程度見てもらえるというふうに皆さんおっしゃっていましたが、どうしても難しいのがやはり労務単価。労務単価を上げようと思うと、本当に元請の会社から渋い顔をされて、それだったらほかのところの取引先でやろうかなみたいなささやきを受けたりとか、そういうことがあって、本当に皆さん、従業員の給料を上げてあげたいのに上げられないと言って、非常に悲痛な思いを、たくさんのことを聞きました。
これはやはり、中小零細企業の給料を上げていかないと、大企業とまたどんどん差が開いていって、都市部と地方の格差もどんどん広がっていきますから、十二月三日の本会議のときに下請法の改正のことをおっしゃっておられましたけれども、とにかく、そういうことがちゃんと解決できるような、実効性のある下請法の改正をやっていただきたい。私もこれからアイデアをいろいろ出していきたいと思いますので、総理に、まずその点をしっかりやっていただきたいということで、お伺いします。
○石破内閣総理大臣 御指摘の下請法の改正につきましては、なるべく早く国会に提出をいたしたいと思っております。新たな商習慣として、サプライチェーン全体での価格転嫁、取引適正化を定着させてまいりたい。
私は、自民党で、建築板金振興議員連盟とか左官業振興議員連盟とか、そういうものをお世話をさせていただいているんですが、今委員がおっしゃるようなお話が山ほどあるんです。いやいや、ちゃんと払ってくださいなというふうに言うと、別に業者はおたくさんだけじゃないからというような話になっちゃうわけですね。そうすると、悪貨が良貨を駆逐するみたいな現象が起こりますので、業界全体にとって決していいことではございません。
これはやはり、全体として法律、そして、それがきちんとカバーできるように私ども立法いたしてまいりたいと思いますので、また御指摘をいただきたいと思います。
○今井委員 よろしくお願いします。
次に、金融所得税制の強化についてお伺いしたいと思います。
これは九月の二日だったと思いますけれども、テレビ番組に石破総理が当時出られまして、こういうことをおっしゃいました。首相に就任した場合の金融所得課税の強化について、実行したいというふうに述べられておられます。
ところが、十月一日に総理になられて、その僅か六日後の本会議のときに、石破総理は、金融所得課税につきましては、貯蓄から投資への流れを引き続き推進していくことが重要であり、現時点でその強化について具体的に検討することは、考えていませんとおっしゃっています。
実行したいとおっしゃっていたのが、考えていませんに百八十度変わってしまったんですけれども、どうしてですか。
○石破内閣総理大臣 九人も出ました総裁選挙でございますが、格差是正の観点から税負担の公平性を確保することは大事ですよねという思いは正直言って今も変わりません。格差というものがあっていいと私は思っていないし、お金持ちだけがどんどん有利になるというのは望ましい社会だと私は今も思いません。これが損なわれている状況であれば、金融所得課税の見直しを含めた検討が必要だというふうに申し上げました。
同時に、それでは、一般の投資家の方々が投資しやすい環境というのをつくっていかねばならない。それは、貯蓄から投資へということで、NISAもiDeCoも一緒の話でございます。
ですから、これは本当に気をつけなければいけないのは、あれはどうも投資というものに後ろ向きらしいと。それが石破ショックという言葉になって、がたんと下がるというようなこと。そこは、いやいや、実は真意はそうではなかったんだと幾ら言ってみたところで、そういうふうな印象を与えるということがあったとすれば、それは私の足らざるところであったと思っております。
ですから、公平性というものは担保したい、しかしながら、貯蓄から投資という流れにさお差すことをしてはならないということを申し上げております。
○今井委員 端的にお答えいただきたいんですけれども、格差是正という観点でいうと、これは御存じですよね、一億の壁というのがずっと前から話題になっていますけれども、一億円を超えると所得税の税率がすごく下がって、一番低いところに行くと一六%ぐらいになってしまうという状態になっている。
かつ、先日、自民党の小野寺議員が紹介されていましたけれども、この二十二年間で、人件費は伸びないけれども、配当が二十三兆円も伸びているわけです。この配当というのは、いわゆる金融所得課税で課税されるわけですから、一六パーしか課税されないわけですよ。
ですから、配当がどんどん増えていっているのにそこの課税が非常に低いという状態で来ているのが今の状態で、これが格差を拡大しているということで、我々はこれをやはり強化しなきゃいけないという考えなんですね。
でも一方、おっしゃるように、じゃ、投資を推進するために、これはやはり上げるべきではないという考えももちろんあるんです。
ですから、まずお伺いしたいのは、石破さんはどう考えていらっしゃるんですか。石破総理の考えを教えてください。
○石破内閣総理大臣 私自身そんな資産を持っておりませんもので、それは新聞報道で明らかなとおりでありますが、一億円の壁というのは自分のこととして意識をしたことがございません。
ただ、そこにおいて、そういう方々も日本の経済を支えておられるわけで、そこをどう考えるかというのは実はすごく難しいなというのを今回改めて思っておるところでございます。
ただ、私どもが守っていかねばならぬのは、老後の備えとして、少しずつ少しずつiDeCoにしてもNISAにしてもやっておられる方々をきちんと保護していく、そしてリスクを最小限にしていくということをよく考えたいと思っております。
○今井委員 済みません、質問に答えていただいていないんですよ。
金融所得課税の強化は必要だと思っているか、必要ないと思っているか、どちらですか。
○石破内閣総理大臣 私の立場でお答えすることは差し控えます、あえて。
○今井委員 総理にはお考えがないということですか。それは最終的にまとめるのは、全体でまとめるのかもしれませんけれども、総理がどう考えているかを私はお伺いしているんです。
例えば、防災庁をつくりたいと言って、そのまま政策を続けていらっしゃるじゃないですか。御自分の考えでやれるわけですよ。私の立場でお答えできませんというのは、そんなのおかしいです。
もう一回お伺いします。金融所得課税の強化は必要だと思われますか、必要ないと思われますか。
○石破内閣総理大臣 これは与党の中でもいろいろな議論がございます。
私は、必要なのは、税負担は公平でなければならないと思っています。これは定理のようなもので、税負担は公平であるべきだと思います。
では、金融所得課税についてはどうなのだということについて、公平であるべきだという意識はみんな共有しながらも、それが、全体の株価の流れがどうなっていくのか、日本経済に、日本の株に投資をしようという人たちのマインドをどう変えるのかという点も考えていかねばならぬことでございますので、総合的に考えていかねばなりません。自分の好き嫌いとか正義感とかいうことだけで物を言ってはならぬということを、よく承知をいたしておるところでございます。
○今井委員 好き嫌いとかそういうことを言っているんじゃないんです。政策として、我々は格差を是正するための政策だと思って言っているので、好き嫌いで言っているんじゃないんです。政策として、この金融所得課税が必要だと我々は思っています。
ですから、総理のお考えを聞いているんです。ちゃんと答えてくださいよ。だって、本会議のときには、現時点で検討することは考えていないとおっしゃっているじゃないですか、はっきり。ということは、必要ないと思っていらっしゃるということですか。ちゃんと答弁していらっしゃるじゃないですか。
○石破内閣総理大臣 何を言っても分かったと言っていただけないことはよく承知の上で申し上げておりますが、それは公平性を確保することは極めて重要だと思っております。ただ、そうした場合に日本経済というのがどうなっていくだろうかというのは、それはいいの悪いの問題ではなくて、どういう現象が起こるかということによく配意をしていかなければなりません。
金融所得課税の強化について現時点で検討することを考えていないと申し上げましたのは、もうやらないとかそんなことを申し上げているのではありません。今、補正予算の審議をいただいておって、これから先、日本の経済がどうなっていくかということをこうやって、ハングパーラメントで議論をしていただいているときに、このことについて私が断定的なことを申し上げることはしない。
大切なのは、日本の経済が決してデフレに戻らないということ。そして、デフレに戻るということは一体何が起こるんだということに、私は今一番配意をしなければならないと思っておるところでございます。
○今井委員 分かりません。
私が言っているのは、必要か必要じゃないかとお伺いしているので、現時点で必要じゃないと思っていらっしゃるならそれで結構ですし、そこをもう一度お伺いしたいんですよ。
これから、総裁にしても、総理にしても、いろいろなことを指示を出して、こういうことについてこういう方向で取りまとめをしてくれと頼むことはあるでしょう、当然。防災庁だって、総理肝煎りで、皆さんにそれをやってくださいといって指示をなさっているわけですから、自分の意思でやっていらっしゃるわけじゃないですか。だから、ここにも意思が必要なんですよ。意思があってしかるべきなんですよ。
だから、金融所得課税の強化が必要でないとおっしゃるなら、それはそれで一つの考えだし、必要だと思うなら、それは一つの考えですから、どちらですかと伺っているんです。
○石破内閣総理大臣 それは、経済は生き物だなぞということを、かつて銀行に勤めておられた委員に申し上げるつもりは全くございませんが、そういうものではないんですか。
防災庁をつくらなきゃいけないというのは、それは、私自身ずっとこの仕事をやってきて、これは絶対に要ると思っております。ですから、そのように申し上げてまいりました。そのほかの政策もそうでございます、自衛官に対するものも。
ですけれども、これは政府の立場にある者の一言一言でこれだけ相場が動いていくということ、それによって、ある意味で、言葉を選ばずあえて言えば、大損した人だっているわけであって、日本経済がどうなるかというのを考えたときに、それは絶対に必要だという防災庁とか、自衛官、自衛隊の改革とか、そういうものとは質を異にするというのは、経済にずっと携わってこられた委員が一番御案内のことかと存じます。
○今井委員 それじゃ、お伺いしますけれども、じゃ、総理は、自分でこういうことをしたいということにはランクがあるんですか。絶対やりたいことと、やれたらいいねというランクがあるということですよね。
私、ずっと疑問に思っているんですけれども、例えば、総裁選あるいは衆議院選挙のときにこうやってやりたいということをおっしゃったら、これは言ってみれば公約ですよね、公約じゃないですか。有権者の人は、そういうものを聞いて、じゃ、この人にしようと選んでいるわけで、判断材料に使っているわけじゃないですか。それで、選ばれた後に、いやいや、あれは言ってみただけで、そんなことやりませんよって、それは有権者に対する背信行為じゃないですか。いかがです。
○石破内閣総理大臣 ランクがあると私は思っておりません。どっちが上で、どっちが下かというようなことはございません。
ただ、これは、私も、世の中において一番大事なのは税負担の公平性だということに変わりはございません。税が公平でなければ誰も納税しようなんて思いませんので、税において大切なのは公平性だという思いは今も全く変わりません。
しかしながら、それによって、では、経済がどう動いていくか。それは、株のどれだけを外国人の方がお持ちであり、そしてまた、株の売買が本当に〇・何秒単位で行われており、そこにおいてアルゴリズムが入っておってということになりましたときに、そこにおいて正しいとか間違っているとか、それだけの価値判断で物事を決めてはいけないと思っております。
防災庁とは全く次元の異なるものであって、それはランクづけとは違うものでございます。
○今井委員 まだ、今、全然答えていただいていないんですよ。自分で発言したことは守らなくていいんですかということを言っている。守る必要はないんですか、必ずしも。少なくとも、私は、できるかどうかは別として、やろうとはしないといけないと思いますよ。やるように努力をするというのが、やはりあるべき姿じゃないんですか。
○石破内閣総理大臣 やらなくていいなんということを私は一言も言っておりません。
それは、やるべきことは全部一遍にできれば、それは誰も苦労しない。私どもはこうやって、私の足らざるところ大であって、我が党は議席を減らして、こういうハングパーラメントということでやっておるわけでございます。
また、私も自民党で三十数年やってまいりましたが、これほど当選者と次点の票差が少なかった総裁選挙というのは、石橋湛山以来だと思っている、くしくもね、だと思っています。
そして、我が党は、本当に自由で民主的な政党でありますので、総裁選挙で私がこれを掲げたので、みんなそれをやってくれなぞという党では全くございません。
やらねばならないということを申し上げました。例えば、いろいろなまた御批判がありましょうが、この地域における安全保障の仕組み、あるいは拡大抑止の在り方、そういうものについては今党内でかんかんがくがくの議論が始まっておるところでございます。そういう議論をスキップして、私が言ったからこれをやれなぞという、そんな政党では我が党はございません。
○今井委員 よく分かりました。だから、総理がやりたいとおっしゃったことは、そのままやれるかどうか分からないから信用しては駄目だということですね。よく分かりました。
次に、済みません、ちょっと統一教会の話をさせていただきたいと思うんですけれども。これは、総理もインタビューとかいろいろ出ておられる、文芸春秋に出ている写真というか記事なんですけれども。済みません、ちょっと個人を、私、攻撃するつもりじゃないんですが、やはりこういうことはちゃんと明らかにしておかなきゃいけないと思いますので、あえて出させていただいていますが。
ここの中に、統一教会の中部地区常任講師という方が作っておられる内部資料がここに出ております。ここに今、写真がありますけれども、根本幸典後援会何とかとありますね。この下のところに、もう本当に、統一教会の名前が書いてあるんです。何かといったら、後援会の発足式なんですよ、根本さんの後援会の発足式です。
ところが、資料の一番最後を見ていただくと、自民党の調査のときに、根本さんは統一教会とは関係があるというふうにお答えになっていないんです。関係がないとおっしゃっているんです。ところが、後援会までつくっておいて、つくっていただいておいて、覚えていませんなんてことはあり得ないですよね、絶対にあり得ないです。
さらに、この資料の中を見ると、本当に名前を出して申し訳ないんですけれども、事実を確認したいので、鈴木英敬さん、あるいは上田英俊さん、これは中部地区ですから中部の選挙区なんですけれども、そういう方々の写真も出ていて、推薦状を渡されたりとか、こういうふうになっているんです。お二人とも、統一教会とは関係がなかったというふうにおっしゃっているんですね。
総理はいつもおっしゃいますけれども、再調査はどうですかと伺うと、新しい事実が出てきたらその場合は再調査するとおっしゃっていました、いつもおっしゃっています。これはもう明らかに新しい事実ですね。
これは、自民党の調査というのがいかにいいかげんなのかということが、ひょっとしたら明らかになるかもしれない事案なんです。だから、私は、統一教会の問題というより自民党の調査の在り方、こうやって今までと違う事実が出てきたときには、やはりちゃんとこれはどういうことなのと本人に確認するなり調査が必要だと思うんですね。
事前通告で、僕はこの三人の方に確認してくださいというふうにお願いしましたが、これはどうだったでしょうか。済みません、通告で出していたんですけれども。
ちゃんと僕は質問のときに言いましたよ。内閣総務官室の質問取りをした方に言いましたよ、ちゃんと、本人に確認しておいてくださいと。
○石破内閣総理大臣 我が党といたしまして、こういう新しい事実が報道された場合、一々、報道の一つ一つについて、これは事実であるとかないとかいうことを断定する立場に私どもおりませんが。こういう報道がなされた場合に、当該議員が自らこれについてはどうだということを申し述べるというスタイルを今のところ我が党は取っておるところであって、本人が黙っているのに我が党として調査をするというようなことよりも、それぞれの議員が自らの責任において説明するということでございます。
○今井委員 自民党の中でやった調査と報道が違うのに、再調査しないんですか。載っていないんですよ、リストに。関係がなかったとおっしゃっている方が、例えばこういうものは真偽がどうか分かりませんけれども、写真ですよ。明らかに後援会をつくっていただいているという写真が出ているじゃないですか。これを調査しないと言ったら、一体自民党の調査というのは何なんですか。そんないいかげんなものなんですか。
裏金問題のときでも何でもそうですけれども、総理は新しい事実が出てこなければ調査しないとおっしゃっている。新しい事実が出たなら、ちゃんと調査してくださいよ。
○石破内閣総理大臣 それは総裁として申し上げますが、我が党として、新しい事実が明らかになった場合には、それぞれの議員の責任において説明するということで徹底をしてきておるところでございます。
○今井委員 ということは、総裁として、今私が名前を挙げた三人の方に、ちゃんと説明をするようにというふうに指示をされるということですね。
○石破内閣総理大臣 それは、この問題が明らかになって以来、そして我が党がこの団体とは一切関係を絶つということを定めまして以来、そのことの趣旨からして当然のことだと思いますが。
○今井委員 当然ということは、指示されるということですね。
○石破内閣総理大臣 時系列が違うのですよ。私どもとして、こういう団体とは一切関係を絶つというふうに決めたときから、仮にこういうことが明らかになった場合には、自らの責任において、あったならあった、なかったならなかったということを申し述べるのですということであって、そのたびごとに、あなたどうなんですかというようなシステムを取ってはおりません。それぞれの議員がそれぞれの責任において、だってこれは、今の御指摘は、恐らく日本最大の月刊誌なのであって、それに載ったということについて当該議員が説明していないとは私は全く思ってはおりません。
○今井委員 説明をするのは、自民党としては、そういう方がちゃんと説明するということをやるということだと今おっしゃいましたよね。ということは、この三人の方は説明をするということでよろしいんですね。それでよろしいですね。
じゃ、もう一度確認します。この三名の方は、やはり自民党のルールに従って自ら説明を果たすということでよろしいですか。
○石破内閣総理大臣 党務の全てについて私は承知をしておるわけではありませんが、私どもとして一切この団体とは関係を絶つと言っておる以上、そうするのは当然のことであって、仮にそういう報告もしていないとするならば、それは党として厳重注意をすべきものであるし、もし、それは私はしていると思いますが、仮になおしていないということでありとするならば、党としてきちんと説明してくださいねということを言うのは、我が党が有権者に対する信頼を確保する上においても大事なことだと思っております。
○今井委員 そうやってはっきり言っていただけるとありがたいです。納得しました。
それと、もう時間がありませんので、最後に、じゃ、政倫審の件なんですけれども。
先日は、うちの大西委員のところの質疑の中で、石破総理はこうおっしゃっているんですね。そこにおいて何が議論されたということは、それが公開されないとしても、それを主権者として、あるいは同僚議員として知るすべというのは当然あるというふうにおっしゃっています。
石破総理も主権者ですけれども、国民も当然主権者ですね。国民も当然知る権利があるはずなんですよ。
こういうことを、プライバシーだと先ほどおっしゃられましたけれども、そもそも公開しなきゃいけないものを公開していない。それは何に使ったんですかと聞くのに、どこにプライバシーがあるんですか。プライバシーなんかないじゃないですか。本来公開しなきゃいけなかったものの使い道を説明してくださいという政倫審なんですから、プライバシーに気を遣う必要は全くないわけです。
総理、最後に、私、提案なんですけれども、もちろん、政倫審に出る方は公開、非公開は自分で決められるわけですけれども、総理がそれを指示できないということ、それはそうなんですが、総裁として、次の選挙で公認するに当たっては、しっかり公の場できっちりと説明責任を果たす、そのために政倫審に出て公開で国民にしっかり伝える、それを条件とするということはできるはずですから、是非それをやっていただきたい。
○石破内閣総理大臣 そこはまた特別委員会等々で議論すべきことだと思いますが、委員は、政倫審の、昭和六十年十月十四日に議決されました、これは参議院ですが、政治倫理審査会規程というのを十分御存じの上で質問していらっしゃるんだと思います。この規程を読みますと、必ず全部公開しなきゃいかぬ、そういうことは書いてございません。そしてまた、なぜ非公開なのかということが本人の申出によってそうなるかということも、それなりに合理的な理由があることでございます。審査を了しましたらば、報告書が作成をされ、それが議長に報告をなされ、議院への要旨報告というものがなされる。それでもなお不十分な点があるかどうかは、実際に個々のケースによって違うのだというふうに考えておるところでございます。
参議院の公認をどうするかという御質問でございますが、それは、これから参議院の公認の在り方をどうするかということは党できちんと議論をすることでございます。これが、国民に対する説明責任をきちんと果たしているかどうかということが大切な基準となることは、当然のことでございます。
○安住委員長 申合せの時間が来ております。
○今井委員 はい。
総理、国民が見ていますから、しっかりやってください。
終わります。
○安住委員長 この際、奥野総一郎君から関連質疑の申出があります。重徳君の持ち時間の範囲内でこれを許します。奥野総一郎君。
○奥野委員 立憲民主党の奥野総一郎でございます。
最初に、政治と金の問題を触れたいと思いますが、この問題が出て、かれこれ一年になります。私も、この二月の予算委員会の集中審議で、当時の岸田総理に対して、調査報告、当時、全議員に聞き取り調査をした調査報告書が出たんですが、岸田総理は、真相究明をすると繰り返し繰り返し当時おっしゃっておられました。
この問題は、選挙結果を見ても分かるように、国民の怒りは深いんですね。きちんと納税をしていない、政治家がしていないかもしれない。自分たちは、一枚一枚領収書を徴収されて、きちんと真面目に納税しているのに、税を使う側、税の使い道を決める側の政治家が、ひょっとして脱税しているかもしれない。その疑惑を払拭し切れないところに、今回の選挙結果もあるし、問題があると思うんです。
スタートは安倍派でした。安倍派のキックバック問題でした。だから、安倍派の問題をきちんと究明する、解明する必要があると思うんです。二月の報告書でも、私は何度も再調査すべきだと申し上げましたけれども、真相は全く明らかになっていません。
という中で、裁判が結審をして、判決が出て、安倍派の会計責任者の松本淳一郎さんの発言が事実認定された。方向性として、還付、還流、キックバックを再開しようという決定が八月の安倍派の幹部会の中でなされ、決まった後に各議員に伝達した、こういう発言が事実だということが認定されたわけですが、これは先ほどから話が出ていますが、安倍派の幹部の皆さん、少なくとも、塩谷さんを除く皆さんとは発言の内容が一致していないわけです。
総理は、先日の当方の野田代表とのやり取りの中で、これは新たな事実じゃないから調査に及ばずと明確におっしゃっていたんですが、端的にお答えいただきたいんですが、今も再調査をする必要がない、自民党としては、自民党総裁としては再調査をする必要がない、こういうことでよろしいんでしょうか。
○石破内閣総理大臣 答弁に変更はございません。
○奥野委員 でも、これをきちんとしないと、なかなかこの問題は収まらないと思うんですよ。
党総裁たる総理がそういうふうにおっしゃる以上、やはりここは国会できちんと我々の責任において真相を究明していかなきゃいけないと思うんですね。
先日、当方の野田代表の方から松本淳一郎氏の参考人招致を求めました。その際に、安住委員長の方から、理事会で速やかに協議します、こういうお答えがございました。まさに、速やかに協議をして前に進んでいかなきゃいけないと思うんですが、委員長に質問してよろしいですか。
委員長に質問させていただきますが、現状、今どうなっているんでしょうか。皆さんの前でお答えいただきたいと思うんです。
○安住委員長 ちょっと速記を止めて。
〔速記中止〕
○安住委員長 速記を起こしてください。
私に対する質問だったので。
今、理事間で協議をしまして、今の経過を報告しますと、参考人の招致の後、速やかに協議に入っております。現時点では私に預からせていただいておりますけれども、この予算案のめどが立ち次第、速やかにまた理事会でこの案件については協議をするということになっております。
以上です。
○奥野委員 私も理事の一員でありますが、よろしくお取り計らいをお願いをいたします。しっかり真相究明を国会で図っていきたいと思います。
それでは、次の話題ですけれども、補正予算の話ですね。
これは再三総理に質問が飛んでいますが、選挙の公示の日、十月十五日の日に、補正予算については前回の補正を上回る大きな規模にしたい、こういうふうにおっしゃっています。十三兆円を上回る規模にというふうにおっしゃっていましたが、これは、皆さんが質問した結果、規模ありきではなくて、きちんと積算をした結果だ、必要施策を積み上げた結果だと何度も答弁をされていますが、この十月十五日の時点で積算がきちんとできていたんでしょうか。
○石破内閣総理大臣 全てきちんと積算を終わっていたわけではありません。
○奥野委員 これは結果から見ると、配付資料にもあるんですが、絶妙の数字ですよね。前回が十三・一兆円ぐらいかな、十三・二兆円ぐらいか、それが今回十三・九兆円ということで、前回よりは上回っているが、コロナ禍のときよりは少し少ないという、あたかも図ったかのような、総理が指示をしたかのような数字になっているわけであります。
これは、積算の結果、偶然そうなったということでよろしいんですね。
○石破内閣総理大臣 これは何度も同じ答弁をして誠に恐縮でございますが、まさしく、今デフレではない、しかし、デフレに戻る、そういうことを否定できない、それを完全に高付加価値型の経済に戻していくためには、岸田内閣で昨年補正予算を組みました、これを更に確定的なものにしていくためには、もちろん中身は違うんです、能登半島の地震もなかったし。だけれども、結果としてそれを上回る規模になったというのはそういうことでございます。
○奥野委員 今のことを分かりやすく言うと、規模ありきでやって、上回ることが大事だ、こういうふうにおっしゃっているというふうに理解をします。そうでないと、こんなにぴったりいくわけがないんですよ。
じゃ、何でぴったりいくかというと、からくりがありまして、これは会計検査院のペーパーなんですけれども、黄色い部分が令和四年度の補正の数字ですね。黄色いところの枠が、千二百八十五と八十五とあるんですが、これが令和四年の補正の項目です。歳出全体でいうと七千項目あるんですが、補正で追加された項目が、この二つを足して千三百七十項目なんですけれども、千三百七十項目のうち、補正で新たに追加された項目は八十五項目しかないんですよ。ということは、既存の項目にオンしているだけなんですね。千三百七十項目のうち千二百八十五項目、ほとんどが、九割以上が既存の項目に予算がオンしているだけなんですよ。だから、緊要性の問題が出ていますが、簡単にと言ってはいけないけれども、既存の項目にオンするだけですから、積算もできるし、簡単に組めてしまうんです。
各省庁は、夏の要求、九月から概算要求が始まりますが、その中で、毎年毎年、補正を見越して過大な要求をするわけですよ。過大な要求をしておいて、補正になると、余分なものを切り出して補正を編成する。だから、すぐに組めるわけですね。
総理がおっしゃった規模も分かるわけです。総理が、前回を上回る規模にと言えば、それに合わせて伸縮自在で切り出してきて組めてしまうんですよ。ということで、緊要性とはほど遠いということであります。
その証拠に、翌年度繰越率というのがありますが、補正予算は当該年度に原則執行する、執行が終わることが原則なんですが、じゃ、翌年度に繰り越したのはどれだけありますかというと、既存の項目にオンしたもの、千二百八十五項目については一五・一%、歳出全体で見ると一一%ですから、繰越率は高いんですね。さらに、八十五項目、新規については、半分が繰越しなんですね。
ということで、そもそも緊要性がないんじゃないか、規模ありきじゃないかというのがこの検査院の報告からも明らかであります。朝日新聞の社説の中でもこのようなことを言っていまして、最終的に、この予算のうち、分かっているだけでも六千億が不用だ、要らなかったということも出ているわけです。
総理にもう一回伺いますが、規模ありきでこういうことをやっていて、今まさに財政も厳しい中で、能登にお金が必要だと言っている中で、こういう無駄な支出を積み上げていく補正のやり方というのは改めるべきじゃないですか。いかがですか。
○石破内閣総理大臣 無駄なものを積み上げたつもりはございません。ですから、これが、補正予算が本当に政策目的あるいは国家経済の在り方にとってプラスになるかどうかを御審議いただくために、まさしくこの予算委員会が開かれているというふうに承知をいたしております。
だとするならば、委員各位におかれて、これは無駄だ、なぜならばこういうわけで無駄なのであるということをまた一つ一つ御指摘を賜るということも、私どもは、それは謹んで聞く、謹聴していかねばならないと思っております。
だから、全体的に大き過ぎるから無駄だ、そうではなくて、積み上げというふうに私どもは申し上げてまいりました。どこが無駄なのか、なぜ無駄なのかということをまた御教示をいただくことができれば幸いでございます。
○奥野委員 ですから、執行がちゃんとされないわけですよね。新規のものについては半分以上が翌年に繰り越されているし、全部悉皆で調べたわけじゃないけれども、この年でいえば、少なくとも六千億が使われないで返納されているわけです。
それで申し上げれば、総理肝煎りの地方創生交付金なんですが、昨年の補正予算でも、七百億ぐらいかな、補正に地方創生交付金が計上されていましたが、これは、去年の秋ですから、本来、今年の三月までに執行されていなきゃいけないんですが、現時点で配賦先が決まっているのは幾らのうち幾らでしょうか。
○北尾政府参考人 お答え申し上げます。
令和五年度補正予算については、現時点において、予算額七百三十五億円に対して、約六百十六億円を採択している状況でございます。
○奥野委員 昨日、百億以上、七百三十五億のうち六百十六億でしたか、ということは、百十九億が未執行なわけです。もう今年度は採択しないらしいんですよ。補正の性質からいって更に繰越しはできないので、ということは、百十九億が不用なんですよね。七百三十億のうち百十九億、一五%、まさにこの数字と近いんですが、一五%が不用なんですよね。総理肝煎りのこの地方創生交付金は二割近くが、去年の補正のものは不用、返納になるわけです。これはやはり財政規律が緩んでいる、緊要性がないという証拠じゃないですか。
ということで、また総理にこれは伺うんですが、再び規模ありきじゃないかと思われるのがこの地方創生なんですけれども、総理は再三、地方創生交付金を二倍にする、こうおっしゃっていますが、ここに書いてあるように、新しい地方創生交付金を倍増しつつ、前倒しで措置をいたしますと本会議で答弁されていますが、これは何で倍増なんですか。これは規模ありきじゃないですかね。根拠はありますか。
○伊東国務大臣 ただいまお話しのとおり、地方創生の交付金につきまして、これまでも、石破総理が初代の地方創生担当大臣になって以来ちょうど十年であります、数多くの実績も残されているところでありまして、この交付金を用いて全国各地で様々な取組が行われており、例を挙げますと、ドローンを活用した買物支援サービス……(奥野委員「違う、違う。もういいです」と呼ぶ)今、中身を少しお話ししてから……
○安住委員長 ちょっと簡潔に答弁してください。
○伊東国務大臣 はい。
高齢者向けオンデマンド乗り合いタクシー、あるいは移動診療車を活用したオンライン診療、さらにはまた自動運転バスを活用した地域交通など、私も実際に見てまいりましたけれども、いろいろな形で、地域に喜ばれる事例で活用されている例がたくさんありました。今年はこれを更に倍増させたいということであります。
○奥野委員 そういうものが本当に緊要性があるのか、今回の補正について言えば、あるのかという話なんですが、これは、地方創生十年の取組と今後の推進の方向という今年の六月にできたものなんですが、成果についてはこの水色の部分、課題についてはこの緑色の枠のところですね。課題が山のようにあって、これは一つ一つやると時間がかかるので、ぱっと見ていったら分かるんですが、成果が少なくて課題が山積だというのは、これを見ても明らかなんですよ。
総理は、先日の答弁の中で、これまでの成果と反省の検証を進め、年末に向け基本的な考え方を取りまとめ、その後十年間集中的に取り組む基本構想を策定する、これは地方創生についてこうおっしゃっていますが、恐らく、反省に基づいてというんですが、反省していないのに、今回、補正予算にまた一千億入れるというのはどういうことですか、総理。
○石破内閣総理大臣 それは、私は地方創生大臣を二年務めました。その後もずっと全国も回ってまいりました。恐らく、市町村でいえば四百七、八十は回ったと思っております。そこにおいて、こうすればよかった、ああすればよかったという反省は実はたくさんございますし、一番の反省は、やはりキー・パフォーマンス・インディケーターというんですかね、何を達成しなきゃいかぬのかという数字が明確でなかったのと、それがあってほしいなという願望にとどまって、PDCAというものがきちんと機能として内在されていなかったので、従来の政策の域を出なかったということが最大の反省でございます。あれをやりたい、これをやりたいというのはございました。
倍増というのは、地方創生のプロジェクトが始まりましたときに、正直言って、これだと、一千億でしたから、千七百十八市町村、かつて竹下内閣でふるさと創生というのをやったときに一億円、あのときは市町村の規模が三倍ぐらいありましたから、数が。そのときに一億円というのを、私は当時当選一回生だったかな、よく覚えております。そのときと比べて少ないねという感じを正直言って持ちました。
ただ、多いとか少ないとかいうことじゃなくて、本当に今度はきちんと活用してKPIが達成されないとこの国が終わるよ、そういう危機感を持って今回の予算を組んでおるものでございます。
○奥野委員 だけれども、去年の補正だって使い残しているんですよ。そんなに需要があると思えないし、きちんと反省しないとまた無駄に終わりますよ。
KPIはそのとおりなんだけれども、ミクロの施策で幾らKPIをやったって、マクロのところで成果は出ていないわけですね。東京一極集中も止まらなければ地方の人口も増えないわけだから、目的を達成できていないということはまさに合成の誤謬、幾ら頑張ったって、細かいお金を積み上げたって、ばらまいているだけで効果はないんですよ。そこをしっかり反省いただきたいので。もうこれ以上聞きませんが。
私は、こんな手の込んだことをしなくても、もっと地方交付税をばんばん増やして、地方の自主性に任せてやらせればいいと思うんですよ、きちんと。そんなにいろいろな交付金をつくったってしようがないと思うんですが。
という中で、一つ、地方創生臨時交付金、重点交付金ともいいますが、について伺いたいんですが、これは執行率も高い。というのは、きちんと人口とか一定の要件で配賦を決めて配賦をする。例えば給食の無償化とか、メニューに載っているものを、手を挙げるとお金が下りてくる、こういう仕組みなんですが、これは、しかし、ぱっと思うと、地方交付税と余り変わらないんじゃないかと思うんです。
下のところ、特に推奨事業メニューですけれども、人口、物価上昇率、財政力、財政力もあるわけです、等を基礎として算定して各自治体に割り振っていくわけですけれども、これは効果が高い。後ほど言いますが、給食の無償化なんかにも使われて、私はこれの仕組み自体は悪いものとは思っていませんが、ただ、地方交付税でもいいんじゃないかと思うんですが、どう違うんでしたか。
○松家政府参考人 お答えいたします。
御指摘の重点支援地方交付金、これは物価高騰対応の重点支援地方創生臨時交付金でございますけれども、地方公共団体がエネルギーや食料価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じて地方創生を図ることを目的として、地域の実情に応じてきめ細かに必要な事業を実施できるよう臨時に措置しているものでございます。
このため、使途の定めのない一般財源であり、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための地方交付税交付金とは制度の趣旨、目的が異なるものと認識してございます。
○奥野委員 物価対策というひもがついているというんですが、交付税だって、算定の中で物価対策とかは入っているわけですよね。物価対策というのは緊要性がありますから、確かに、ハイパーインフレで急に二〇%になりましたとかというと緊要性はあると思うんですけれども、毎年数%でも、この流れが、まさに総理も認めておられましたけれども、毎年毎年なだらかに物価が上がっていくというわけだから、当初予算でこういうものも組み込んでやっても私はいいと思うんですよね。
そこで、自治財政局かな、伺いたいんですが、交付税とは違うと言うんだけれども、交付税というのはそもそもどういうものかと簡単に御説明いただいた上で、この臨時交付金と交付税を一本化したらいいと思うんですが、あるいは、もうちょっと言うと、先ほどの地方創生交付金も含めて、全部地方交付税という形で当初予算で配賦したらいいと思うのですが、いかがでしょうか。
○大沢政府参考人 お答えいたします。
地方交付税は、法律上、使途の定めのない一般財源でございまして、使途を限定せずに地方が地域の実情に応じた施策を講じることができるように財源を確保しているものでございます。
委員の御指摘がございました、二つの交付金の御指摘がございましたけれども、こちらについては、先ほど答弁がありましたように、あくまでも国庫支出金ということで使途が限定をされております。その中で、地方団体に、その限定された事業に取り組んでいただくように、その目的で交付されているものでございまして、その役割、目的が異なるものでございますから、このような形で予算計上をしているものと承知しております。
○奥野委員 今お答えになりませんでしたが、交付税の予算策定のときに、積算根拠があって、それぞれの行政需要を積み上げていくわけですよ。その中には、こういった物価対策とかも当然含まれていますよね。
というわけで、自由度がより大きいのは交付税と思っていただければいいんですが、地方創生の観点から見たときに、分権の観点から見て、やはりできるだけ自由度を持たせて使ってもらうのがいいと思うんですね。国が縛ってやるよりはいいと思う。一回、そのKPIをきちんとして、国がコントロールする形でやっていてうまくいっていないんですから、これは明らかに失敗と認めた上で、私は、より分権を進めて、交付税によりシフトしていくべきだと思います。
局長に伺いたいんだけれども、これは長年の懸案で、法定税率は所得税の三三%、酒税の五〇%と決まっていますが、この法定率を引き上げるという議論がありますが、それをやったらいいと思うんですが、いかがですかね。
○大沢政府参考人 お答え申し上げます。
地方財政の健全な運営のためには、本来的には、交付税率の引上げにより地方交付税総額を安定的に確保することが望ましいと考えております。
交付税率の引上げについては、令和七年度の概算要求におきましても、巨額の財源不足が見込まれることから、事項要求をさせていただいております。
現在のところ、国、地方共に厳しい財政状況にあるため、交付税率の引上げは容易ではございませんけれども、今後も粘り強く主張し、地方交付税総額を安定的に確保できるよう、政府部内で十分に議論してまいります。
○奥野委員 総理、こういうのをやってほしいんですよね。使われない補正、交付金とかじゃなくて、きちんと政策論でやりましょうよ。それが私は石破総理だと思いますよ。
最後にもう一点、給食費の問題。
これは石破さんの公約ですけれども、いっぱいいいことが書いてあるんですよ。いっぱいいいことがある、細かくて読み切れないくらい書いてあるんだけれども、給食費の無償化もちゃんと書いてあったりしてですね。
文科大臣に伺いたいんですが、昨日、総理が答弁で、年内に課題、これは給食費無償化の実現に向けた調査ですから、その課題の整理を年内に終えると言っておられるわけです。文科省としてはどうなんですかね。これは、今、地方創生臨時交付金だから補正なんですよ。補正でやった場合に、給食費のパネルを御覧いただくと、完全無償化の団体が五百四十七、それから臨時交付金を使っているのが二百三十三あるんですが、これは、補正だといつ取りやめになるか分からないので、文科省としてきちんと当初予算で要求をして、給食費の無償化を実現していくべきだと思いますが、どうでしょうか。
時間がないのでまとめて聞きますが、もう一つは、このときによく公平性の問題というのが出ますが、行政需要があって、これだけ多く、五百以上の、三分の一近い団体の中で無償化が行われているわけです、逆に、無償化がないところは不公平じゃないですか。だから、地方創生というなら、全国あまねくきちんと給食費の無償化をすべき、財政力のある東京とか都市部だけじゃなくて、全国あまねくきちんと措置すべきだと思いますが、大臣として、給食費無償化、しっかり来年度予算できちんと取り組むかどうか、実現に向けて取り組むかどうかを伺いたいと思います。
○あべ国務大臣 委員にお答えさせていただきます。
やはり学校給食費に係る保護者負担の軽減はまさに喫緊の課題でございまして、補正予算について、今回の重点支援地方交付金で〇・六兆円でございます。
そうした中で、地域の実情というのがございまして、先ほどおっしゃってくださった、実は、地域によっては、実施、既に給食の無償化をしているところとしていないところがございます。
そういう中にありまして、経済困窮世帯におきましては基本的に無償という形で、児童生徒の約一四%が適用されているところでございまして、これは、各自治体によって御判断されるというふうに私どもは考えておりまして、地域の実情に応じていくということが重要であるということ。
さらには、この無償化を全てということのお話でございますが、全体の三割、先ほど委員がおっしゃってくだすった五百四十七自治体におきまして、小学校段階、中学校段階の全員を対象にしているところもある中にございまして、実は、給食を未実施としているところ、さらには喫食しない児童生徒への恩恵が及ばない、実はこの対象者は六十一万人ございまして、そういうことも考えたときに、低所得世帯の児童生徒に対しては既に無償化されているという問題と、給食費に係る就学援助に関する、いわゆる三位一体改革で、先ほどおっしゃってくださった税源移譲と一般財源化、国と地方の役割分担をどうしていくか、さらには、少子化対策としてこの政策の効果がいかにあるかということも含めて、この在り方を、いわゆる法制面でしっかり、年末を目途に課題を整理してまいります。
○安住委員長 時間が過ぎています。
○奥野委員 本当に残念ですね。やらない理屈を並べ立てられて、私はがっかりしました。総理、しっかり取り組んでください。
以上です。
○安住委員長 この際、大島敦君から関連質疑の申出があります。重徳君の持ち時間の範囲内でこれを許します。大島敦君。
○大島委員 衆議院議員の大島です。
私が会社に入ったときの挨拶が、御安全にという挨拶でした、鉄鋼会社。今でも日本の鉄鋼会社、重工業メーカーでは使われている言葉です。やはり日本の産業は物づくりでもっていると考えております。今回の議論を通じて、スチュワードシップ・コードあるいはコーポレートガバナンス・コードを変えられるんじゃないかなと思ったの、日本の資本主義を規定しているのはこの二つですから。投資家に対するスチュワードシップ・コード、あるいは企業のコーポレートガバナンス・コード。
それで、金融担当大臣に伺いたいんですけれども、こういう感覚を持ったかどうかを教えてください。
○加藤国務大臣 転嫁に対しては、これまでも様々な施策を講じている。その中で、今委員からスチュワードシップ・コード等についてはお話がありました。
まず、コーポレートガバナンス・コードにおいては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出に向けて、上場会社は、株主のみならず、取引先や顧客を含む多様なステークホルダーとの適切な協働に努めるべきことが明記されているわけであります。
ただ、こうした原則は示しながら、一方で、このコードというのは、具体的な行動は各企業の自律的な創意工夫に委ねるプリンシプルベースの手法を採用していることは御承知のとおりでありますので、特定の企業行動をこのコードの下で義務づけるというのは趣旨にはなじまないと思います。
他方で、こうした取組が進むようには、企業に対して、自律的な取組が進むように、金融担当、金融庁としても取組はしていきたいと思います。
○大島委員 答弁は手短にお願いします。
なぜこれを考えたかというと、大きなギアチェンジができるのではないかなと思ったの。
これまでの経済政策とは違って、この二つ、コーポレートガバナンス・コード、例えば私たちが持っている年金の資産は、全上場株式総額の大体七%強ぐらいかな、あと日銀が持っているのも七%の後半ですから、二つ足すと一五%を国民が持っているんです。上場企業の一五%。ここの株式について全くノーケアでいいかなと思うの。与党も野党も、賃金上げろ、下請価格しっかりやれ。もう八年間やっているんですよ、ここで。それでも一向に改善していない。この現状を変えるにはどうした方がいいかなというのがシステムの議論だと思っているの。個々個別の議論は、それは個々個別に役所が対応すればいい。私たちは、法律というツールを使いながら、システムとしてそれを解決する、そういう時代に入ってきたのかなと思っているんです。
ですから、日経新聞、最近の論調は変わっています。自社株買いについて否定的な意見の識者の発言が出ているんです、自社株買いに対して。古くは、二〇一六年だったかな、ハーバード・ビジネス・レビューに載った論文があって、そのときも自社株買いは、賃金は米国でも上げないし、設備投資にも向かわないしという否定的な議論。日経新聞が書くというのは、そろそろそういう時代に入ってきたのかなと思うものですから。
例えば、金融担当大臣に検討をお願いしたいのは、この二つの有識者会議のメンバーを替えるということも、総理としては必要かもしれないですよ、これからは。そうすると、日本の資本主義の在り方が変わっていきますから。その点についてうなずいていらっしゃるから、一言お願いします。
○石破内閣総理大臣 うなずくと御指名を賜りまして、ありがとうございます。
日経が書いたから論調が変わるか、世の中が変わるかどうかは、あそこのいろいろなコラムを読みながら思うことはございますが。
自社株買いについて制限することというのは、各企業が個別事情などを考慮して利益を柔軟に分配する余地を狭めちゃうんじゃないかなという思いも一方においてあるわけですね。自社株買いは、株主への利益還元とか株式の価値向上のため、事業環境や事業計画などを踏まえて自律的判断において行われるんだけれども、自社株買いについて制限することは慎重な検討も必要だとは思っているのですが、このことについて、私も問題意識は十数年前から持っておるところでございます。
こういう立場でございますので軽々なことは申し上げませんが、自社株買いというものについての多方面からの検討というものは当然活発に行われるべきものであって、私から断定的なことを申し上げるつもりは全くございません。
○大島委員 それで、まずは年金の壁から入りたいと思います。
まず、一番のパネルを、杉村さん、持っていただけると思います。
今、政府の中で議論されていることは、たまたまこの場でも皆さんは議論しています。この図を見ていただくと、百六万円の壁、五十一人以上の会社で、被扶養者の年収、所得が百六万円を超えると、事業主にも十五万円、本人は十五万円、それぞれ社会保険を負担しなければいけないということです。
今、厚生労働省で議論している年金部会の議論は、この要件を外そうと、まずは五十一人という要件を外そうというのが一つ。もう一つが、年収要件も外そうと。今、百三十万円の壁、これは五十人以下の会社。それについても全部、二十時間という縛りの中で、扶養なのか被扶養なのかを決めるという議論が行われていると思うんですけれども。
ここの議論で一番大切なのは、五十一人以上の会社のイメージだと。石破総理の選挙区あるいは武藤経産大臣の選挙区、大島の選挙区もそうですけれども、国立国会図書館で企業データを見ると、五十一人以上の会社は一〇%ぐらいなんです。ほぼ九割が五十人以下の会社なの。五十人でも、じゃ、十人、二十人、三十人の会社のイメージを持てるかどうかなの。
私、一回転職をして、生命保険会社で、新規顧客の開拓でずっと中小・小規模企業を営業していましたから、鉄鋼会社のときには想定できなかった感じを持っている。何千社という会社を訪問して、経営者の心を聞きながら営業してきたので、経営者の本当の気持ちは、従業員のためを思いたいと思っても、御自身の会社を継続させるのが経営者の最大の関心事です。ここをよく分かっていないと経済政策は当たらないと思っているの。今日は深くは述べません。
もう一つの風景は、日本の今の上場企業の役員の皆さんが二十代、三十代のとき経験した心象風景に迫らないと経済対策は当たらないんです、ここは。そこをしっかりと改善することがこの場の議論だなと思っていまして。
ですから、ここの、要は百六万円の壁を、来年の通常国会で、厚生労働省の年金部会としては議論しながら、私たちも考え方は分かります。私のところにも、実はこういう意見もあるんですよ。市役所に勤めていて、御自身は国民年金と国民健康保険なので、だけれども、厚生年金にあるいは社会保険に入りたいんだけれども、市役所の方が十九時間以内に抑えられているから入れないという意見もあるんです。
様々な意見があって私たちの国は成り立っていて、私は、この話を最初に聞いたときに、五十人以下、痛いなと思いましたよ。
私、時々私の地元の中小・小規模企業にアンケート調査を出しているの。今回出したアンケート調査の枚数が全部で四千三百四十社。それで、この束は、ここ数年廃業したんですよ、返ってこなかった。こういう現実、皆さんは分かりながら議論しないといけないなと思っています。様々な声を聞きながら。
それで、経産大臣に伺いたいんですけれども、今回、経産省はなかなかいいアンケート調査をしていただいて、価格転嫁が進んでいるかどうかについてのアンケート調査をしていただいたんですけれども、そのアンケートの手順だけ、一分以内で説明してください。
○武藤国務大臣 大島委員のアンケートのことについてのお問合せに、質問にお答えさせていただきます。
中小企業庁が実施しております価格交渉促進月間におけるアンケート調査ですが、三十万社の中小企業に対してはがきを郵送し、回答をいただいた方、はがき内部のQRコードを読み取っていただきながら、インターネット上でアンケートに御回答いただいております。
以上です。
○大島委員 このインターネットのQRというのがなかなかくせ者でして、本当の意見が入ってくるかどうかをまず考えてください。インターネットで、QRコードをスマホで読み取ってそれに対して答えられる人は、意外と若い人かもしれない、柔軟な人かもしれない。でも、町の床屋さんとかあるいは飲食店の方とか、本当の中小・小規模企業、本当の零細の方たちがそういうアンケートに答えていないと思っていますよ。
切実な声をこの一枚一枚のはがきを見ながら自分は聞いているんです。大きな会社に勤めていたときと保険のセールスをやったときの気持ちが全然違うから。そこを是非分かっていただきたい。
見ていただくと、下請構造が一次、二次、三次、四次のように下がっていくと、価格転嫁は進んでいないということは明確です。価格転嫁は進んでいない。まだこの下にあるということなの、価格転嫁が進んでいないところが。そこの気持ちをしっかり分かって議論するのが僕はこの場だと思っていまして。
ですから、どうやって価格転嫁を進めていくかなと思ったときに、これは国土交通省かもしれないし、あるいは経産省かもしれないんですけれども、今回皆さんのところで出していただいた物流総合効率化法というのがあって、これはなかなかよくできている法律で、これについて、また短時間で御説明していただけると助かります。
○武藤国務大臣 今の物流統括管理者の制度でございます。
令和八年度より施行される予定の改正物流効率化法でございますが、一定規模以上の荷主に対して経営者層から物流統括管理者を選任することを義務づけております。物流統括管理者の選任が義務づけられる企業につきましては、日本全体の貨物重量の半分程度をカバーするとの考え方の下で、約三千二百社の荷主が該当することになると想定をしております。
これら大手荷主において物流統括管理者が選任されることで、物流の負荷軽減や効率化に向けた各社の取組が着実に進むことを期待しております。
○大島委員 ありがとうございます。
この物流総合効率化法、国土交通省が所管の法律ですけれども、経産省が今、答弁をしていただきました。
これは一定の将来像がありますよね、物流のフィジカルインターネット。私、将来の物流というのは、何十万個の大きいものも小さいものも全て量子コンピューターで管理をしながら最適化を図るというのが多分五年後から十年後の物流だと思っていまして、そのソフトウェア会社にも訪問をさせていただいて、様々意見を交換させていただきました。カナダのD―Waveの量子コンピューターを使いながら最適化を図っている。こういう会社のシステムがしっかりとすれば、日本は世界でまたオーナーになれるかなと思っています。
この法律は、大臣御承知のとおり、エネルギーの使用の合理化に関する法律をベースにしながら、もっと前は戦争直後の傾斜配分。これは、企業合理化法、全部、条文を読みました、そこから起因している流れなの。経産省の二つの流れ、規制の流れと自由にする流れがあって、今の時代はこういう流れかもしれない。
農水大臣に伺います。農水省としても来年出す法律があるはずです。これは食品に関して同じようなスキームを適用していると思うんだけれども、その点について、これも手短に御説明ください。
○江藤国務大臣 なかなかこの件につきましては、最終的には生産、流通、加工、そして消費者の方、最終的に消費者の方の御理解をいただかなきゃいけないので、同じようなスキームを横に展開するのは難しいですが。しかし、フランスのエガリム法も、できましたけれども、なかなか成果が上がっておりません。しかし、このことには挑戦しなきゃいけないと思っておりますので、来年の通常国会の提出に向けて鋭意作業中でございます。
○大島委員 下請法の改正案ではないと思うの。私、今の日本の産業構造の系列、下請を変えることが日本の産業構造自身を変えることだと思っているの。アメリカは下請はないです。全ての企業はオーディションです、一年ごとの。一年ごとにオーディションを受けて採用された会社が、部品メーカーとしてスペースXに納入していくような。日本の下請構造は、今回、こういう狭い領域ではなくて、日本の産業自身を変えるという観点で、大臣、議論した方がいいと思うの。
ですから、私は、せっかく大臣から答弁を受けていただいたので、今回の物流総合効率化法の中で、チーフ・ロジスティクス・オフィサーですか、会社の中に物流担当役員を置けと書いてあって、これは省エネ法でも同じですから。そこに、このCLOにプラス、物流をしっかり見ろという役目を負わせたら済むのではないのかなと思うの。だって、三千二百社で五〇%の日本の物流を全部管理しているわけですから。だったら、ここに同じような機能を与えて、公取委員長、来ているかしら。公取委員長、今回の下請価格の人件費のここの指針はなかなかいいので、この点についてまた手短に答弁をお願いします。
○古谷政府特別補佐人 御指摘の指針でございますけれども、労務費の転嫁に関しまして、発注者と受注者それぞれが取るべき行動として十二項目の指針を示しております。
例えば発注者として取るべき方策として、経営トップがしっかり関与していただくこと、それから発注者側から定期的な協議を実施していただくこと、それから労務費の転嫁について説明を求める場合には公表資料に基づくこと、さらにサプライチェーン全体での適切な価格転嫁ということに配慮をして価格交渉に発注者には当たっていただきたい、そういったことを求めております。
また、受注者側にも商工会議所などの相談窓口に相談するなどして積極的に情報を収集した上で交渉に臨んでいただきたいといったことを求めておりまして、こうした行動指針に沿わない行為をすることによって公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会におきまして独占禁止法や下請法に基づいて厳正に対処することがあるということを明らかにさせていただいております。
○大島委員 この指針は私が読んでもなかなかよくまとまっています。これを法制化したら済むかもしれない。
委員長に伺いたいんですけれども、この指針の浸透度合いについての感想をお聞かせください。いろいろな会社が知っているかどうかについてお知らせください。
○古谷政府特別補佐人 現在、この指針につきまして周知徹底を図りますとともに、特別調査というのを実施しております。現在取りまとめ中で、近く公表させていただきたいと思いますが、五月時点の調査でありまして、昨年十一月にこれを策定いたしまして、五月時点ですので、まだ浸透度合いは半数程度にとどまっておりますけれども。知っている人の方が知らない人よりも価格転嫁の受入れが進んでいるということは確認できると思います。まだ周知途上にあるというふうに認識しております。
○大島委員 この間タクシーに乗りましたら、タクシーの助手席の後ろにモニターがあって、価格転嫁していますかと公正取引委員会の広告が流れまして、何か涙ぐましい努力をされていると思いました。
これは、パートナーシップ宣言もあってこの指針があるけれども、全然浸透していないではないですか。八年間、政府はやっているんですよ。上場企業の経営者の皆さんにしっかり分かってもらう必要があると思うの。
私も、元請の購買担当でしたら慎重になりますよね。この間、地元の会社で、こういう資料を出してくれと、取ったの。十人ぐらいの物づくりの会社かな。あと、四十人を超えた物づくりの会社で、こういうものは出せないというんですよ、難しくて。だって、一・五円のこういう小さな部品に、材料費、加工費、外注加工費、購入部品費、製造原価、一般管理費、見積単価まで出せというんですよ。そして、下の方にその会社の判こがあって、まずは担当が判こを押して、係長が判こを押して、課長が判こを押して、部長が判こを押す。これが今の要は一次、二次、三次の下請です。
親会社はできています。地元で私がある会社にどうですかと聞いたら、三菱重工さん、日立さんはしっかり下請価格の転嫁に応じていただいている。ただ、それが一次、二次、三次、四次、ずっと下までいくと応じてくれないと。それはそうですよね、サラリーマンですから。大島だって購買担当でしたら、勝手に値上げしたら部長に呼ばれ、部長は社長に呼ばれ、社長は親会社に呼ばれ、何をやっているんだということで終わるわけ。
ですから、武藤さんに、あるいは石破大臣にお願いしたいのは、下請法の改正ではなくて、今回の経産省が提案しているスキームをしっかりやってみた方が話は早いと思うの。
武藤さんの、経産大臣の御地元はメーカーが多いですよね。リーディングメーカーが非常に多くて、産業構造も極めて重層的で、多分、繊維、あるいは織機もあったかな、あと自動車産業があったりして、よく分かっていると思うので、その点について、答えられないとは思うけれども、前向きな答弁をできればお願いしたい。
○武藤国務大臣 今、一分以内でと言われなかったので、ちょっとだけお時間をいただいて。
大島先生の本当に御指摘のとおりで、サプライチェーン全体での価格転嫁を進めることは極めて重要だと私も認識しております。
下請法というのは直接の契約関係がある発注者、受注者について規制をしておりますけれども、下請法を補完するため、例えば、直接の取引先に加えて、その先を含めた全体での取引適正化を宣言、公表するパートナーシップ、さっきおっしゃっていただきましたけれども、推進しております。一つ先の取引先も含めてサプライチェーンの、これが大事なところで、多段階での事業者が連携した取組を支援する仕組みにつきましても今後検討してまいりたいと思っています。
サプライチェーンの取引構造は業種によって様々でありまして、本当に、それぞれの業界ごとの自主行動計画を実行、改善するなど、きめ細かに取引適正化を図っていきたいと思います。
大島先生が言うのもごもっともだと思いますので、またよろしく御指導ください。
○大島委員 私たちはシステムの議論をしているの。八年間やっていても全然価格転嫁していないじゃないですか。システムがおかしいと思う。法体系がそろっていないから価格転嫁が起きていないの。
ですから、CLOにプラス、その会社が持っている下請構造について全部把握させて、総理なり大臣が報告せよと言ったら報告する仕組み、あるいは、しっかりとこの公正取引委員会が作った指針を読んでいるかと言ったら、しっかり読んでいるという連絡が来る、そういうことが必要だと思います。
最後に、私、地元の机の上には、この中小企業憲章を置いているの。これは二〇一〇年の六月十八日の閣議決定です。私たちが政権を取っていたときの閣議決定なんですけれども。
私、中小企業憲章を変える時期に来ているかなとは思っているの。それも法制化したいなと思うの。国民運動として、中小企業の皆さんに、これまでの中小下請企業の構造から、将来的には一億人の人口に二〇五〇年はなるものですから、それに向けて、日本の中小・小規模企業がどのように支援をされ、そして、自律的に中小・小規模企業が幅広い裾野をつくって、様々な産業の物づくりの部品の対応ができるような、そういう指針に変えたいなと思っているの。
是非、石破総理、この中小企業憲章、そして、中小・小規模企業の下請構造がしっかりと整って下請価格の転嫁ができない限りは、冒頭申し上げました、厚生労働省がこれから提出しようとしている規模要件もあるいは年収要件も外して二十時間だけの要件にするというのは、なかなか大変だと思うの。
その悲鳴が、その声が聞こえているので、是非、まずは中小・小規模企業の価格転嫁を全部成し遂げてから、私も社会保険制度については守りたい立場なんです、国民皆保険はすばらしいですから。国民皆保険は日本だけですから、保険証一枚あれば、がんセンターで高度治療が受けられる国は。
そのためにも、幅広い方たちに被保険者になっていただくためにも、是非、下請価格の転嫁対策をシステムとして解決していただきたいことを石破総理にお願いしたいんですけれども、最後に答弁をお願いします。
○石破内閣総理大臣 久しぶりに大島議員の議論を拝聴して、とても同学年とは思えないと思ったところでありますが。
おっしゃるように、大企業と中小企業、私も銀行にいて、一日二百軒ぐらいかな、新規のお客様を回って、理念が全然違うねということをよく承知をいたしております。時代が全く変わってまいりましたので、価格の転嫁ができないメカニズムというのは一体何なんだろうかということはよく究明をしないと、法律を変えれば何とかなるというものではないというのは、今の御議論を聞きながら承知をいたしたところでございました。
下請法につきましては、また委員の御見解を聞きながら、私どもとしても議論を深めてまいりたいと思いますが、中小企業憲章を法律にするかどうかということも含めて検討をさせていただきたいと思います。
これは我が党の中にも議論はございますし、公明党さんからもこういうものの必要性というのは指摘を受けておるところでございます。
これこそ与党、野党関係ございませんので、どうすれば本当にきちんと価格の転嫁ができるか、中小企業の生産性というのをいかに上げ、賃上げを実行するか等々、また今後も御教示を賜りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○大島委員 終わります。
○安住委員長 この際、本庄知史君から関連質疑の申出があります。重徳君の持ち時間の範囲内でこれを許します。本庄知史君。
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。
石破総理とは初めて議論させていただきます。長い解説ではなくて、端的な回答をお願いいたします。先ほども石破語録というような言葉が出ていました。
それで、総合経済対策、補正予算案の決定プロセスについて伺いたいと思います。
先ほど、奥野委員の質問に、総理が昨年を上回る大きな補正予算を成立させたいと発言をされた十月十五日、衆院選の公示日、この段階で積算はあったのか、積み上げはあったのかと問われて、総理はこう答えました。全て積算が終わっていたわけではないと。
失礼ですけれども、私、子供の答えかと思いましたよ。宿題は終わったのかと言われて、全部終わったわけではない、では、どれだけ終わっているんですか、こういう話です。
それで伺いますが、この十月十五日の段階で、石破総理は、昨年の補正予算の十三兆円を上回る積算になるということを把握されていたんですか。明確に答えてください。
○石破内閣総理大臣 そのような決めつけの議論というのは本質をそらすと思いますが、あえて申し上げれば、能登半島のあの地震というものを考えたときに、予備費では対応できないということを考えれば、それは昨年の補正の規模を超えるということは間違いないという確証はございました。
○本庄委員 それが何で超えるという根拠になるんでしょうか。予備費の金額は決まっていたんですか。昨年並みの予備費を積むという前提であれば理解しますが、そこも決まっていないのであれば、補正予算の、経済対策の全体像というのは私はまだ分からなかったと思います。
それで、政府参考人に伺いたいんですが、十月四日の経済対策の指示、そして衆院選の公示日、石破総理の発言、そして十一月の二十二日に経済対策の決定、こういう過程の中で、今回の国費十四兆円という数字が固まったのはいつですか。お答えください。
政府参考人です。内閣府か財務省か分かりませんが、いずれかお答えください。それから、総理に報告をいつしたのかも教えてください。
内閣府に通告をいたしております。内閣府は財務省かもしれないと言っていましたが、いずれにしてもお答えください。(発言する者あり)
○安住委員長 ちょっと速記を止めてください。
〔速記中止〕
○安住委員長 速記を起こして。
加藤財務大臣。
○加藤国務大臣 若干、流れだけ言わせていただきますと、十月四日に経済対策策定に係る総理指示がありました。十月九日に各省から内閣府への施策登録、これが期限が出されました。その後、政府内において調整を進めさせていただき、そして、十月末から逐次、総理にも検討状況を御説明させていただき、最終的には十一月の二十二日に経済対策を閣議決定した、そして二十九日に概算を出したということでありますから、十三・九兆円という意味においては、十一月二十二日の経済対策、これをもって決定した、こういう流れになっています。
○本庄委員 十月十五日の公示日の段階では数字は分からなかった、規模ありきの御発言だったということですね。
官房副長官の青木さんが、総理の発言の翌日にこういうふうにおっしゃっているんです。これから具体的な施策を積み上げ、昨年を上回る規模としていく予定となっている。これは十六日の官房副長官の公式の記者会見の発言です。
総理、もう一回確認します。
この十五日の公示の段階では、十三兆を上回る十四兆だという積算はなかったということですか。いかがでしょうか。
○石破内閣総理大臣 積み上げはございません。
めどとして申し上げましたが、何度も申し上げていますが、デフレからの脱却、デフレに戻らないためにはそれなりの規模は必要だということ、そうすれば、昨年を上回る規模になるというめどを立てるのはむしろ当然のことだと私は思っております。(発言する者あり)
○安住委員長 御静粛に。
○本庄委員 それは結果論、結論ありきで、積み上げではなくて、積み上げただけでしょう。積み上がっただけじゃないですか、総理。
これは、十四兆円の今回の補正予算の数字、規模の根拠なんですね。非常に重要な問いです。私は、野田代表にも、そして昨日の酒井議員にも総理が明確に答えてこられなかったということを非常に残念に思っていますし、やはりこれは規模ありきの経済対策、補正予算だったんだなというふうに考えざるを得ません。答弁は求めません。次の質問に行きたいと思います。
では、どうぞ。
○石破内閣総理大臣 決めつけて答弁を求めないのはおかしくないですか。
それは、先ほど来申し上げているように、積み上げは必要です。まず規模感、それは、デフレに戻らない、そして震災対策ということで、規模感を申し上げ、その後に申し上げたのは、その後に積み上げて、必要な施策を積み上げるということを同時に申し上げておるところでございます。
そこにおいて、御党がいろいろなことを決めつけられますが、これがかくかくしかじか無駄であるということを是非おっしゃっていただいて、御審議に供していただきたいと思っております。
○本庄委員 御自身の御発言ですから御自身が一番よく分かっていらっしゃると思いますが、十三兆を超えるという裏づけは公示日の段階ではなかった、ただ、そうかなという中で、上回るということはおっしゃった、このように私は理解をいたします。あとは見ていただいている方の御判断だと思います。
次に、基金についてお伺いをしたいと思います。特に、宇宙基金ですね。
まず、先ほど、午前中も我が党の重徳議員がこの宇宙基金を取り上げました。それも含めてお尋ねをしたいと思います。
まず、総理は、この宇宙基金の補正予算としての緊要性について、るる力説をされていましたね。緊要性というよりも必要性というふうに私には聞こえましたが、いずれにしても、財政法二十九条は緊要性だけではありません。予算作成後に生じた事由、これに基づいて緊要となった経費だということです。
これも踏まえてお答えをいただきたいんですが、この基金、今年の九月四日の概算要求時点、僅か百億円ですよ、要求百億円。去年もそうでした。それが、補正、僅か二か月、三か月足らずで、突然、三十倍の三千億に膨れ上がっているんですね。去年もそうでした。
なぜ、概算要求時点に百億だったものが、僅か三か月足らずの補正の段階では三千億に膨れ上がるんですか。予見できなかったこと、そして緊要性、この観点から御説明ください。
○城内国務大臣 本庄委員の御質問にお答えします。
令和七年度当初予算の概算要求後、宇宙分野の周辺産業に関して大きな状況の変化が生じました。
例えば、具体的に申し上げますと、米国企業による世界最大規模のロケットの実証試験が成功したり、あるいは、米中において官民による衛星コンステレーション構築が急激に進むなど、国際競争が更に激化しております。また、国産ロケットの海外受注、これは数年前ですと数年に一回ぐらいの受注なんですが、相次いで実現するなど、世界からの我が国に対する打ち上げニーズも増加し、宇宙輸送等の競争力強化を急ぐ必要があるので、可及的速やかに予算措置を行う必要が生じたことから、今般の補正予算へと計上したものであります。
以上です。
○本庄委員 総理、今の大臣の説明を踏まえて答えていただきたいんですが、今の御説明はもう分かっていることじゃないですか。昨日今日いきなり明らかになったことじゃないですよ。そんな単純な政策を展開しているんですか、我が国政府は。違うでしょう。もっと中長期の、長い目で、そして腰を据えた政策に取り組んでいるんじゃないんですか。
それから、ミサイルが飛んだとかアメリカの開発がどうだという話があったけれども、それで慌てて今何かやって、年度内に何かできるんですか。そんな簡単な話なんですか、宇宙政策は。私は違うと思いますよ。
要らないとは言っていない。必要性は精査したらいいと思いますよ。何でこんなに慌てて補正で、二年も連続で、たった百億だった概算が三千億に膨れ上がって、通してください、こういう話になっているんですか。これはエントリー料じゃないですか、補正予算、入れてもらうための。概算、取りあえず何かのっけておけ、こういう話にしか見えませんよ。
総理、いかがですか。
○石破内閣総理大臣 背景は今担当大臣が御説明したとおりですが、私は、既に採択したもの、あるいはこれから採択が見込まれるもの、そういうものを足しますと、既にもう千億を上回っちゃったということが事実としてあるのだと。でなければ、先ほど来おっしゃる緊要性というものを満たすことになりません。
私は、この緊要性というのを満たすのはかなり厳格なことだと正直言って思っておりまして、もう一度同じことを申し上げますが、既に採択済み、あるいは採択予定の各プロジェクトの資金需要のめどというものが、昨年度に基金に措置した予算額に見合う規模に達しちゃったということは事実でございます。
そうしますと、今までの宇宙プロジェクト、いろいろな宇宙関係と申しますか、その部分が、私は必ずしも、いろいろな方々の努力にもかかわらず、十分ではなかったという反省は持っております。
したがいまして、エントリー料というふうなそしりを受けないように、今後はきちんと本予算でも措置をしていかねばならないと考えております。
○本庄委員 本予算でと今おっしゃいましたね。百億じゃなくて、必要なオーダーで本予算できちっと計上していく、補正予算に依存しない、こういうことですか、総理。
○石破内閣総理大臣 補正予算に依存するというのは、そもそも日本語として成り立たないものでございます。
○本庄委員 考え自体は正しいと思います。実行してください。
それから、足りないから、必要だからという話がありましたけれども、法治国家ですよ、財政民主主義ですよ。これは政府自ら基金のルールを作っているじゃないですか。三年分、そして、その三年分の検証をした上で積み増し、これは総理が議長の会議で決めたルールですね。
宇宙の今後十年間の予算は一兆円ですよ。三年分といえば三千億じゃないですか。せいぜい三千三百億ですよ。もう計上してあるんですよ、三年分。去年です、これは。何で今年また残り三年分、要は六年分ですよ、慌てて計上するんですか。基金のルール違反じゃないですか。これは違いますよ、基金のルールの違反じゃないかと言っているんです。総理が議長の会議で決めた基金のルールですよ。
予算決定と同時に、定量的な成果目標を策定する。そして、基金への新たな予算措置は三年程度として、成果目標の達成状況を見て、次の措置を検討する。これは去年の十二月、当時はまだ岸田総理ですけれども、総理が議長となっている行政改革推進会議で決めたルールですよ。これはどうなっているんですか、今回。
担当大臣は要らないです。あなたは査定を受ける立場でしょう。総理が議長ですから。
○加藤国務大臣 まず、先ほど総理からお話がありましたけれども、既に、既定の部分については採択予定のプロジェクトが出てきている。そして、さらに、これがポイントなんですけれども、新たに宇宙分野への関与、裾野拡大が特に期待できる新規のテーマ、そうしたものについて、既存のテーマ、成果目標とは異なる枠組みで今回対応させていただいたということでありますから、これまでにやってきたものに乗せるというのではなくて、新たな分野、これに対して措置をしたということでありますから、基金の点検・見直しの横断的な方針の趣旨に反するものにはなっていないというふうに考えております。(発言する者あり)
○安住委員長 静かに。
○石破内閣総理大臣 五年度と、今御審議いただいております六年度について、これは少し差がございます。
五年度の補正予算の計上分につきましては、いろいろなテーマがございますが、テーマごとに成果目標を、宇宙ですよ、テーマごとに目標を策定、公表して、成果目標の達成状況を確認して、次の措置を検討していくというような形になっておりますが、これを前提として、六年度の補正予算の案では、五年度に措置しましたテーマ及び成果目標とは違うということで、新たな予算措置を伴うものでございます。
両方とも基金ルールにのっとってやっておりますが、それは設定している目標が違いますので、全く同じような算定をしたものではございません。
○本庄委員 二つ申し上げておきますが、まず、事業ベース、事業ごとだとかテーマごとということは何も決めていませんよね。これは基金について書いてあるんですよ。皆さん自身が決めたルールですよ。基金についての成果目標ですよ。事業ごとなんてどこにも書いていませんよ。宇宙戦略基金という基金としてどうなのかということですよ。事業が変わればまたつけられるといったら、どんどん増えていくじゃないですか。それでいいんですか。意味がないじゃないですか、この基金のルール、そうしたら。
それから、三年分だという枠からははみ出ていくんじゃないですか、もう三年分確保されているんですから。これは、六年分に手をつけようとしているんですよ、まだ二年目なのに。全く骨抜きになっているというふうに私は思います。
その上で、総理はさっき、宇宙基金について、検証成果があるとおっしゃいましたね。
そこでちょっと確認をしたいんですが、政府参考人に。
まず、昨年のこの基金の予算、合計は三千億です。文科省に千五百、経産省に千二百六十億、総務省に二百四十億、計三千億を計上して基金を造成しましたが、これは支出、幾らですか。今、基金から幾ら出していますか。
○竹村政府参考人 お答え申し上げます。
総務省で措置した分については、令和五年度末時点での支出額は約十四万円、残高は約二百四十億円となっております。
また、本年十一月には、国会に対して、令和六年度末時点での見込額として、支出額は二十四億円、残高は約二百十六億円と報告させていただいております。
なお、令和五年度補正予算分については、全てのプロジェクトの公募を完了しておりまして、今年度中にはほぼ全額について資金需要のめどがつく予定でございます。
○本庄委員 文科省と経産省も答弁してください。
○堀内政府参考人 お答えいたします。
文部科学省で措置した分につきましては、令和五年度末時点での支出額は八十七万円、残高は千五百億円となっております。
また、本年十一月には、国会に対しまして、令和六年度末時点での見込額として、支出額は百五十億円、残高は千三百五十億円と報告させていただいております。
なお、令和五年度補正予算分につきましては、全てのプロジェクトの公募を完了しておりまして、本年度中にはほぼ全額について資金需要のめどがつく予定でございます。
以上でございます。
○伊吹政府参考人 お答え申し上げます。
経済産業省で措置した分については、令和五年度末時点での支出額は七十三万円、残高は千二百六十億円となっています。
また、本年十一月には、国会に対して、令和六年度末時点での見込額として、支出額は百二十六億円、残高は千百三十五億円と報告させていただいております。
なお、令和五年度補正予算分、経産省分千二百六十億円については、全てのプロジェクトの公募が完了しており、今年度中にほぼ全額について資金需要の目途がつく予定でございます。
○本庄委員 お聞きのとおり、たっぷり残っています。それからようよう出して、ようよう採択したというのが関の山で、とても検証できるような状況ではないと私は思います。
総理、検証結果はあるとおっしゃいましたが、本当にあるんですか。もう一回答弁してください。
○石破内閣総理大臣 執行状況については、十一月二十二日、国会に報告をいたしております。執行状況についての国会報告が十一月二十二日。また、成果指標等に関します基金シートの作成、公表、こういうことを行いまして、透明性の向上を図っておるところでございます。十分でないところは今の委員の御指摘に沿うところもあろうかと思いますが、私どもとして、執行状況につきましては国会に御報告を申し上げております。
これが単にエントリーするためのお金として千億積みましたというようなものだとは私は理解をいたしておりませんで、これは、補正に頼ることなく本予算で、きちんとした積算の下に、よりそういうものを積み上げていく努力はしていかねばならないと思っております。
○本庄委員 総理は成果の検証があるとおっしゃったんですね。支出の状況だとか指標だとか、そういったことではありません。
その成果の検証を、国会、この委員会に出してください。委員長、よろしくお願いします。
○安住委員長 理事会で協議をします。
○本庄委員 本予算中心でやっていきたいという総理の姿勢は、私も評価します。今年度からやりましょうよ。この補正、来年度に回して、来年度の予算委員会で審議することもできますよ。慌てる必要はないと思いますということだけ申し上げておきたいと思います。答弁は要りません。
半導体の方に移りたいと思います。
今回の経済対策の大きな柱として、AI・半導体産業基盤強化フレームというものが導入されました。私も半導体の重要性は理解しているつもりです。これからの日本にとって、最も重要な産業の一つだと思います。一方で、これまで失敗してきたという経緯もあり、この点もよく踏まえて、この国策とも言える政策を進めていく必要があるというふうに思います。
非常に大きな事業規模、今後十年で五十兆円超の官民投資、この根拠は私はよく分かりませんが、これが根拠があると仮定しましょう。その上で、二〇三〇年度まで、つまりあと七年ですね、六兆円程度の補助、委託、そして四兆円以上の金融支援。これで十兆円以上、エネルギー特会に区分経理して、半導体やAIの支援に使っていこう、こういうすごく大きな話です。
財源なんですが、財投特会から繰り入れる、足りない部分はエネルギー特会からつなぎ債を出すということも書かれています。それから、基金から国庫返納金を一・六兆充てるということも書かれております。あとはGX債、そして金融支援のための財源確保四兆円、こういった大きなフレーム、骨格が経済対策には書き込まれているということです。
これに関連して幾つかお伺いをしたいと思いますが、まず、総理は十一月十一日の記者会見で、支援の原資についてはこれから各省庁間で議論することになるが、赤字国債は発行しない、これだけははっきり言える、こういうふうにおっしゃいました。何を根拠に赤字国債を発行しないとおっしゃっているんですか。
○武藤国務大臣 本庄委員にお答えいたします。
今の赤字国債を発行しないという案件ですけれども、今回策定しました新たなフレームというのは、財政投融資特別会計からの繰入れ、今お話ございました基金等からの国庫返納金ですとか政府保有株式の売却益の活用など、歳出を裏づける財源をあらかじめ特定しており、赤字国債に頼る必要のないことから、赤字国債を発行しないという説明を行ったところであります。
以上です。
○本庄委員 私はすごくミスリーディングな説明だと思いますね。このエネルギー特会のつなぎ債だって、支援がうまくいかなければ焦げつくことだってあり得るんじゃないですか。もっと言えば、GX債だってそうですよ。うまくいくという前提で国民負担が生じない、税金投入は要らない、こういうフレームですよ。私も、うまくいってほしいし、そのために努力しなきゃいけないと思いますが、国債発行が要らないとか国民負担が発生しないと断言してしまうのは、私は、かなりうそに近いと思いますよ。
総理、いかがですか。
○石破内閣総理大臣 今おっしゃいますように、そうならないようにお知恵とお力を賜りたいと思っております。
私どもとして、国債発行によるという方針は取っておりません。そうならないようにどのようにして工夫をしていくかということを申し上げておるところでございます。
先ほどのお話もそうなのでございますけれども、宇宙戦略基金にしてもそうで、であらばこそ、執行状況について国会で報告をしておるということでございます。そしてまた、成果指標というものも必要でございますから、そういうようなシートも作成をいたしております。私どもが何の根拠もなくそういうものをのっけて、エントリーのために使ったという事実はございません。
ですから、そういうものに対して、これから先、本当に宇宙の熾烈な競争具合というのは、テレビを見る、新聞を見る、ラジオを見るたびに私自身も焦燥感に駆られるところでございます。既にそういうようなものが計画も含めましていっぱいになっておりますので、もう一度それを補正予算に計上するということをいたしておるところでございます。
○本庄委員 基金からの国庫納付金等一・六兆円、これについて、最後、少し説明をして質問をしたいと思います。
お配りしている資料にもありますが、これは財務省が作ったものです。今回の補正予算の税外収入の使途ということで、厚生労働省関係の基金等から千八百億円、これは防衛力強化に回ります。一方で、経済産業省関係の一・三兆円、これがこのAI、半導体産業基盤強化の財源の一つになる、こういうふうになっているんですね。
国債を使っていないとおっしゃいましたが、一・三兆円を捻出しているこの基金、これはコロナのときに、マスクの調達だとか、ゼロゼロ融資だとか、経営支援だとか、こういったことに活用してきて、大量の赤字国債で財源調達した基金の残り金ですよ。その一・三兆円をAI、半導体に入れるという話ですよ。赤字国債じゃないんですか、原資は。そして、これは基金の流用ですよ。私は基金のロンダリングだと思いますよ。
総理、いかがですか。
○石破内閣総理大臣 私どもが申し上げておりますのは、新たに発行することなくということを申し上げているのであって、これは全く質が違うものだと思っております。新たな国民負担ということを求めるということはいたしません、そういう意味で申し上げておるものでございます。
○本庄委員 それは詭弁なんですね。これは一般会計からお金を入れるという仕組み自体があるんです。したがって、足りなければ一般会計から、これからも入れることが可能となると思われます。思われますと言っているのは、これは法改正がいろいろ要るんですね。新しい法律も必要です。
これは総理も、代表質問、所信表明演説の中でもおっしゃっていました。これからなんですよ、本格的なスキームは。何でこの補正予算で一・三兆円も基金から流用して、先食いのように始めるんですか。私は、そういう財政との向き合い方がおかしいと言っているんです。
半導体は必要です。支援も必要です。でも、こういうやり方で国策を前に進めていくことは、私は、大きな禍根を残すということを申し上げて、質問を終わります。
○安住委員長 次回は、明十一日午前八時五十五分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時五十九分散会